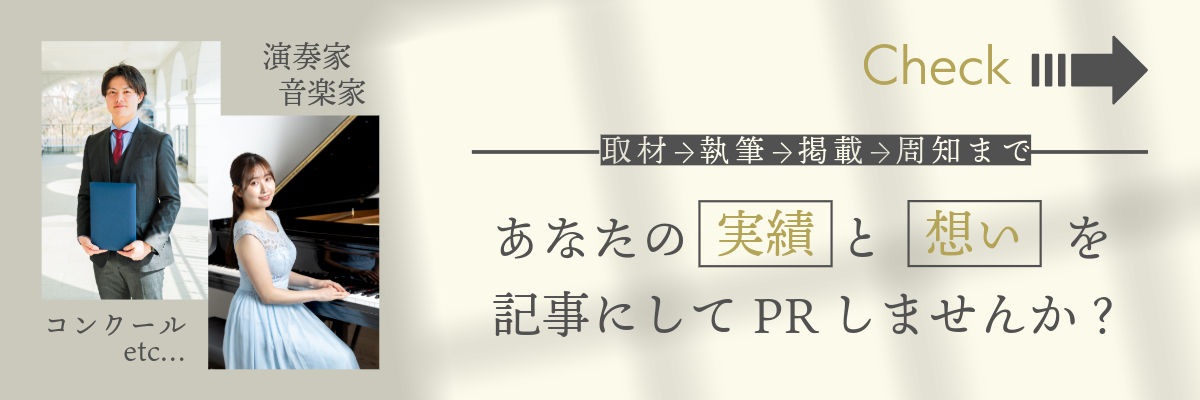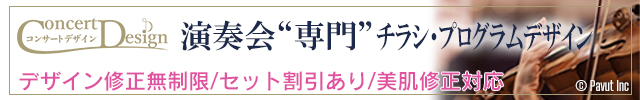これまでのソリストとしての実績から、最新の音楽研究まで。常に歌と言語の最前線に身を置いてきた田辺とおるさんが「審査員」として注ぐ眼差しは、演奏者への敬意に満ちています。
自身の集大成としてコンクールを制作し、運営すること。核心にあるのは、受験者が自らの現在地を正しく知り、次へ踏み出すための場所を創ることでした。「ハードルが高い」と言われることもあるこのコンクールの運営の裏側には、受験者への細やかな配慮と、御自身が歌手として長い間舞台に立ってきた体験が息づいています。既存の枠組みを超えて歩み続ける「国際声楽コンクール東京」の真実を伺いました。
取材・文|編集部
自分にピッタリな音楽コンクールが見つかる!国内外の音楽コンクール情報や結果まとめをわかりやすくご紹介し、次世代の音楽家や音楽ファンの皆様に寄り添います。
プロフィール
田辺 とおる(Toru Tanabe)公式サイト(論文・解説・随筆等を所収)
国際声楽コンクール東京 代表・審査委員長代行
武蔵野音楽大学卒業後、グラーツ音楽大学で研鑽を積む。ドイツ・北ハルツ劇場専属バリトンソリストを経て、欧州各地でオペラ、ミュージカル、俳優、声優として幅広く活動。映画『ラストサムライ』等の吹き替え等も手掛ける。
2009年「東京国際声楽コンクール」を創設。現在は「国際声楽コンクール東京」代表として、年間1000名以上が参加する日本最大規模のコンクールへと発展させた。
教育・研究:国立音楽大学講師、名古屋芸術大学・名古屋音楽大学大学院客員教授等を歴任。東京外国語大学大学院修士号(学術)取得。同大学院博士後期課程、単位取得満期退学。
出版・執筆:『ドイツオペラアリア名曲集』『ミュージカルアリア名曲集』『オペレッタアリア名曲集』をドレミ楽譜出版社より刊行するほか、論文、エッセイなど執筆多数。
──国際声楽コンクール東京で審査を担当されたご感想と、全体としての印象をお聞かせください。
田辺
当コンクールは前身の時代を含めて、2025年で17年目を全うしました。制作の中心は一貫して、審査委員長の川上洋司先生(東京藝術大学名誉教授)、私の妻でコンクール代表代行・審査副委員長の小畑朱実(武蔵野音楽大学教授)と私の三名が担っています。
審査員は地区大会・准本選・本選を合計して500人を超えます。そしてさらにコンクール受験生をお送りくださっている、全国の声楽・ミュージカル指導者の先生方が多数いらっしゃいます。コンクールはこれらの皆さんのお力の結集であることをまず申し上げ、コンクール代表として深く感謝いたします。
当コンクールは部門や年齢層が非常に多岐にわたるため、全体的な総括を述べることは容易ではありませんが、弊会が主催する「プリマヴェーラ声楽コンコルソ」や他社コンクールとの棲み分けが、着実に進んでいると感じられます。実際に、受験者や指導者の方々からも「(それぞれの特徴を理解した上で)意図してこのコンクールを選んで受験している」という声を耳にするようになりました。
当コンクールに対して「ハードルが高い」というイメージを持つ方もいらっしゃると聞いています。しかし、同時にそれは「高い壁だからこそ挑戦したい」という受験者の意欲を引き出すポジティブな要因にもなっていると思います。ただし、実際のデータを見ると地区大会全体の合格率は75〜78%前後を推移しており、決して入り口の段階から門戸を狭めているわけではない、という点もお伝えしておきたいと思います。
── 国際声楽コンクール東京の特徴や強みはどのような点にあるとお考えですか。
田辺
まず、国際声楽コンクール東京は18部門、プリマヴェーラ声楽コンコルソは15部門と、年齢別に極めて細かく部門を設けております。これにより、声楽やミュージカルを志すあらゆる方が、自身の学習環境や水準に合わせて必ず最適な舞台を選べる環境を整えました。
運営面においても、他社コンクールとの差別化を明確に図っています。審査員を多く配置することはもちろん、会場選びにおいても、普段の発表会ではなかなか使用できないような各地のトップクラスの演奏会場を確保することに尽力しております。また、情報の透明性も重視しており、志願者数や合格率といった統計、さらには審査員の個別点数に至るまで、細かく情報公開を行っている点も大きな特徴です。
さらに、受験者の成長を促す「教育的側面」を重んじている点も、私たちの誇れる特色です。例えば、准本選と本選では書面による講評のかわりに、審査員から直接アドバイスを聞ける「講評会」を開催しています。また、規約を詳細に定めることによって、選曲への意識付けや注意喚起といった教育的啓蒙としての機能を持たせています。
こうしたかたちを取っている理由は、制作責任者である私自身が元歌手であり、35歳まで数多くのコンクールに挑んできた経験があるからです。当時の実体験に基づき、受験者として「やってもらって嬉しかったこと」を最大限に反映し、「避けてほしかったこと」を排除する。現場第一の視点こそが、本コンクールの基盤となっています。
── あえて他社が踏み込まないレベルまで、詳細な情報を公開されるのはなぜでしょうか。
田辺
理由はシンプルです。受験者がそれを「知りたい」と思っているから。それに尽きます。
コンクールに参加すれば、当然点数がつき、順位が出ます。自分が獲得した点数の内訳…つまり、どの審査員が何点をつけたのかを詳細に知ることは、受験者にとって非常に重要な情報のはずです。
当会では、准本選と本選において、審査員個別の採点結果をすべて公表しています。これは、私たちが実施している「講評会」とも深く連動しているんです。准本選と本選では10名近い審査員が客席に座り、列を作る受験者一人ひとりに、直接フィードバックを伝える時間を設けています。
2時間以上かけて対話をする際、目の前の審査員が自分を高く評価したのか、あるいは厳しく評価したのかが具体的に可視化されていれば、アドバイスの与え方、受け止め方もより具体的になります。審査員側も、自分の採点が公表されるという前提があるからこそ、その点数に至った理由を責任を持って、自身の言葉で誠実に伝えることになる。情報の公開は、審査の質を高めるための、いわば覚悟の表れでもあります。
私は、コンクールは単なるイベントではなく、一つの「教育的な装置」であるべきだと考えています。単に点数をつけて「また来年頑張ってね」と紙一枚渡して終わるのではなく、一歩踏み込んで教育的な効果を生み出していく。情報の透明性は、受験者が納得感を持って次の一歩を踏み出すために、欠かせない土台なのです。
── 審査員の方々には、運営側としての具体的な審査基準を伝えることもあるのでしょうか?
田辺
たとえば単に「厳しく(または優しく)してほしい」などと伝えることはありませんが、それぞれのステージ(地区大会・准本選・本選)が持つ役割については、明確に共通認識を持つようお願いしています。
まず、全国各地で行う地区大会。合格率は特に設定していませんが、なるべく多くの方に上位ラウンドで「他流試合」を経験してほしいと願い、結果的には全部門平均75-78%程度で推移しています。地元の競争から抜け出して全国レベルを肌で感じることは、大きな教育的効果に繋がると確信しているからです。
日本の伝統的なコンクールの中には、最初に高額な受験料を一括で徴収し、一次予選で一気に人数を絞り込むところもあります。事務効率は良いかもしれませんが、それでは落ちた受験者に教育的効果は残りません。私は入賞者がステータスを作る機会のみならず、あくまで「教育的な装置」としてこの場を作りたい。だからこそ、まずは上の舞台へ送り出すことを優先します。
一方で、准本選・本選となると役割が変わります。 准本選では、審査員に「合否のラインを数字ではっきりさせてほしい」と依頼します。1点差の中に何人も並ぶような曖昧な審査ではなく、審査員自らが責任を持って「この人は通す、この人は落とす」という意思を点数に込めてもらう。それが情報の透明性、ひいては受験者の納得感に繋がるからです。
そして最終ステージの本選。ここではトップクラスの競り合いになります。審査員には「あなたにとってのトップ3には、本年のこの部門の水準がよほど低いと考える場合を除いて、90点以上をつけてほしい」と伝えています。
たまに「今年は高得点を出せない」と、あたかも審査の厳しさをステータスと感じておられるような審査員もいらっしゃるのですが、私たちは世界的な名歌手を待っているわけではありません。今日、この場所で全力を尽くした受験者の中から、責任を持って1位から3位を選び抜く。それが審査員の仕事であり、舞台に立つ者への敬意だと考えています。
── 制作責任者として「受験者がされて嬉しかったことを取り入れ、嫌だったことは排除する」とは、具体的にどのような形で運営やルールに反映されているのでしょうか?
田辺
一言で言えば、「規約は厳格に、運用は柔軟に」という姿勢の徹底です。
まず、当コンクールの規約は他社に比べて格段に詳細です。特に演奏曲のジャンル分けや楽譜の解釈については、かなりうるさく書いています。なぜかと言えば、それが教育だからです。 今の受験者は、自分が歌う曲への理解が不足しているケースが非常に多いので。
親任せのエントリーで作曲家や曲名を間違えたり、曲のカットやアレンジが不適切だったり…。そうした不備に対し、私たちは事務的に却下するのではなく、業務的に可能な限りは「ここが違いますよ」と突き返します。修正申告をする過程で、彼らは自分の曲と真剣に向き合い、学習する。規約の細かさは、自覚を促すための教育的装置なんです。
一方で、当日の運用については緩くしています。 私自身、35歳まで国内外で山ほどコンクールを受けてきましたが、ネットもない時代、情報を集めるだけで一苦労でした。当日の段取りにもとても不安がありました。だからこそ、受験者にはなるべく落ち着いて臨んでほしい。 例えば、交通トラブルで遅刻しても演奏順の最後尾で歌えるように調整しますし、伴奏者が急病になれば、当会の誇る公式伴奏の名手たちが即座に代役を引き受けます。リハーサル室が確保できない会場でも、「開演前と休憩時間は舞台上で声出ししていいですよ」と開放しています。
公開演奏であるコンクールは本来、一種の「お祭り」だと思います。ガチガチに緊張している受験者に対し、杓子定規な対応でさらに追い詰めるようなことはしたくない。事務局スタッフが受付で雑談をしてリラックスしてもらうのも、そのためです。
芸術的なルールには厳しく、しかし受験者には、できる限り人間的な配慮をもって誠実なサポートを尽くす。この両輪が、私が行き着いた理想のコンクールの姿です。
── 審査の際、技術面において具体的にどのような視点を重視されていますか?
田辺
技術面については、私たちは審査の際、各項目を細分化して分析的に判断しています。採点表の数字以上に、審査員の頭の中では非常に緻密な思考回路が動いていると考えてください。
技術の欠点は個人差の大きいものですが、多くみられる傾向をあげるならば、声楽もミュージカルも、「副鼻腔共鳴(顔に響かせる、声を前に集めるなどと表現されること)」に指導のテーマが偏りすぎて、他の要素とのバランスが悪くなっていることです。
以下のような問題の原因となります。
・喉頭と舌根が浮き上がりやすい。浮いた喉頭は息もれに繋がるか、逆にそれを抑制しようとして、声帯を締め付ける圧力が強すぎる「喉(を詰めた)声」になりやすい。
・吸気が浅くなり、肺の下部まで吸気して横隔膜を拡張させる動きが不足する。その結果「支え」が弱くなる。同時に、吸気が短く、速すぎる原因にもなる(吸気はなるべく長く、遅く、少量を目指さなければならない)。
・母音を変音させて浅く平たい、潰れた音の原因になる。たとえば「口角を上げて歌う」という指導は大抵、a 母音を ae などに変音させてしまう。
・鼻声にすることによって、「響きを前に集め」ようとする傾向をうむ。口を横開きしてこのような母音を作る際には、下顎の硬直も伴う場合が多い。
日本の伝統音楽や演歌、浪曲などはこのような発声を使うので、もしかしたら日本人の感覚のなかに根付いているのかもしれません。しかし西洋音楽や西洋の言語による歌唱には馴染みません。
技術は「○○という声をだす」という具体的なヴィジョンがあってはじめて機能する方法論です。それは名演奏の記憶と発声理論の研究によって培われます。特定の技術に偏ったり、技術指導の言葉に拘泥して「とにかくこう歌えばよい」と盲信することは大変に危険です。
── では表現の面ではいかがですか?
田辺
技術と同じくらい重要なのが、作品の様式や内容に即した表現ができているかという点です。よく「演奏者の個性」という言葉が使われますが、私は、演奏者が自分自身の個性を意識することは良くないと考えています。
演奏者は、あくまで作品の再現という命題を担った「作品の僕(しもべ)」であるべきです。個性について悩むよりも、歌曲であれば詩の主人公、オペラやミュージカルであればその役の人物が何を考え、感じ、どう生きているかを徹底的に掘り下げるべきでしょう。
たとえばシューベルトの『魔王』を歌うとき、聴衆が聴きたいのは「田辺とおるが歌う魔王」ではなく、舞台上に存在する恐ろしい魔王や必死な父親そのものです。歌い手の影が消え、作品の登場人物が浮かび上がったとき、初めて「表現」が成立するのだと私は信じています。
そもそも、個性というのは演奏者が「出す」ものではありません。それは聴き手が後から判断するものであって、演者が意識した時点で自己顕示になってしまいます。聴衆は演奏者の個性よりも、作品を聞きに来ているのです。
また、演奏者から「感動を届けたい」という言葉を耳にすることもあります。それが演奏者自身の、作品への感動であるならば問題ない。しかし私には「私の演奏によって、聴衆に感動を与えたい」という自己顕示を指しているように聞こえてしまうのです。
たとえば、ある役を演じる際「演者が役になりきっているから素晴らしい」という評価がありますが、私はそれも論理的な矛盾だと思っています。舞台の上に演者「本人」が見えてしまっている時点で、役の人物よりも演技・演奏という「行為」の方が目立っていることになります。
もちろん、演者によって理想とするパフォーマンスの形は異なります。過去に聞いた名演の感動や、自身の解釈によって「この役の理想像はこうだ」という高い志を持つことは不可欠です。しかし、理想の再現を求めて研鑽することは、自身の個性を出そうとすることとは異なります。
その、理想とする形が人によって違うからこそ、結果として第三者の目に個性として映るだけなのです。作品に対して忠実であること。結局、表現者がやるべきことはそこに尽きるのだと思います。
── オペラやミュージカルを歌う場合、語学の問題が避けて通れません。語学学習は歌唱の勉強にどう関わってきますか?
田辺
外国語の歌詞は、個別の発音を学べば歌えるというものではありません。歌唱と語学学習は不可分です。「○○語は勉強していないけど発音だけ教わった」という状態で歌うことは、もってのほかだと思います。理解していない言語の歌は歌えません。少なくともコンクールには不適切です。
ただし「理解」の程度は柔軟に考えるべきです。ペラペラに会話できなければ歌えない訳ではありません。最低限度の文法と詩行の各単語の意味が解っていれば、その曲を学習する素地になると思います。
発音についてはまず、正確を期すこと。たとえば発声技術のために言語発音を歪めてはいけません。「iは喉がつまるからeに、uは響かないからoにする」などという昔の教育認識が、いまだに散見されます。しかし、声楽のベルカント技法では各母音の歌い方が厳密に説明されているので、勝手に他の母音(つまり他の単語)に入れ替えてしまうことは許されません。
とはいえ外国語発音は、本質的には技術ではなく表情の問題です。単体の単語ではなく文章全体のなかで、その音節の発音を考える必要があります。作品解釈や音楽表現の問題なのです。
たとえば英語のth やドイツ語のch など、各言語には特有の発音もありますが、多くはieaouといった母音やt, d,s などの子音のように、どの言語でも一見同じにみえます。しかし全ての言語音声には、その言語に独特の「色合い」があります。母音も異なりますし、子音にもたとえばtなどのように、英語・ドイツ語・イタリア語・フランス語で相当異なるものがあります。
これらを可視化するものは発音記号(International Phonetic Alphabet/IPA文字)です。通常記号だけでは、言語間の差は十分に表現できませんが、膨大な補助記号を組み合わせれば、言語音声は理論的にはすべて文字化することができます。ただし歌手は音声学者ではないので、これを耳で聴き分けて口腔で再現しなければなりません。このような「色合い」のうえに「表情としての発音」が成立します。
──外国語発音を歌唱技術的に理解した上で、表現のツールとして取り込まなければならないという事ですね?
田辺
技術と表現は、いうなれば互いが互いに奉仕し合う、表裏一体のものです。しかし、学習者はこれを二つ別個のものとして捉えがちです。
技術に関しては、言語発音、正しい音程、正しい響きの作り方などの各要素がバラバラに捉えられ、往々にしてそのどれか一つに極端に傾斜した歌唱教育がなされることも少なくありません。
反対に、表現上の課題への取り組み方はどうでしょうか。技術的研鑽の不足しているところで「こう歌えば感情が伝わるかな?」と考えてしまうと、気まぐれな試行錯誤に陥ります。私は、表現とはストイックで論理的な探求の果てに滲み出てくるもの、と考えています。
──技術の研鑽が表現に資するというお話しはよく分ります。しかし現実には、技術を研鑽しただけで、表現まで自動的に豊かになることは、なかなか難しいと思います。表現の研鑽のためにヒントがあれば教えてください。
田辺
たとえば「役の人物に憑依する」などといえば聞こえはいいのですが、実際にはもっと分析的な作業です。歌詞を読むヒントとして私はいつも、次の3つの設問を提案しています。かっこの中は、想定している反問です。
1:作者はなぜ、この内容の詩行を書いたのか
(違う内容が来るとすれば何が考えられるか。その場合、文脈はどう変わるのか)
2:作者はなぜ、この内容にこの言葉遣い・表現・語順を選んだのか
(別の言い方をするならば、どういう表現が考えられるか)
3:作者はなぜ、この内容のあとに、このような次行を書いたのか
(別の内容への発展を想定するならば、何が考えられるか)
独白であるアリアや歌曲は、このような必然的連関を演奏者が創出しなければなりません。どこにも答えは書かれていないので、自分だけの「解」を創るのです。歌唱表現の説得力が増します。これは外国語も日本語も同じことです。
お勧めするのは、ノートの左に詩行、真ん中に設問への回答、右に「もし別バージョンならば」という反問への回答を書くこと。コンクールに出すような歌い込んでゆく曲には、ぜひこのような頭脳労働をすると良いでしょう。
──つまり歌詞を、歌手自身のものとして読み込んでゆくということでしょうか?
田辺
その通りです。演奏者は歌詞、楽譜、背景などの情報を勉強しますが、解説者ではないので、それだけでは不十分です。これらの情報を基盤として、自分自身にとっての必然性を構築しなければなりません。それは演奏者の主観の産物です。つまり「(正確な情報に基づいた)勝手な解釈」です。しかし説得力があれば、聴衆も共感します。
詩行には「顔」があります。なかには表現主義詩などのように難解なものもあります。オペラ台本でも、セリフの根拠が分かりにくい抽象的な歌詞はたくさんあります。こういった「辻褄」の見えにくいものは、無理に辻褄を合わせないこと。もしかしたらその詩の意図は論理的な脈絡ではなく、単語単位のインパクトであるのかもしれません。つまりそのような詩行の「顔」、要するに何を訴えている言葉なのかを、自分なりに把握すると表情作りのヒントになります。
また、詩の「立ち位置」も大切です。詩は「誰か(A)」が「誰か/何か(B)」を観察した結果です。A/Bは、自分(作者)である場合も、他者の場合もあります。Bは物体や現象もありえます。まずどんな歌詞であっても、誰が何を観ている言葉なのかを明確に理解することが大切です。
そしてAとBの「距離感」を自分なりに解釈すること。たとえば一人称詩のAは私です。そしてBも私の場合が多くあります。しかしBの何を、Aは観察しているのか。自分(A)が自分の「心(感情)」(B)を見て言語化している場合、ABの距離はとても近い。
一方Aが理性的に自分をみる場合もあります。感情ではなく自分の思考や連想の回路を、みているように思われる詩です。また「狂乱」など、「自分」に別の要素が加わっていることもあります。正気を逸しているならばAは揺らぎ、観察を矛盾なく展開することはできない。つまりAという実体そのものに乏しい。
あるいはオペラアリアの場合。Aは(挿入歌でもない限り)ある役のセリフなのだから常に「自分」です。しかし観察する対象物は何か、自分との距離感はどうか。これらは詩行の展開にあわせてかなり変化し、それが感情の濃淡になっています。
── 言葉の重要性を痛感されているからこそ、具体的な学習方法についても受験者にアドバイスされているそうですね。
田辺
はい。本選の表彰式などでもよく話すのですが、受験者には『カフェトーク(オンラインレッスン)』などのプラットフォームを積極的に活用しなさいと伝えています。今の時代、ウェブ会議システムを使えば、地球の裏側にいるネイティブスピーカーと安価に、かつ手軽に繋がることができる。これを使わない手はありません。
私が特におすすめしているのは、自分の歌う曲の歌詞をネイティブに「朗読」してもらうことです。まず本物の言語の響きを耳に入れ、次に自分が朗読して直してもらう。勉強の過程にこのような訓練を差しはさむと、歌唱のクオリティは見違えるほど良くなります。
手頃な価格で、ネイティブの生きた言葉に触れられる。こうした便利なツールを使いこなし、効率的に、かつ本質的に技術を磨いていく。それが今の若い世代に求められている「学びの形」ではないでしょうか。
── 「声」は身体そのものを楽器とするため、日々の体調やメンタル管理が極めて重要だと思います。プロとして、また審査員として、この難しさにどう向き合うべきだとお考えですか?
田辺
メンタル面に関しては、器楽奏者も声楽家も本質的には変わりません。先ほどの「演奏者の個性」の話にも通じますが、演奏において一番の妨害要素となるのは、「良い演奏をしたい」「褒められたい」という虚栄心です。これをいかに排除し、作品の再現だけに集中できるか。それが演奏家に課せられた最大の課題です。
一方で、健康管理は器楽奏者よりもデリケートです。とりわけ呼吸器系のコンディションは歌唱に直結します。しかし、ここで伝えたいのは「不調時の向き合い方」です。
よく受験者から「今日は調子が悪かった」という言葉を聞きますが、調子が悪いときに無理をして普段通りの演奏をしようとしてはいけません。優れた演奏家とは、「今日は調子が悪いから、こういう計画で演奏しよう」と冷静にコントロールできる人のことです。
歌唱においては、不調時は好調時よりも音量を1〜2割下げることが鉄則。自分の体調という現実に即して、その日に出せるベストな設計図を書き直す必要があります。
── なぜ「もっと出そう」とするのではなく、あえて「下げる」ことが正解なのでしょうか?
田辺
これは人間心理的な罠なのですが、調子が悪いときほど、出ない声をなんとか補おうとして無理に押し出そうとしてしまうんです。自分自身の経験からも言えますが、その選択は100%失敗します。
考えてみてください。例えば、どこかのタンポが緩んで息が漏れている管楽器や、調律が狂っているピアノがあったとします。その楽器で無理やり大きな音を鳴らそうとすれば、ただ雑音が増え、聴くに堪えないものになるだけですよね。声という楽器も全く同じです。楽器の状態が整っていないのなら、その不完全な状態に合わせて、ダウンサイズした設計図を引き直さなければなりません。
もちろん、コンクールという競争の場で音量を下げるのは勇気がいります。しかし、全ての演奏者にとって最も大切なのは、今日の自分の体調でいかにベストなパフォーマンスを構築するかという視点です。
日頃のチェックポイントをそのまま持ち込むのではなく、技術面を少しずつ縮小しながら扱っていくこと。そうすることで、不調ゆえの汚い響きを緩和し、破綻を防ぐことができるのです。ただし、単に小さく歌えば声が抜けてしまいますから、「呼気圧の支えや喉頭のポジションなどの身体的条件は変えずに、音量だけを下げることによって、質の低下を最小限に抑えて歌いきる技術」を普段から練習しておく必要があります。
── そうした「不調時のコントロール法」は、一般的に教わることができるものなのでしょうか?
田辺
「一般的に」はわかりませんが、優れた指導者はアドバイスしていると思います。ただ一方では、不調の時には本人がナーバスになりますので、精神面ばかりアドバイスしようとしている指導者も少なくないようです。
── 実際に、今大会のグランプリを受賞された方も「当日は不調だった」と仰っていました。審査員として、やはりそうした不調は感じるものですか?
田辺
いいえ、全く感じませんでした。彼の演奏は、文句なしのダントツな1番でしたから。「こんなに素晴らしい方がうちのコンクールに来てくれたんだ」と、ただ圧倒されて聴いていました。
本人の調子がどうであれ、それを客席に悟らせず、最高の結果を出す。「設計図の引き直し」が完璧に機能している証拠です。
── 公式サイトのご挨拶でも触れられていましたが、韓国人の圧倒的な演奏レベルに驚かれたそうですね。今の日本と彼らとの間には、一体どのような「差」があるのでしょうか?
田辺
それは個人の才能や身体条件、あるいは言語などの差ではなく、声楽教育の差ではないかと感じています。誤解を恐れずに申し上げれば、日本の声楽教育は多くの指導現場において、もしかしたらアップデートが遅れているかもしれません。
たとえばかつて日本人が抱いていた「声は強いが言葉は疎か」という韓国人歌手への印象は今日、もはや感じられません。おそらくは、欧米の第一線でキャリアを築いた歌手たちが、最新の知見を持って指導にあたっているからではないかと思います。
韓国にも日本にも、良い指導現場も悪い現場もあるとは思います。一概に括ることは難しいでしょう。しかし日本の声楽分野では、語学、音声、発声技術などへの理解が十分ではないまま、何十年前かの(つまり指導者本人が学生だった頃の)指導方法を慣習的に継続している現場は、少なくないと思います。
また一方では、留学に対するハングリー精神が異なるのかもしれません。今の日本の若者は「お金がない」からと、留学を諦めてしまう人が少なくない。しかし、私たちの時代も学生は貧乏でしたが、プロを目指すなら留学しない選択肢などありませんでした。一方で、韓国の学生たちは、世界で実績を残さなければ母国でも仕事ができないという厳しい現実の中で、必死に外の世界へ飛び出していきます。
私は決して「打倒韓国」などという、勝ち負けを意図している訳ではありません。ただ、お隣の国のこのような事情を紹介することによって、日本に刺激をもたらしたいのです。それは私たちが担っている、声楽教育の底上げに寄与すると信じています。
── 参加者目線と公平性をここまで徹底して追求し、実現されているコンクールは他に類を見ません。その強い原動力はどこにありますか?
田辺
発端を辿れば、私自身がドイツで20年ほど舞台に立ち、日本に戻ってきたときに感じた違和感にあります。2009年にこのコンクールの前身を立ち上げた際、日本の歌唱教育には少し浦島太郎のような心境で問題意識を持ちました。
そして今、65歳という年齢を迎え、私はこの活動を一種の「終活」だとも捉えています。もちろん、いつ人生の幕が下りるかは分かりません。しかし口幅ったい言い方で恐縮なのですが、体験を通じて私が蓄積した情報や確信のなかには、もしかしたら「私しか日本の後世代に残せない」ことがあるのではないか、とも感じるのです。嫌われ役になっても正論を吐きたいという意気込みなのかもしれませんが。
世界で戦える次世代を育てること。コンクールに仕込んだ公平性、透明性、教育性は、専攻の各部門においてはこの目的のために機能しています。ただしこれは、愛好者部門でも同じことなのです。公平に透明に教育的に採点され、講評されることは全部門にとって大切だと考えています。
── 今後の展望として、新たに構想されていることはありますか?
田辺
具体的なプランをガチガチに固めているわけではありませんが、テーマとして持っているのは「アフターケア」の充実です。
コンクールで入賞して終わり、ではなく、その後の演奏機会やキャリア形成をどう支援できるか。以前、私が携わっていた組織ではプロモーターとしてのノウハウを活かした披露演奏会も行っていましたが、今はまた違う形での展開を模索しています。
実は嬉しいことに、すでに外部からのアプローチという形でその芽は出始めています。本選には大手芸能事務所のマネージャーなども来場しており、実際に入選者がスカウトされ、所属が決まったケースもあります。
また、過去の優勝者が立ち上げた企画とのコラボレーションで、ミュージカル部門の最高位に入賞した方に、大きなステージでの出場権を提供するといった取り組みも始まりました。こうした柔軟な連携を通じて、若き才能が世に出る機会であり続けたいと考えています。
──国際声楽コンクール東京へ参加を検討している方や、音楽を志すすべての方へのメッセージをお願いします。
田辺
音楽を演奏したいと思う人にとって、コンクール受験は「必須」ではありません。芸術作品の演奏を数字で評価することについては、私自身、根源的な矛盾を感じています。
しかしながら、私がコンクールを制作している理由は他者の演奏と自分の演奏を比較することが、技能的にも精神的にも、そして芸術的にも成長するための大きなエネルギーになると信じているからです。私自身もその道を辿ってプロ歌手になり、35年間舞台に立ってきました。
ただし、「比較」にはガイドが必要です。演奏者が独りよがりに自己や他者を評価してしまうと、往々にして冷静な分析を損なう恐れがあります。そのために私たちは、紙に書いて渡す講評だけでなく、講評会を通じて審査員の分析を直接お伝えしているのです。
芸術作品の演奏が「いつ、どのように上達するのか」は、なかなか測りがたいものです。しかし諦めず、指導が間違っていなければ歌は必ず上達します。コンクールでいえば、目に見える形で「順位」が上がります。私たちは、継続的に挑戦してくださるリピーターの皆さんからそのことを痛感し、大きな勇気をもらっているのです。
当コンクールは地区大会から本選まで、すべての大会を無料で一般公開しています。一人でも多くの方に受験者の「熱量」を肌で感じてほしい。そして歌を志す人が互いに刺激しあい、成長できる仕組みを作っていきたい。そんな想いで、これからも柔軟に、新しいことにはどんどん挑戦してゆきたいと思っています。
インタビューを終えて──編集後記
田辺さんからのお言葉から強く感じるのは、一つのコンクールを支える揺るぎない哲学と現場を知り尽くした一人の音楽家としての深い愛情です。
田辺さんが繰り返された「教育的装置」という言葉。それは、リスクを承知で審査員の点数まで開示する誠実さや「不調な時こそ無理をしない」といった、舞台に立つ者への具体的で優しい助言に裏打ちされていました。そこにはただ順位をつけるだけでなく、受験者が自分の足で次の一歩を踏み出せるようにという、親心のような温かな眼差しが感じられます。
日本の現状を案じ、韓国のレベルの高さに警鐘を鳴らす言葉は、時にハッとするほど鋭いものでした。しかし、自らを「浦島太郎」と呼び、この活動を人生の「終活」だと語るその姿には、嫌われ役を買って出てでも、後に続く人たちに「本物の世界」を遺してあげたいという、純粋で孤独な覚悟が滲んでいました。
厳格な規約や厳しい提言。そのすべての根底にあるのは「音楽を志す人が、迷うことなく正しく報われてほしい」という切なる願いです。国際声楽コンクール東京は、単なる競い合いの場ではありません。自分自身という楽器、そして素晴らしい音楽作品に誠実に向き合おうとするすべての人にとって、ここは日本で最も「厳しく、そして最高に優しい場所」なのだと確信しました。お忙しいところ、貴重なお話をありがとうございました。
国際声楽コンクール東京の概要については下記をご覧ください。
国際声楽コンクール東京の結果については下記をご覧ください。