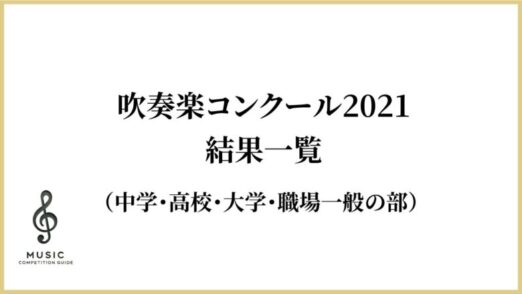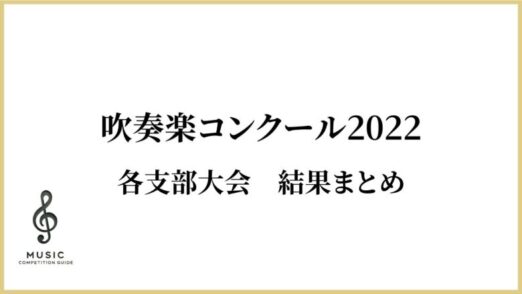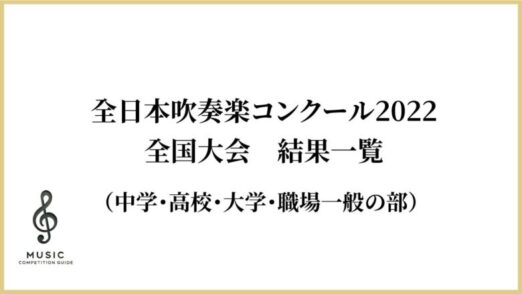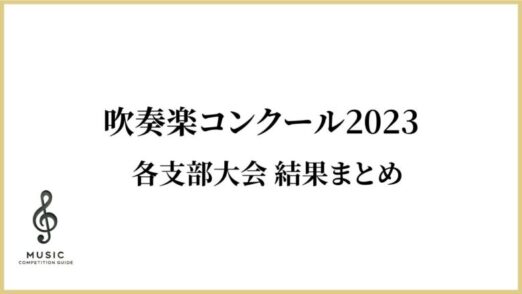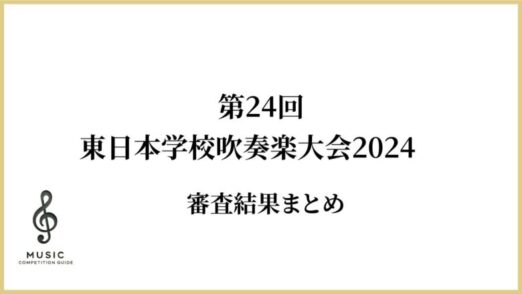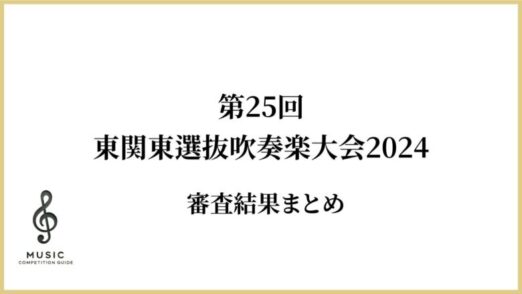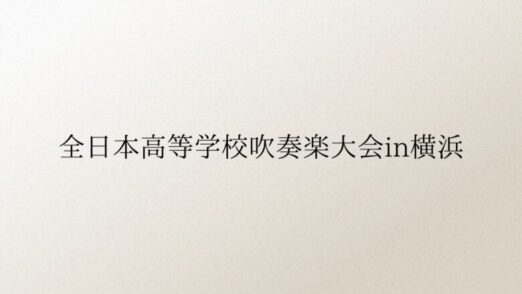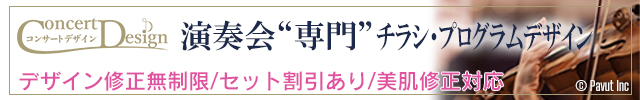静岡・愛知・岐阜・三重・長野の5県で構成される東海支部は、吹奏楽の盛んな活況エリア。教育的活動も精力的におこなわれており、オーケストラ的な美しい響きとアンサンブル力の高さで知られています。
本記事では、そんな東海エリアから選りすぐりの強豪10校とそれぞれの直近5年の実績をご紹介!各学校の気になる取り組みや強み、魅力もあわせて解説します。
特に各校の選曲や練習スタイルは見逃せません。2025年の全日本吹奏楽コンクールが始まる前に、ぜひチェックしてみてくださいね。
日進市立日進西中学校(愛知県)
直近5年の全国大会出場は、2021年(銀賞)、2024年(銀賞)。愛知県を代表する強豪校の一つです。
全日本大会では安定して上位の成績を収め、豊かな音楽性が高く評価されています。特に2024年の演奏では卓越したリズム感と色彩感で会場を沸かせました。各パートのバランスと響きの明瞭さが特徴で、曲のドラマを堂々と描き切る表現力を持ちます。
長年にわたり名指導者の下で培われたテクニックと部員の主体性が伝統として受け継がれています。現在は後藤新治先生の下で基礎合奏やセクション練習に力を注ぎ、練習を進めています。クラシックの序曲からバレエ音楽まで幅広い選曲に挑戦。曲の背景を深く理解した表現が強みです。
日進市立日進中学校(愛知県)


この動画を YouTube で視聴
直近5年の全国大会出場は、2023年(銅賞)。同じ日進市の姉妹校として西中と切磋琢磨する存在です。2023年に東海大会で金賞を受賞し、全国大会出場を果たしました。
久々の出場となった2023年全国大会では、自由曲に喜歌劇「天国と地獄」序曲を選び、伸びやかな歌心と木管セクションの流麗なパッセージで会場を魅了しました。
部員同士の仲が良く、一体感のあるハーモニーが持ち味です。西中と合同で研修会を行うなど交流も盛ん。合奏練習や表現力の育成に力を入れています。クラシックの大曲や海外の著名な作品にも積極的に挑戦する姿勢が光ります。
碧南市立南中学校(愛知県)
直近5年は全国大会に出場していませんが、2019年に力強いサウンドで高い評価を得て、愛知県代表として東海支部大会に出場を果たしています。東海支部大会では鈴木英史作曲のシンフォニック・ポエム「大いなる約束の大地~チンギス・ハーン」を雄大に演奏し、銅賞を獲得しました。
吹奏楽が熱心な土地柄もあり、小学校バンドからの継続者が多く基礎力が高い点が強みです。少人数でも一人ひとりが複数の役割をこなし、アンサンブル力を高めています。
また、合奏前の基礎トレーニングや歌唱を通したフレーズ練習などに重点が置かれ、楽曲の情景をイメージする指導が徹底されています。選曲は物語性のある邦人作品を選曲するなど、ドラマチックな表現にも取り組んでいます。
浜松市立湖東中学校(静岡県)
直近5年の全国大会出場は、2021年(銅賞)、2022年(銅賞)。久々に全国大会へ駒を進め、その実力を見せつけました。
2021年の全国大会では、豊かな響きと色鮮やかな演奏で会場を魅了し、大舞台を堂々と演じ切りました。2022年大会では中橋愛生作曲「時の跳ね馬~吹奏楽のための」を巧みに表現し、審査員からも好評を得ています。
湖東中は浜松市内でも近年急成長したバンドで、地元の吹奏楽関係者からも注目されています。OBが講師として練習を手伝うなど地元のサポートも厚く、部員の士気も高いのが特徴。今後の活躍が期待されます。
浜松市立南部中学校(静岡県)
直近5年では全国大会に出場はしていないものの、2019年に静岡県代表として東海支部大会に出場。中橋愛生作曲の「時の跳ね馬~吹奏楽のための」を演奏し、銀賞を受賞しています。
2019年には音のエネルギーに満ち溢れた演奏で会場を沸かせました。銀賞に輝いた要因として、木管と金管のバランスの良さ、打楽器の精確さが挙げられ、審査員からも高評価を得ています。
南部中は古くから県大会上位の常連校で、地元での信頼も厚い学校です。指導陣は基礎合奏に独自のメソッドを取り入れ、部員の自主性を促すスタイル。選曲傾向として、近現代の邦人作品やエネルギッシュな曲を得意とし、バンドの持ち味である明快なサウンドを活かしています。
松本市立鎌田中学校(長野県)
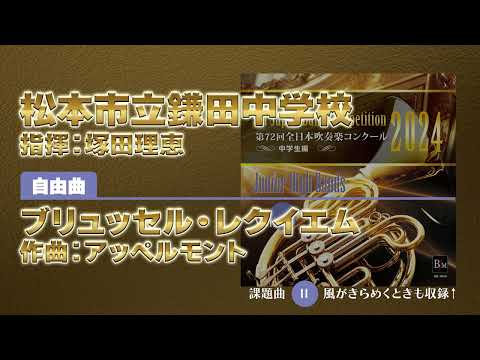
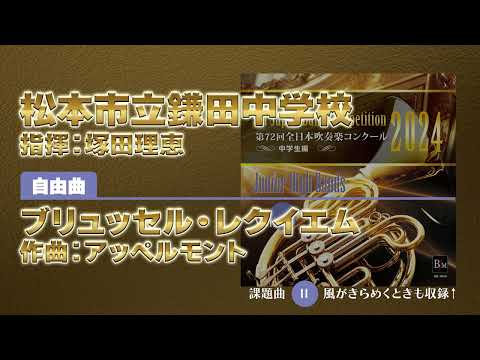
この動画を YouTube で視聴
直近5年の全国大会出場は、2021年(銀賞)、2022年(銀賞)、2023年(銅賞)、2024年(銀賞)。近年4回連続で全国大会に出場している屈指の名門校です。また、2022年には東海支部大会で最優秀団体に贈られる朝日新聞社賞を獲得しました。
いずれの年も楽曲の世界観を深く表現。特に2022年の演奏では精緻なアンサンブルと表現力が高く評価されました。管楽器それぞれの美しい音色とダイナミクスの幅広さ、そして音楽の構築力が際立っており、「松本サウンド」と称される透明感ある合奏が大きな特徴です。
部員たちは曲想を深く理解しつつ、主体的な表現を追求。編成上の工夫としては、各パートの役割を明確化し少人数でも厚みのある響きを作っている点が挙げられます。部内の結束力も強く、一丸となって練習に励む姿勢が強豪たる所以です。
松本市立梓川中学校(長野県)


この動画を YouTube で視聴
直近5年の全国大会出場は、 2023年(銅賞)、2024年(銅賞)。2024年の東海支部大会では朝日新聞社賞(最優秀賞)に輝いており、その安定感が光ります。
2023年全国大会での演奏では、初めての出場ながら緊張を感じさせない伸びやかな音楽を奏でました。朝日新聞社賞を獲得した2024年の演奏も、高い技術力と音楽性で審査員から好評を得ています。
梓川中は松本市郊外に位置し、過去には1970年代に全国大会連続出場の経験もある伝統校。指導面では基礎の徹底とアンサンブル練習の充実が特徴で、特に少人数でも一糸乱れぬ合奏力に定評があります。また、各奏者がソロ的な意識を持って演奏することで全体の響きを充実させている点も特筆に値します。
長野市立裾花中学校(長野県)
直近5年の全国大会出場は、 2022年(銅賞)。長野市立裾花中学校は、長野市勢として久々に全国大会に名を連ねた実力校です。
2022年は自由曲に西村朗作曲「秘儀IV〈行進〉」という難曲を携えて挑みました。全国大会では緊迫感あふれる演奏で健闘し、銅賞を受賞しています。複雑なリズムを克服した集中力と、木管の鋭いトレモロの対比が好評を博しました。
裾花中はこれまで1970〜80年代にも全国大会で活躍した歴史を持ち、近年その伝統が復活しつつあります。基礎練習では音程やバランスの追求に時間を割き、シビアな合奏力を養成。選曲面では、邦人現代作品の難曲に挑むこともあれば、海外のクラシック作品や吹奏楽オリジナル作品も取り入れるなど、多彩な選曲が見られます。少人数ながら編成を工夫して迫力を出す技術も高く、長野県勢を牽引する存在として期待されています。
上田市立第二中学校(長野県)


この動画を YouTube で視聴
直近5年では全国大会に出場していないものの、 2019年長野県代表として東海支部大会に出場し、銀賞を受賞しています。東信地方の伝統校の一つで、東海支部大会では安定した成績を収めています。
2019年は「大いなる約束の大地~チンギス・ハーン」を選曲し、繊細な弱音から力強いクライマックスまでダイナミックレンジの広い演奏を展開。木管の透明な響きと金管の柔らかなサウンドが調和し、曲の持つ抒情性を丁寧に表現しました。
選曲は情景描写に優れた邦人作品やクラシックの名曲編曲などを好み、部員の音楽的感性を育てるプログラム作りをしています。編成では各パートにバランス良く人員を配置し、厚みとまとまりのあるサウンドを重視。地域との繋がりも深く、地元での定期演奏会では毎回高い評価を得ています。
大垣市立東中学校(岐阜県)


この動画を YouTube で視聴
直近5年では、 全国舞台から遠ざかっているものの、東海支部大会では安定した成績を収めています。2024年には県大会で朝日新聞社賞を獲得し、東海支部大会では銀賞を受賞しています。
県大会・支部大会で常に上位に名を連ねる大垣東中は、「今年こそ全国へ」と期待される存在。その実力と情熱は県内外のバンドから注目されています。
基礎練習ではロングトーンやスケール練習に加え、独自のハーモニー練習法を取り入れて、どんな会場でも響くサウンド作りを心掛けています。選曲はエネルギッシュな海外作品から和風の邦人作品まで幅広く、毎年異なる作風の曲に挑戦する柔軟性も強みです。
各校とも、それぞれの土地で培った伝統と工夫を武器に、全国大会という晴れ舞台で素晴らしい演奏を披露してきました。選曲の個性や指導体制に違いはあれど、「音楽を心から楽しみ聴衆に届けたい」という情熱は共通しています。
今年は一体どの中学校が東海支部から全国の檜舞台へと進むのでしょうか?東海エリアの強豪校の活躍から目が離せません!