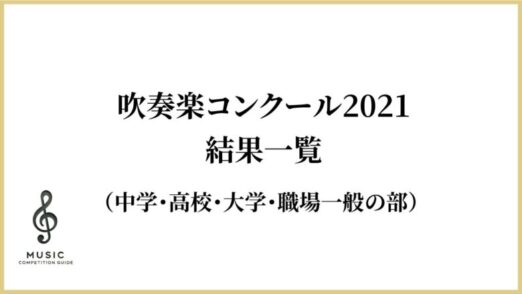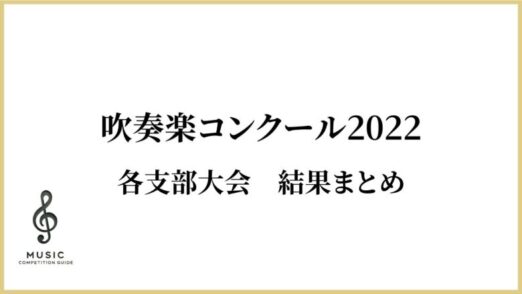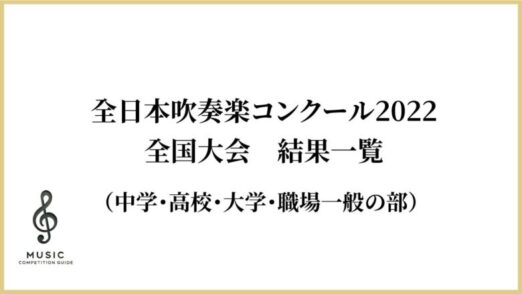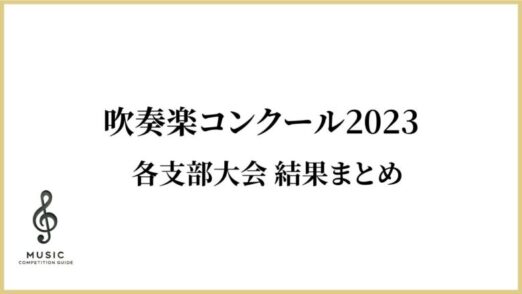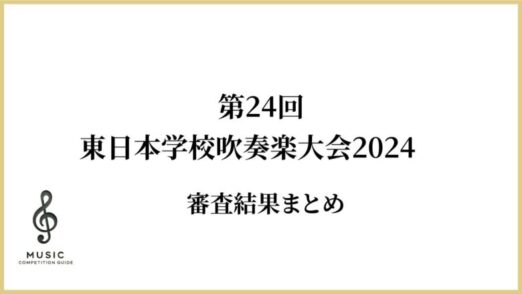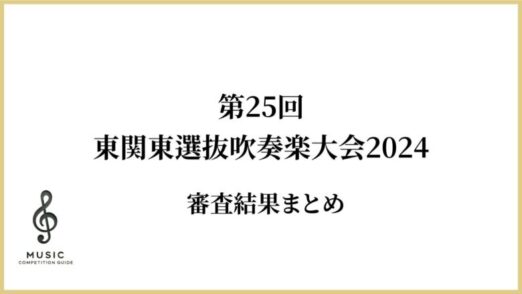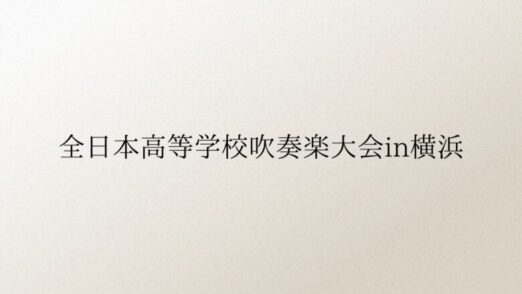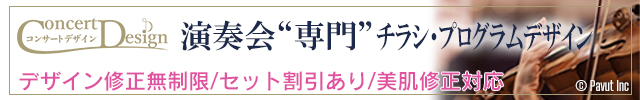「オーケストラ部」でありながら、管楽器+打楽器+コントラバスの吹奏楽編成で吹奏楽コンクールに挑み、2年連続で全国大会金賞に輝いた幕総オケ部。アニメ『青のオーケストラ』のモデルでもある同校だが、気になる今年のコンクール曲はなんとあの「往年の名曲」だった……!
取材・文:オザワ部長
世界でただひとりの吹奏楽作家。神奈川県立横須賀高等学校を経て、早稲田大学第一文学部文芸専修卒。在学中は芥川賞作家・三田誠広に師事。 主著に『吹部ノート 12分間の青春』(日本ビジネスプレス)、『空とラッパと小倉トースト』(Gakken)など。小学校合唱部を描いた『とびたて!みんなのドラゴン 難病ALSの先生と日明小合唱部の冒険』(岩崎書店)は2025年度の課題図書に選定。詳しくはこちら>>
吹奏楽界で注目される「オケ部」
全日本吹奏楽コンクールには全国の支部大会を突破した30校が集まるが、その中でも千葉県立幕張総合高校シンフォニックオーケストラ部(通称・幕総オケ部)は唯一の「オーケストラ部」だ。ヴァイオリンやヴィオラ、チェロといった弦楽器奏者も多数所属しており、オーケストラとしてコンサートやコンクールにも参加している。
一方、部員数は例年200人を超えており、吹奏楽編成でも吹奏楽コンクールA部門(55名まで出場できる大編成部門)に充分出場できる人数がいることもあり、オケ部として吹奏楽コンクールに出場しては好成績を残してきた。全国的に見ても、吹奏楽コンクールに参加しているオーケストラ部は極めてまれだ。
これまで全日本吹奏楽コンクールに4回出場し、4回とも金賞。しかも、ここ最近は2023年、2024年と2年連続で金賞を受賞していることもあり、幕総オケ部は吹奏楽界で注目の存在だ。
自由曲はなんとリードの名曲!
となると、気になるのが今年の課題曲と自由曲。顧問の伊藤巧真先生に聞いてみると、驚きの答えが返ってきた。
「課題曲は伊藤士恩作曲《マーチ「メモリーズ・リフレイン」》、自由曲はアルフレッド・リード作曲の《オセロ》です」
幕総オケ部の自由曲は、一昨年はモーリス・ラヴェル作曲《バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第2組曲より 夜明け、全員の踊り》、昨年は同じくラヴェルの《「スペイン狂詩曲」より I.夜への前奏曲 II.祭り》だった。
幕総オケ部にとって、クラシック曲を吹奏楽に編曲したいわゆる「オケもの」は得意中の得意。クラシック曲をオーケストラ編成で演奏することもあるし、管楽器奏者は弦楽器の音やボウイング(弦楽器の弓の動かし方)に間近に触れることができる。一般的な吹奏楽部に対して大きなアドバンテージがあると言えるだろう。
ところが、今年はオケものを離れて、敢えて吹奏楽の名曲であるリードの《オセロ》で挑むというのだ。
伊藤先生はこう語る。
「私が顧問になってから、吹奏楽オリジナル曲を自由曲にしていた時期もありますが、2019年からはクラシックの名曲を取り上げるようにしていました。そして、今年については、せっかく“吹奏楽”コンクールに参加するので、吹奏楽について深く考えながら挑んでいきたいということで《オセロ》を選曲しました」
強豪バンドの名演にも触発されて
リードの《オセロ》といえば、昨年の全日本吹奏楽コンクールで岡山学芸館高校(岡山)が演奏し、見事金賞に輝いている。それは、吹奏楽関係者の間で語り草になるほどの名演だった。
伊藤先生の今回の選曲は、岡山学芸館高校の演奏からも影響を受けていた。
「やはり学芸館の演奏は強く意識しました。ただ、ライバルとか競うとかではなく、かつて名曲として全国大会で頻繁に演奏されながら、最近はあまり取り上げられなくなっていた《オセロ》を学芸館が素晴らしく演奏してくれました。それを聴いた私は、学芸館の中川重則先生が『いい曲はいまも昔もいい。いい曲をいまこそ演奏しよう!』というメッセージを発せられているように思えたんです。《オセロ》には芳醇な響きの魅力がありますし、楽譜も非常に巧みに書かれています。うちの部員たちにも、そんな名曲に触れさせたいと考えたんです」
伊藤先生の言葉にもあったように、もともとシェイクスピアの悲劇のために書かれた《オセロ》という曲はかつて吹奏楽コンクールの人気曲だった。特に、天理高校(1981年)、神奈川県立野庭高校(1986年)、北海道札幌白石高校(1987年)の全国大会金賞の演奏が名演として知られている。
「《オセロ》は全5楽章あり、コンクールには時間制限があるので全部演奏することはできません。どこかをカットするのですが、今回うちでは天理や野庭、札幌白石と同じように第1・3・4楽章を演奏することに決めました」
演奏に込められた深いメッセージ
《オセロ》を演奏するのはいわば名曲のリバイバルだが、伊藤先生は「指導法のリバイバル」をも構想している。
「いまでは部員一人ひとりがチューナーを持ってチューニングしたり、合奏にハーモニーディレクター(基準音を出したり、さまざまなリズムを再生したりなど、多くの機能を備えたキーボード)を使ったりするのが当たり前になっています。ですが、そういった機器が導入される前でも名演はありました。よくよく考えると、音楽家を育てるならまず機器に合わせるところからは始めないはず。それでは音が生きてこないと思うんです。なので、機器に頼る前に、ソルフェージュを中心とした練習で曲づくりをしていきたいと考えています」
良い演奏を届けるだけでなく、往年の名曲の素晴らしさを再発掘して伝え、そして、指導法についてもメッセージを発信する―—。今年の《オセロ》には伊藤先生の思いがたっぷり詰まっているのだ。
すでに各地でコンクールの地区予選がスタートしている。幕総オケ部は8月の千葉県大会でシード演奏を披露し、その後の本選大会で今年最初の本番を迎える。もちろん、目指すのは東関東大会を経て全国大会に出場することだ。
コンクールの結果も大事だが、幕総オケ部がつくり上げる《オセロ》がどんな音楽になるのか、いまから楽しみでならない。