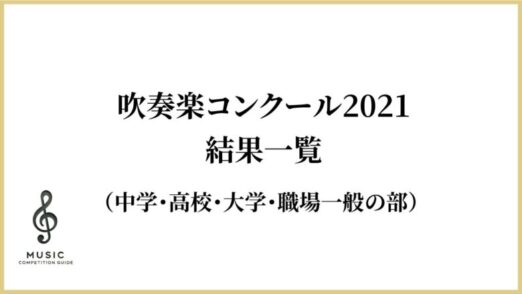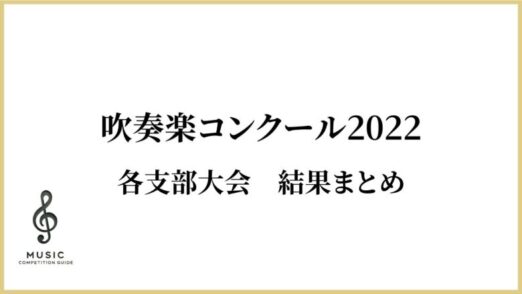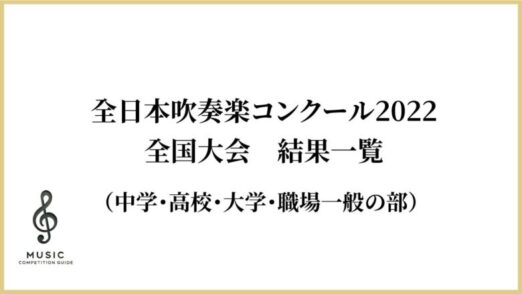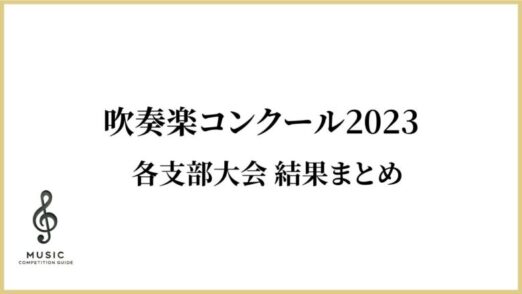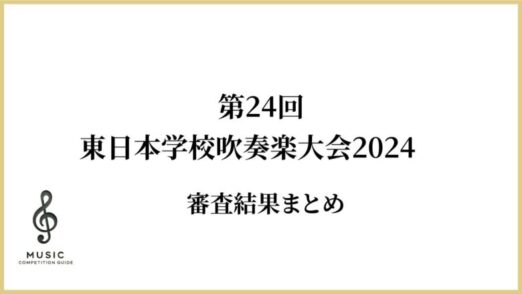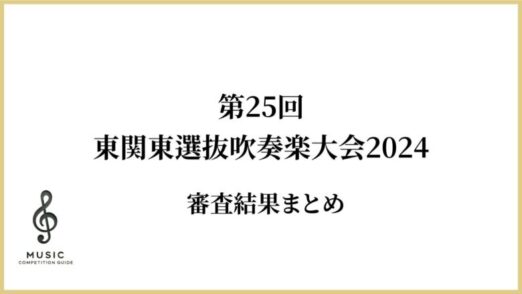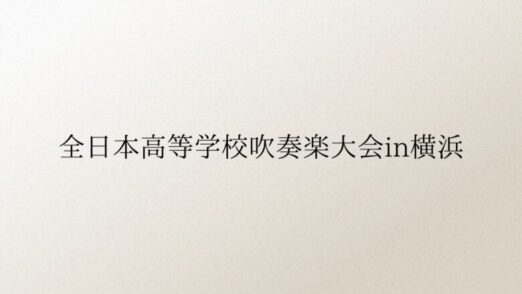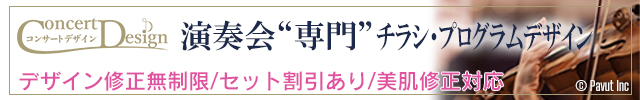東京支部は東京都のみで構成される単独支部。多くの団体がしのぎを削るなか、全国大会へ進むのは狭き門です。練習時間も限られる中学生バンドは、どうやって全国の檜舞台へ駆け上がるのでしょうか?
本記事では東京エリアで特に輝きを放つ強豪10校を厳選して紹介!各学校の取り組みや強みなどにスポットをあてて、特徴を解説しています。
全国大会進出が期待されるフレッシュで個性豊かなバンドの数々。その魅力をぜひチェックしてみてくださいね。
小平市立小平第三中学校(小平三中)
直近5年の全国大会出場は、2020年(大会中止)、2021年(金賞)、2022年(金賞)、2023年(金賞)、2024年(金賞)。4年連続で全国大会金賞という快挙を達成しています。
小平三中は澤矢康宏先生の指揮のもと、質の高いアンサンブルと表現力で知られています。2023年の自由曲「夜の来訪者~J.B.プリーストリーの戯曲に基づいて~」では物語性豊かな演奏を披露し、1年生18人もの初心者部員も含めた全員でハイレベルなサウンドを作り上げました。初心者の多さを感じさせない完成度で聴衆と審査員を魅了し、見事金賞を獲得しています。
部員同士の結束力が強く、「全員で音楽を楽しむ」姿勢を大切にしています。難易度の高い現代作品からクラシックアレンジまで果敢に挑戦。特に松下倫士氏や天野正道氏といった邦人作曲家の作品を巧みに表現できる技術力と音楽性が評価されています。
安定感あるサウンドと緻密なアンサンブルで、聴く人の心を掴む名演を繰り広げる東京屈指の名門校です。
羽村市立羽村第一中学校(羽村一中)


この動画を YouTube で視聴
直近5年の全国大会出場は、2021年(銀賞)、2022年(銀賞)、2024年(銅賞)。過去には2015年~2017年にかけて3年連続金賞を受賞した実績もあります。
羽村一中は少人数でも迫力ある重厚なサウンドが持ち味。2022年の自由曲「交響的断章」では、金管セクションの力強さが際立ち、部員28名とは思えない圧巻の演奏を披露しました。一人ひとりの役割が大きい分、ミスを全員でカバーするチームワークが音に表れ、聴衆を引き込む緻密な表現を実現しています。
伝統的に金管セクションのパワフルな響きと躍動感のある演奏で知られ、壮大でシンフォニックな作品を十八番としてきました。羽村市から全国に名を轟かせる強豪校です。
玉川学園中学部(玉川学園)


この動画を YouTube で視聴
直近5年の全国大会出場は、2023年(金賞)。久々に代表復帰しています。2023年の自由曲「キリストの受難」(フェルラン作曲)は、フルートやトランペットの技巧的なソロ、中低音の重厚な響きなどが特徴の難易度の高い楽曲ですが、果敢に挑み金賞を勝ち取りました。
この曲は同校が過去に全国大会で演奏した思い入れのあるレパートリー。当時の先輩たちに負けないドラマチックな演奏で会場を魅了しました。課題曲の荘重なポロネーズも含め、表情豊かなサウンドで高い評価を得ています。
玉川学園の吹奏楽部は、全人教育の一環として音楽を追求。「真・善・美・聖・健・富」の6価値を体現しています。プロの演奏家や卒業生によるパートレッスンなどを通して、基礎力を培っています。
「音を楽しむ」精神で培った豊かな表現力が強みで、近年は全国大会でもその実力を示しつつあります。部員同士の仲も良く、「チーム玉川」と称される団結力と表現力豊かな演奏が持ち味です。
足立区立第十四中学校(足立十四中)
直近5年では全国大会に出場していませんが、東京都大会では安定した成績をおさめており、2024年には金賞を受賞しました。長年にわたり高水準の演奏を維持しており、最近ではコンクールだけでなく地域のイベントやマーチングでも精力的に活動しています。
足立十四中吹奏楽部の強みは、生徒たちのチームワークと研究熱心さ。部員自らが選曲や表現方法を相談し合い、古典曲から現代曲まで様々なレパートリーに挑戦しています。
近年は森川凌顧問の指導のもとでマーチングにも力を入れ、シンプルながら切れのある演奏と動きで高評価を得ています。地域のコンサートや定期演奏会でも安定感抜群のパフォーマンスを披露しており、「東京都大会で名前を見ない年はない」と言われるほどの存在感を示す学校です。
足立区立西新井中学校


この動画を YouTube で視聴
全日本吹奏楽コンクールへの出場はまだありませんが、東京都大会常連校です。また、全日本マーチングコンテストでは2021年に全国大会初出場で金賞を受賞しました。
西新井中は「初心者の聖地」とも言えるユニークな存在。部員の約8割が中学入学時は楽器未経験にもかかわらず、毎年の東京都コンクールで上位入賞を果たしています。
ベテラン顧問の宇野浩之先生(吹奏楽指導歴40年)が率い、他校との合同コンサートや海外交流演奏会など「本物を聴く機会」を多く設ける指導方針が特徴的です。その成果もあり、初心者中心のバンドとは思えないハイレベルなサウンドを実現しています。
宇野先生はこれまで都内の複数校を全国大会に導いてきました(赴任校ごとに全国出場を達成してきた名指導者です)。西新井中は今後の躍進が期待される注目の存在と言えるでしょう。
中央区立日本橋中学校


この動画を YouTube で視聴
直近5年では全日本吹奏楽コンクール全国大会に出場していませんが、過去には出場経験があります。また、日本マーチングバンド協会(JMBA)主催の「マーチングバンド全国大会」マーチングでは全国大会常連の強豪として知られます。
2024年の全日本吹奏楽コンクール東京都大会では見事金賞を受賞し、代表こそ逃したものの堂々たる演奏を披露。特に木管セクションの繊細な表現と金管のバランスが良く、クラシックの名曲からポップスまで幅広いジャンルを安定して演奏できる柔軟性があります。地域のイベント「親子フェスタ」でも毎年オープニングを飾っており、澄んだ音色で観客を楽しませています。
マーチングにも早くから取り組み、関東大会・全国大会の常連として成果を上げてきました。都会の学校らしく行事も多い中、効率的な練習で質を高めている点も見逃せません。指導歴30年以上のベテラン高塚奈美香先生のもと、演奏と動きの両面で磨きをかけ、「魅せる吹奏楽」を追求し続ける実力校です。
板橋区立赤塚第三中学校(赤塚三中)


この動画を YouTube で視聴
全日本吹奏楽コンクールへの出場はないものの、全日本吹奏楽連盟(AJBA)主催の全日本マーチングコンテスト常連校で、2023年と2024年には連続で金賞を受賞しています。
「赤三」の愛称で親しまれる板橋区の強豪校。2024年の東京都大会では惜しくも代表を逃しましたが金賞を獲得し、勢いのある演奏で注目を集めました。同年の区民まつりでは、明るく躍動感あふれるサウンドでマーチを堂々と演奏し、沿道の観客を沸かせました。
赤塚三中吹奏楽部は、顧問の先生方の熱心な指導のもと、初心者から経験者まで一丸となって練習に励み、「自分たちのベストを尽くす」文化が根付いています。卒業生にもプロ奏者が多数おり、そうしたOB・OGとの繋がりも部の財産と言えるでしょう。今後、コンクール全国大会への初出場が期待される注目校です。
江戸川区立鹿本中学校(鹿本中)


この動画を YouTube で視聴
全日本吹奏楽コンクールへの出場は未経験ですが、東京都大会金賞の実績があります。近年ぐんぐん頭角を現している新進気鋭のバンドです。
2024年の東京都大会には地元・江戸川区代表として出場し、自由曲「アシュラ」(石川健人作曲)で迫力ある演奏を披露しました。管楽器と打楽器が対等に絡み合う難曲でしたが、小柄な中学生たちとは思えない力強さとキレで音楽を表現し、会場を驚かせ、聴く者に感動を与えました。惜しくも全国大会出場は逃したものの、技術・表現両面で高評価を受けています。
江戸川区は地域ぐるみで吹奏楽を応援する土地柄で、OB・OGが結成した「鹿本ウィンドアンサンブル」が演奏会に参加するなど、中学生をバックアップする体制が整っています。そうした恵まれた環境の中、部員たちは自主性を持って練習メニューや演奏づくりに取り組み、年々レベルアップを遂げています。
羽村市立羽村第二中学校(羽村二中)
全日本吹奏楽コンクールへの出場経験はないものの、東京都大会には毎年出場しており、羽村一中、羽村三中と並んで高水準の音楽活動をおこなってきました。
実は2011年頃まではオーケストラ編成の音楽活動を主体としており、その後吹奏楽部として再スタートした経緯があります。もともとオーケストラ路線だった背景から、クラシック音楽への理解が深く、吹奏楽に移行してからもシベリウスやホルストなど管弦楽作品の編曲に積極的に取り組んでいます。
少人数ながら、繊細な表現とアンサンブルのまとまりが光る学校です。派手さよりも一音一音に心を込めた丁寧な演奏が持ち味で、コンクールでも堅実な演奏で高評価を得ています。
羽村市立羽村第三中学校(羽村三中)


この動画を YouTube で視聴
全日本吹奏楽コンクールへの出場経験はありませんが、羽村市内では活発な音楽活動をおこなっていることで知られます。部員数は年によって少ない場合もありますが、アットホームな雰囲気で息の合った演奏が持ち味です。
羽村市内の小学校・中学校は全て金管バンドや吹奏楽の活動があり、先生方の熱心な指導と地域の支えで音楽文化が育まれてきました。羽村一中・二中との交流も盛んで、合同バンドでの演奏は全国大会級の迫力になることも。
音楽を心から楽しみ、聴く人にも楽しさを届ける——そんな温かさにあふれた羽村三中のサウンドに期待が高まります。
各校それぞれに個性豊かな強みがあり、東京の中学生バンドのレベルの高さと音楽にかける情熱を感じずにはいられません。ぜひ紹介したYouTubeリンクから、彼らの演奏を実際に聴いてみてくださいね。きっと吹奏楽の魅力と中学生たちのひたむきなパワーが伝わってくるはずです。今年の吹奏楽コンクールでも、これら強豪校の熱演をお見逃しなく!