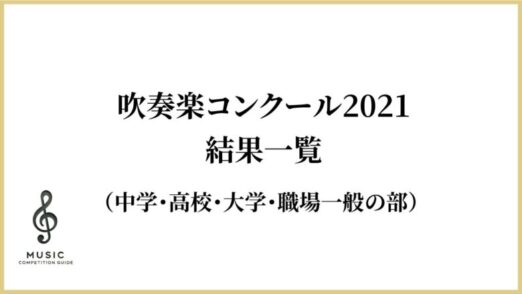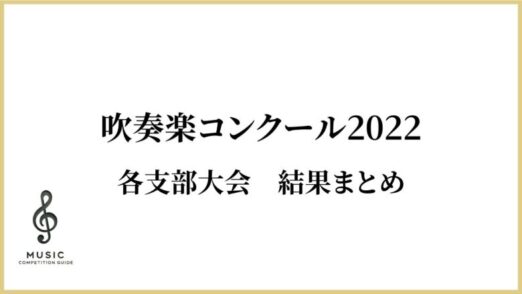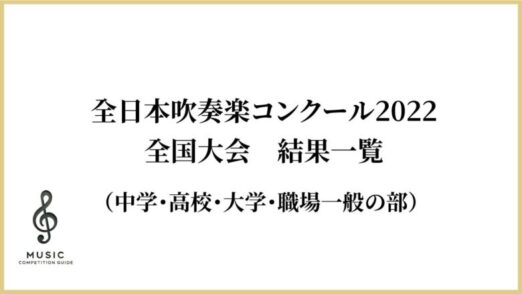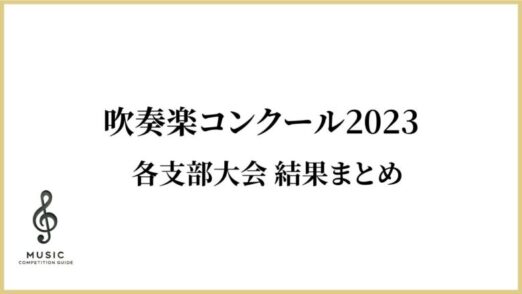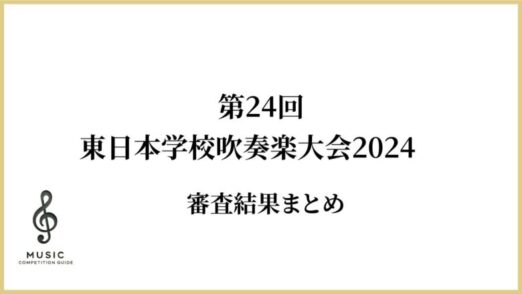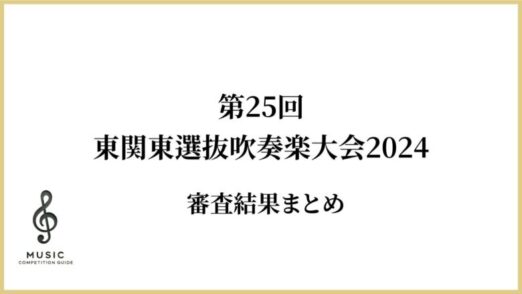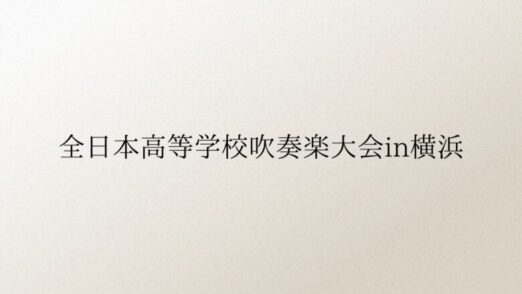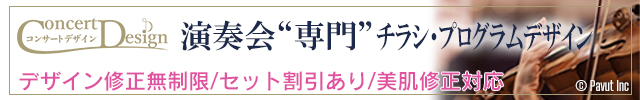さまざまな交流演奏会が若き奏者たちを大きく成長させている西関東支部。新潟県、群馬県、山梨県、埼玉県から構成される西関東支部には、全国大会の常連校がひしめいています。
今回は、高校生顔負けの完成度で注目を集める「中学校の部」から、特に輝きを放っている10校の名演と直近実績を詳しく紹介!
指導者・保護者・部員はもちろん、コンクール情報を探す学校関係者にも、今秋の全日本吹奏楽コンクール観戦がさらにおもしろくなるヒントをお届けします。
川口市立青木中学校(埼玉県)
直近5年では全国大会に出場していないものの、 2015~2018年にかけては4年連続で全国大会に出場しています。2018年の全日本吹奏楽コンクールでは自由曲「ウインドオーケストラのためのマインドスケープ」(高昌帥)を情感豊かに演奏し、初の金賞に輝きました。
2019年は惜しくも代表を逃しましたが、それまで培った地力は健在で、聴衆を魅了する演奏に定評があります。明るくパワフルなサウンドと正確なアンサンブルで急成長を遂げたバンドです。
「行動4原則」(挨拶・返事・素早い行動・相手の目を見て話を聞く)を掲げ、日常生活から規律を重んじる指導で急速にレベルアップした常連校。「聴く人を楽しませる演奏」をモットーに、コンクール以外の演奏活動も積極的におこなっており、ディズニーランドでの演奏経験もあります。
川口市立神根中学校(埼玉県)


この動画を YouTube で視聴
直近5年では全国大会に出場していませんが、2018年に西関東支部代表として、全国大会初出場しています。多彩な音色変化が要求される真島俊夫作曲「三つのジャポニスム」を情緒豊かに表現。木管セクションの機動力と金管の力強さのバランスが良く、初出場ながら安定感のある演奏で注目されました。
川口市立神根中学校のサウンドを磨き上げたのは、生徒の自主性を尊重しつつも細部まで妥協しない指導でした。初の全国舞台でも平常心で演奏できる精神力の強さも、この学校の持ち味です。
現在は、部員数はそれほど多くないものの、派手さよりも緻密なアンサンブルを重視する校風で知られています。基礎合奏の徹底と選曲の巧みさも特筆に値します。
朝霞市立朝霞第一中学校(埼玉県)
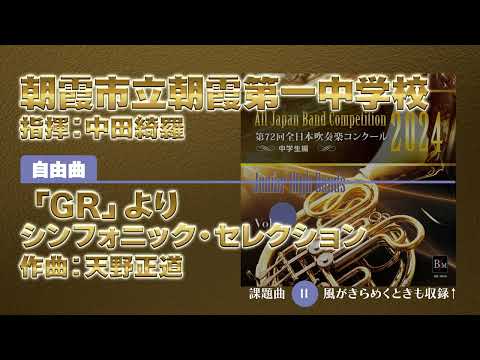
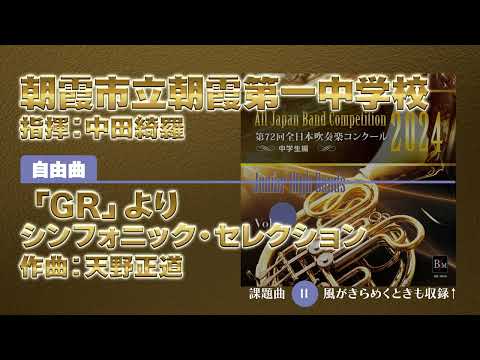
この動画を YouTube で視聴
直近5年の全国大会出場は、2021年(銀賞)、2022年(銀賞)、2023年(銀賞)、2024年(銀賞)。ここ数年、全国大会に連続で出場しており、抜群の安定感を誇ります。
ドラマティックで表情豊かな演奏が持ち味で、2018年にはプッチーニ作曲の歌劇「マノン・レスコー」で金賞を獲得しました。以降も全国大会では「カヴァレリア・ルスティカーナ」「タイス」などオペラ作品などで入賞を重ねています。高い技術に裏打ちされた安定感と表現力は、全国トップクラスと言えるでしょう。
「効率の良さ」を意識したムダのない練習で、短時間でも成果を出す部活動運営がなされています。顧問の先生は生徒一人ひとりの演奏技術の向上と、息を合わせる合奏力の両立にこだわった指導を展開。毎年掲げるスローガン「雑草魂」のもと、生徒自身が目標を話し合って決める主体性の高さも特徴です。
越谷市立大相模中学校(埼玉県)


この動画を YouTube で視聴
直近5年の全国大会出場は、 2021年(銀賞)、2022年(銀賞)、2023年(銀賞)。近年の自由曲は難易度の高い現代邦人作品からクラシックの大作まで多彩で、いずれも緻密なアンサンブルと迫力あるサウンドで聴かせます。2023年には八木澤教司作曲「不朽の大樹」を巧みに表現し銀賞を受賞。特に表現の幅広さには定評があります。
「音楽ができることへの感謝」をモットーに、楽しさと真剣さを両立させた部活動を展開。2018年に代表を逃す挫折も経験しましたが、翌2019年に見事復活するなど勝利への執念も光ります。
明るく抜けの良いサウンドと高い表現力を武器に、西関東を代表する常連強豪校として君臨しています。
草加市立青柳中学校(埼玉県)
直近5年では全国大会に出場していないものの、 2019年に西関東支部代表として念願の全国大会初出場を果たしました。
支部大会初出場が2017年と遅めながら、2019年には課題曲「エイプリル・リーフ」と自由曲「歌劇《トスカ》より第一幕」で全国銀賞を受賞。明るく透明感のあるサウンドと勢いのある演奏で急成長を遂げています。特に「トスカ」では中学生離れしたドラマチックな表現力が高く評価されました。
部の歴史は浅いものの、指導者の的確な指導と生徒たちの情熱で短期間にトップレベルへ成長。動画などで演奏を積極的に公開してはいませんが、基礎力の確かさと勢いで西関東の新勢力として注目されています。
さいたま市立土屋中学校(埼玉県)


この動画を YouTube で視聴
直近5年の全国大会出場は、 2022年、2023年、2024年。2022年に初出場で銀賞を受賞し、2023年・2024年と連続金賞受賞という快挙を成し遂げています。
近年台頭してきた新星。2024年の自由曲「歌劇『タイス』瞑想曲」では豊かな音楽表現と統一感が際立ち、見事金賞を獲得しました。丁寧なフレージングと柔らかなサウンドが持ち味で、全国でも稀有な存在感を示しています。審査員からは「中学生離れした完成度」と称賛されました。
大編成ではないものの、一人ひとりの実力を最大限に引き出す指導で急成長を遂げています。特に合奏力の向上に力を入れており、少人数でも厚みのある音づくりに定評があります。
飯能市立加治中学校(埼玉県)


この動画を YouTube で視聴
直近5年の全国大会出場は、 2021年(銅賞)。約20年ぶりとなる全国大会出場を果たしました。
2021年の全国大会では、樽屋雅徳作曲「月下に浮かぶひとすじの道標~3.11超克の祈り~」を演奏し銅賞を受賞。東日本大震災への祈りをテーマとした難曲に全身全霊で挑み、情感あふれる表現が聴く者の心を打ちました。木管セクションの美しいハーモニーと金管の芯のある音色が高く評価され、久々の全国復帰ながら存在感を示しました。
部員は少数精鋭で、基礎重視の練習と豊かな音楽性の育成を両立する指導が特徴です。コンクール自由曲では物語性のある作品を選ぶ傾向があり、音楽的メッセージ性に富む「聴衆の心に響く演奏」を追求。今後の活躍が期待されます。
さいたま市立内谷中学校(埼玉県)
直近5年では全国大会に出場していません。2018年西関東吹奏楽コンクールで金賞を受賞するものの、代表選考で惜しくも落選。しかしながら実力は高く評価されており、全国大会出場に最も近い学校の一つです。
2018年の西関東大会では、課題曲「ルイ・ブルジョアの讃美歌による変奏曲」を力強く演奏しました。厚みのある中低音セクションと柔軟なアンサンブルが持ち味で、県大会では常にトップクラスの評価を受けています。
長年にわたり県大会・西関東大会で上位に名を連ねる実力校です。部訓「凡事徹底」のもと、基礎基本の積み重ねを大切にした練習で確かな合奏力を築いてきました。生徒の自主性を重んじながらも細部まで妥協しない指導方針。その実力と安定感から「次代の全国常連候補」として期待される存在です。
長岡市立東北中学校(新潟県)
直近5年では全国大会に出場していませんが、2021年(銅賞)、2022年(金賞)、2023年(銅賞)と連続して西関東吹奏楽コンクールに出場しています。新潟県内では屈指の強豪校です。
2022年の西関東大会で披露した福島弘和作曲「ラッキードラゴン~第五福竜丸の記憶~」は、東北中ならではのクリアなサウンドが光る名演でした。代表選出は逃したものの、全国大会出場校に引けを取らない完成度で観客を魅了しました。
新潟県内で長年トップクラスを維持し続ける伝統校。現在もその伝統を受け継ぎつつ新しい表現に挑戦しています。全員で音を作り上げる合奏重視の指導で、一体感のある音楽づくりには定評があります。「明るく華やかなサウンド」が強みのバンドです。
高崎市立塚沢中学校(群馬県)


この動画を YouTube で視聴
直近5年、全国大会には出場していませんが、群馬県代表として西関東大会には度々進出しており、2021年と2022年には銀賞を受賞しています。
群馬県勢の中では常に有力校として名前が挙がり、特に重厚なハーモニーと安定したリズムが評価されています。2022年西関東大会ではアッペルモント作曲「ブリュッセル・レクイエム」を演奏し銀賞を獲得。会場を魅了しました。惜しくも全国大会には届いていませんが、「県内トップレベルの演奏技術」と専門誌で紹介されるほどの実力校です。
文武両道を掲げる校風のもと、少人数でも一人ひとりが存在感のある音を出せるよう、個人技術の向上にも力を入れています。マーチングコンテストでも全国大会に連続出場するなど(2023年銀賞受賞)、奏者の総合力が高い点が特徴。今後の全国大会出場が期待されます。
実績に裏付けられた高い演奏力と特色あるサウンドでエリアを牽引する、西関東支部の強豪校。地域の枠を超えて全国レベルでしのぎを削る彼らの演奏に、多くの吹奏楽ファンが熱い視線を注いでいます。今年の全日本吹奏楽コンクールでも、これら強豪校の活躍から目が離せません。