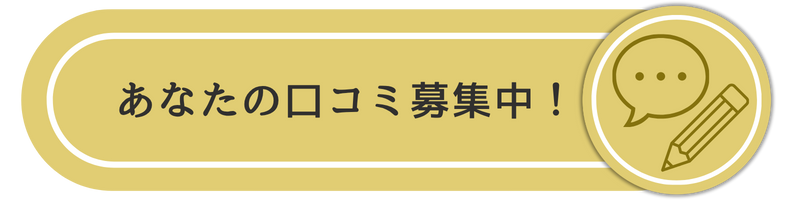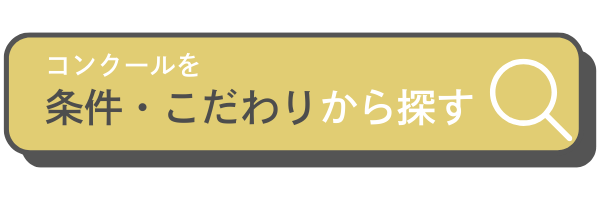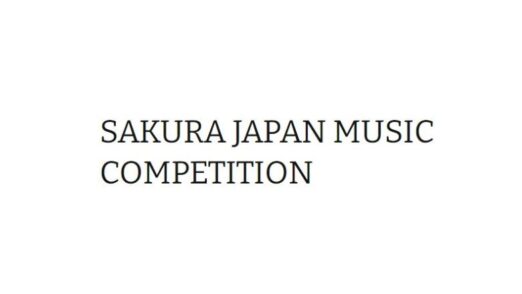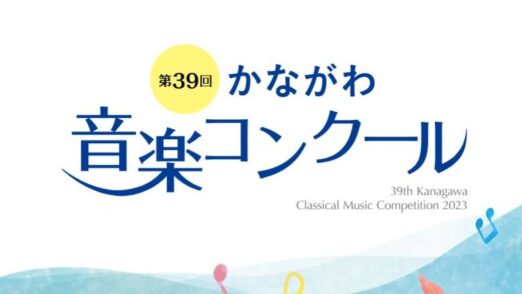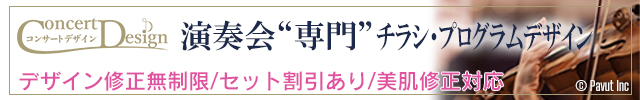若き音楽家の登竜門として知られる第9回仙台国際音楽コンクール(ヴァイオリン部門)が、2025年5月24日から6月8日にかけて開催される。世界中から才能ある若手ヴァイオリニストたちが仙台に集い、熱い演奏を繰り広げる。
開催概要:若き才能が集う国際舞台
コンクールは仙台市青年文化センター(日立システムズホール仙台)を会場とし、国籍問わず、1995年1月1日以降に生まれた演奏家が出場資格を持つ。
本大会への出場者は、2024年秋から2025年初頭にかけて実施された動画提出による予備審査を通過した精鋭たちだ。出場者の発表は2月12日に行われた。
審査委員長を務めるのは、1980年のエリザベート王妃国際音楽コンクールで優勝経験を持つ世界的なヴァイオリニスト、堀米ゆず子氏。第7回大会から導入されたセミファイナルでのコンサートマスター審査は、堀米の発案によるものである。
独自の審査と多彩な課題曲:試される総合力
コンクールは予選、セミファイナル(準決勝)、ファイナル(本選)の3ラウンドで構成され、協奏曲を中心としたプログラムが最大の特徴だ。予選からファイナルまでの全ての演奏は一般公開される。
課題曲は多彩かつ高度なものが揃う。予備審査ではパガニーニの《カプリース》やバッハの無伴奏ソナタなど、技術と音楽性の両面が問われる難曲が出された。予選ではモーツァルトの作品とイザイの無伴奏ソナタという対照的な組み合わせが課される。
セミファイナルでは、協奏曲に加えてモーツァルトの「カッサシオン」やブラームス交響曲の指定箇所をコンサートマスター(またはコンサートミストレス)として演奏するという、独自の課題が設けられている。
この審査は、ソリストとしての力量だけでなくオーケストラ団員としての資質も評価する、世界でも珍しい試みであり、仙台コンクールならではの総合的な審査方式となっている。
ファイナルではモーツァルトの協奏曲に加え、ロマン派以降の大作協奏曲を演奏することが求められ、出場者の幅広い音楽性と表現力が試される。
伴奏は、予選では仙台フィルハーモニー管弦楽団および山形交響楽団のメンバーによるオーケストラ(指揮者なし)、セミファイナルおよびファイナルでは広上淳一指揮のもと、仙台フィルハーモニー管弦楽団が務める。
充実の賞とキャリア支援
1位入賞者には賞金300万円と金メダル、ディプロマが授与される。さらに、仙台フィルハーモニー管弦楽団または国内主要オーケストラとの共演機会、リサイタル出演、CD制作といった副賞も用意されている。
2位から6位までの入賞者にも賞金(200万円~60万円)とメダルなどが贈られる。海外在住の出場者には渡航補助や滞在費のサポートもあり、若手音楽家にとっては演奏経験だけでなく、キャリア支援の面でも魅力的なコンクールとなっている。
熱戦をオンラインで!無料ライブ・オンデマンド配信
会場に足を運べない音楽ファンも、コンクールの全日程をインターネットで楽しめる。公式発表によると、期間中、ヴァイオリン・ピアノ両部門の予選からファイナル、ガラコンサートに至るまでの全ての演奏が、公式YouTubeチャンネルでライブ配信される予定だ。
さらに、各日の演奏映像は翌日から2026年6月30日まで期間限定でオンデマンド配信され、後から視聴することも可能になる。配信は無料で提供される見込みで、世界中の若き才能たちの熱演を自宅で堪能できる。
最新情報は公式サイト・SNSでチェック
仙台国際音楽コンクールでは、公式ウェブサイトのほか、SNSを通じても情報発信を行っている。公式X(旧Twitter)アカウント「@sendai_simc」では、出場者発表やプログラム情報、関連イベントの案内、ライブ配信の告知など、最新ニュースが随時更新される。
このほか、公式FacebookページやYouTubeチャンネル、ニュースレターなども開設されており、観客やファンは様々なオンラインプラットフォームを通じてコンクールの進捗を追うことができる。
注目の日本人出場者たち:世界へ羽ばたく4人の若きヴァイオリニスト
第9回大会のヴァイオリン部門には、日本から的場桃、松木翔太郎、落合真子、吉本梨乃の4名が出場する。いずれも国内外で優秀な実績を持つ、注目の若手ヴァイオリニストだ。
的場桃:国内外のコンクールを席巻する期待の新星
的場桃は2007年東京都生まれの17歳(高校2年生)。5歳でヴァイオリンを始め、桐朋学園大学音楽学部附属「子供のための音楽教室」で佐々木歩に師事した。
2019年の「第73回全日本学生音楽コンクール」東京大会小学校の部で第1位、2022年の「第76回全日本学生音楽コンクール」全国大会中学校の部でも第1位を獲得。さらに2022年チェコ音楽コンクール(ヴァイオリン部門ジュニアの部)でも第1位に入賞するなど、国内の主要ジュニアコンクールを次々と制した将来有望な新星だ。
その確かな技術と「人の心に響く音」と評される音楽性は注目を集めており、現在は精力的に演奏活動を行いながら研鑽を積んでいる。
松木翔太郎:国際舞台で輝く実力派、N響とも共演
松木翔太郎は2006年生まれの18歳(高校2年生)。3歳からヴァイオリンを始めた。小学生の頃より頭角を現し、「日本クラシック音楽コンクール」小学生の部でグランプリを受賞。「第75回全日本学生音楽コンクール」中学生の部では東京大会第1位、全国大会第2位に入賞した。
国内だけでなく国際舞台での活躍も目覚ましく、2022年レオニード・コーガン国際ヴァイオリンコンクール(ウクライナ開催)第3カテゴリーで第1位に輝くなど、数々の国際コンクールでトップクラスの成績を収めている。
NHK交響楽団メンバーとの共演や宮崎国際音楽祭での演奏経験も持ち、世界的ヴァイオリニストの徳永二男、三浦道子、三浦文彰らに師事してきた。現在、桐朋女子高等学校音楽科(男女共学)に特待生として在学中で、その実力と将来性から国内の若手の中でも特に注目されている。
落合真子:首席入学の実力と室内楽での活躍も光る
落合真子は2001年滋賀県生まれの23歳。幼少期をロサンゼルスで過ごし、6歳からヴァイオリンを始めた。滋賀県立石山高校音楽科を経て、東京藝術大学音楽学部に宗次德二特待奨学生として首席で入学し、在学中に福島賞を受賞している。
国内最高峰のコンクールである日本音楽コンクールでは、第90回(2021年)ヴァイオリン部門で第2位を受賞。そのほか、第18回KOBE国際音楽コンクール最優秀賞、第7回刈谷国際音楽コンクールグランプリ、松方ホール音楽賞など、数多くのタイトルを獲得している。
また、2023年には室内楽グループ「クァルテット風雅」を結成し第1ヴァイオリンを担当、サントリー芸術財団の室内楽フェローに選出されるなど、室内楽でも活躍の幅を広げている。卓越した技術と豊かな表現力を併せ持ち、国内外で研鑽を積む実力派だ。
吉本梨乃:ウィーンで研鑽、クライスラー国際2位の最有力候補
吉本梨乃は2003年兵庫県生まれの21歳。幼少より国内コンクールで入賞を重ね、14歳で単身ウィーンに留学。ウィーン国立音楽大学の英才課程で名教授ミヒャエル・フリッシェンシュラーガーに師事した。
17歳からはベルギーのエリザベート王妃音楽院にて巨匠オーギュスタン・デュメイにも師事し、欧州を拠点に研鑽を続けている。
16歳で出場した第16回パドヴァ国際音楽コンクール(イタリア)では最年少優勝者となり、弦楽器・ヴィルトゥオーゾ・オーケストラ付き部門で立て続けに優勝、全部門グランプリも受賞するという快挙を成し遂げた。
また、2022年には権威ある第10回フリッツ・クライスラー国際ヴァイオリンコンクール(ウィーン)で第2位を受賞。2018年上海アイザック・スターン国際ヴァイオリンコンクールでのファイナリスト選出(スカラーシップ受賞)など、輝かしい国際実績を持つ。
近年はウィーン室内管弦楽団やウィーン放送交響楽団、ブルガリア国立放送響など国内外のオーケストラと共演を重ね、高い評価を獲得している。さらに2022年にはウィーン・フィルハーモニー管弦楽団のエキストラ奏者オーディションに合格し、ウィーン国立歌劇場や楽友協会で同楽団の公演に参加するなど、一流の現場で経験を積んでいる。
世界的視野で活躍する新進気鋭のヴァイオリニストとして、本コンクールでも最有力候補の一人に挙げられる。
世界の精鋭が集結:ハイレベルな戦いに注目
今回のコンクールには、全体で43の国と地域から638名の応募があった。その中から映像審査で選抜されたヴァイオリン部門の出場者は、17の国と地域から集まった38名の若き演奏家たちだ。出場者の中心年齢層は10代後半から20代となっている(出場資格の上限は30歳)。
ヴァイオリン部門には欧米やアジア各国からも実力派が多数参加。ロン=ティボー国際コンクールやジョルジェ・エネスク国際コンクールで入賞経験を持つヴィクラム・フランチェスコ・セドーナ(イタリア)をはじめ、パガニーニ国際コンクールやイザイ国際コンクールなど著名コンクールの入賞者が顔を揃える。
過去大会からの再挑戦組にも注目が集まる。2019年の第7回大会で第6位に入賞した韓国のコー・ドンフィが再びエントリーしており、その成長と雪辱を期す演奏に関心が寄せられている。
日本勢では、前述の吉本梨乃(2022年クライスラー国際2位)や落合真子(2021年日本音楽コンクール2位)といった、世界的コンクールで実績を残す実力者が出場しており、母国開催の舞台でのさらなる飛躍が期待される。
今大会は各国から将来を嘱望される若手が集うハイレベルな顔ぶれとなり、熱戦は必至だ。
仙台から世界へ:コンクールの意義と歴代受賞者の軌跡
仙台国際音楽コンクール(SIMC)は、仙台市が創設した歴史ある国際コンクールで、3年ごとに開催されている。
日本を代表するコンクールの一つとして国内外で非常に高く評価されており、ヴァイオリン国際コンクールのレベル分類では、世界三大コンクール(チャイコフスキー国際コンクール、エリザベート王妃国際音楽コンクール、ショパン国際ピアノコンクール)に次ぐ、国際的に評価の高いコンクールに位置付けられる。
独自の審査が育む総合力
課題曲に協奏曲を中心に据え、全ラウンドでオーケストラとの共演機会を設けている点が、このコンクールの大きな魅力だ。ソリストとしての才能だけでなく、共演者としての総合力を養い、披露できる場となっている。
特にヴァイオリン部門セミファイナルにおける「コンサートマスター審査」は世界でも類を見ないユニークな取り組みで、将来オーケストラで重要な役割を担う資質をも評価する画期的な試験である。
こうした特色により、SIMCは若手演奏家にとって登竜門であると同時に、音楽文化の国際交流を促進する貴重な機会となっている。
歴代受賞者の輝かしい活躍
本コンクールからは、これまでに数多くの才能ある演奏者が羽ばたいている。過去の入賞者には、ヴァイオリンの青木尚佳(第6回・第3位)やピアノのユジャ・ワン(第1回・第3位)、津田裕也(第3回・第1位)といった、国際的に活躍する演奏家が名を連ねる。
例えばユジャ・ワンは、第1回大会ピアノ部門3位入賞後、世界的なピアニストとして大成し、現在では著名オーケストラとの共演やリサイタルで活躍している。
また、青木尚佳は第6回ヴァイオリン部門3位入賞後にドイツを拠点に国際的ソリストとして活動し、津田裕也も第3回ピアノ部門優勝を機に国内外で精力的に演奏キャリアを重ねている。
それ以外にも歴代入賞者からは多くのプロ演奏家が巣立っており、近年では仙台で入賞後に他のメジャー国際コンクールで優勝する例も見られる。こうした実績は、本コンクールが世界の音楽界に新星を送り出す重要なステップとなっていることを物語っている。
仙台の地から羽ばたいた先輩たちの活躍に続くように、第9回大会でも新たなスターの誕生が期待される。