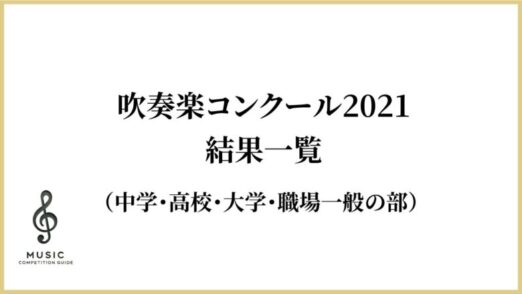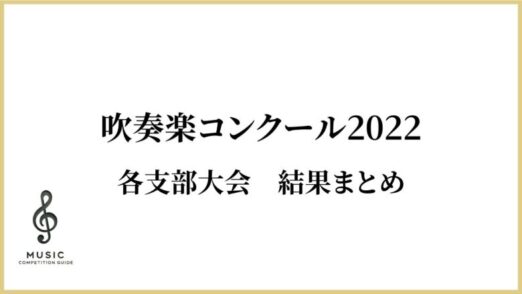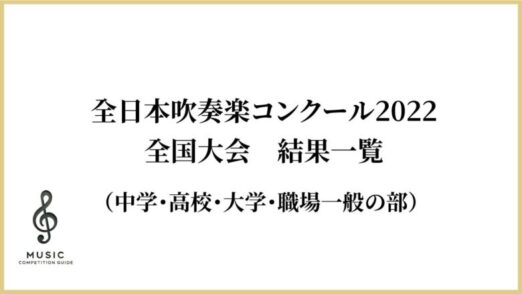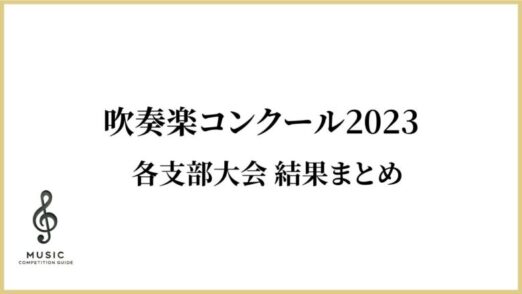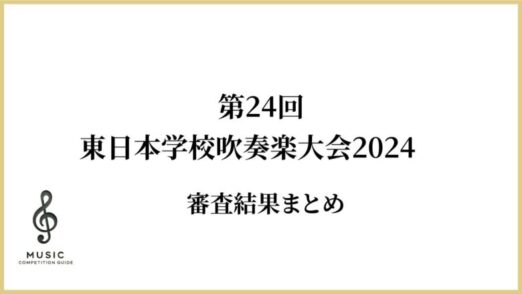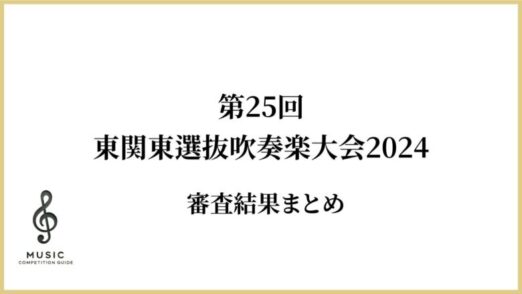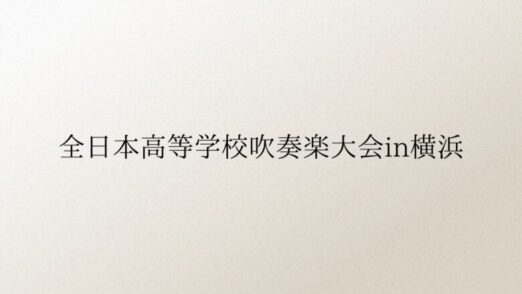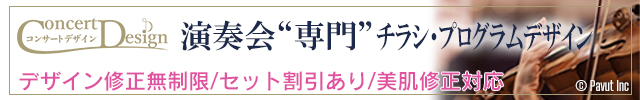2025年10月25日、新潟で開催される全日本吹奏楽コンクール・大学の部。東京支部から代表に選ばれた2大学は、常連の東海大学吹奏楽研究会と、創部初の快挙となる明星大学学友会吹奏楽団だ。そこで、先月開催された東京都大会・大学の部で8団体が繰り広げた熱演を振り返り、明星大学の喜びと全国への意気込みを交えてお伝えする。
取材・文:オザワ部長
世界でただひとりの吹奏楽作家。神奈川県立横須賀高等学校を経て、早稲田大学第一文学部文芸専修卒。在学中は芥川賞作家・三田誠広に師事。 主著に『吹部ノート 12分間の青春』(日本ビジネスプレス)、『空とラッパと小倉トースト』(Gakken)など。小学校合唱部を描いた『とびたて!みんなのドラゴン 難病ALSの先生と日明小合唱部の冒険』(岩崎書店)は2025年度の課題図書に選定。詳しくはこちら>>
大学の激戦区・東京支部
大学生が繰り広げる演奏の魅力は、成熟と成長と知の音楽が聴けるところだろう。高校生が「青春の音楽」なのだとしたら、そこから技術的に向上し、人間的な成長を遂げ、さまざまな経験と大学での学術によって、社会に出る直前の大学生にしかできない演奏というものが現れる。
また、高校よりもさらに学生の自主性に重きを置いて活動しているため、各団体ごとの個性の違いもくっきりしているのが特徴だ。
今回の東京都大会・大学の部も、まさに色とりどりの個性が咲き乱れる大会となった。
東京は全国的に見ても大学がもっとも集中するエリア。まず、その中で予選を突破して東京都大会(都大会本選)に出場することが難しい。今年は本選にいくつか常連団体の姿がなく、寂しさを感じる一方、早稲田大学應援部吹奏楽団のように約30年ぶりに都大会に復活した団体もあった。
そんなハイレベルな都大会・大学の部で、今年は大きなニュースがあった。
悲願の初出場!明星大学の起こした快挙
ここ数年、都大会の代表には東海大学吹奏楽研究会と創価大学パイオニア吹奏楽団が選ばれてきた。
そんな中、今年初めて代表の座を射止めたのが明星大学学友会吹奏楽団だ。東京の羽村市立羽村第一中学校吹奏楽部を全日本吹奏楽コンクールに10回導いた音楽監督・玉寄勝治先生のもと、独自のソルフェージュを中心に基礎力を磨きあげ、創団58年目にして悲願の全国大会初出場を決めた。
課題曲《マーチ「メモリーズ・リフレイン」》は冒頭から金管楽器の華々しい音が響きわたり、中間部のトリオも丁寧で美しかった。自由曲《吹奏楽のための交響曲「ワイン・ダーク・シー」》(ジョン・マッキー)は勇壮なホルンのユニゾンから第1楽章が始まり、ゆったりと歌い込む第2楽章、たたみかけるような第3楽章と、最初から最後まで観客の心をつかんで放さなかった。演奏後の拍手が、演奏の成功を如実に物語っていた。
明星大学学友会吹奏楽団の団長を務める岩本萌枝さん(3年・クラリネット)はこう振り返る。
「全国大会出場は、尊敬する歴代の先輩方でも成し遂げられなかったことで、そう簡単ではないとわかっていました。それでも、諦めてしまったら終わり。私は絶対に夢は叶うと信じていようと心に誓っていました。特に、団長になってからは『私は全国を目指してるから』と言葉に出すようにしていたので、それが伝わったのか、みんなも“都大会の先”を考えて活動してくれました」
都大会直前にはかなり緊張感が高まっていたが、それは気合いが入っていることの裏返しでもあった。
「自由曲の《吹奏楽のための交響曲「ワイン・ダーク・シー」》を玉寄先生が選んだとき、『これは勝ちにいく曲だな』と思いました。私は第2楽章のソロを吹いたんですが、本番は緊張で音になっているかわからないくらいでした。でも、積み重ねてきた練習と、みんなが『大丈夫だよ』と言ってくれたことを思い出し、心をこめて吹きました。自由曲の最後のほうは泣きそうになりながら、『終わりたくないな』と思っていました」
演奏後の万雷の拍手や歓声は岩本さんの耳にも届いており、反響の大きさに驚いたという。そして、表彰式はついに明星大学の夢が叶った瞬間になった。
「私はステージ上にいたんですが、代表団体として名前を呼ばれたとき、テンパってしまって、本当に呼ばれたのかわからなくなってしまいました。『本当? 訂正されるんじゃない?』と(笑)。間違いではないとわかってからは、心から幸せに思いました。団長としても、ひとりの団員としても、日ごろはあまり誰かから肯定されることはありませんが、自分のやってきたことは間違いではなかったんだと濃い呈された気がしました」
明星大学の大きな特徴として、練習が週4日しかないということだ。例年都大会に進出する強豪でありながら、学生生活とバランス良く両立しながら活動してきた。
「毎日練習しないと忘れてしまうこともあるので、中学や高校で毎日部活をやっていたときと比べると不安な面もありました。でも、将来に向けて勉強したり、ボランティアに参加したり、資格に挑戦したり、アルバイトをしたり、それぞれが両立しながら活動を続けてきました。そのスタンスを崩さずに結果を出せたのはよかったと思います」
自分たちの力だけではない、歴代の先輩たちの努力が受け継がれてきたからこその今年の悲願達成だったと岩本さんは強調する。
「先輩方からたくさん『夢を叶えてくれてありがとう』というメッセージをいただきましたが、私たちこそ先輩方に感謝を伝えたいです」
いよいよ全国大会。出場順はなんと1番だ。
「これまでは全国大会に出ることが目標でしたが、出られるからには金賞をとりたい。都大会で評価してくださった方たちにも、代表になれなかった大学にも、金賞をとることでその気持ちに応えたいと思っています。そして、大切にしてきた課題曲と自由曲を最後まで楽しみ、悔いのない演奏をしてきます」
悲願の裏側にあった音楽監督の思い
一方、明星大学学友会吹奏楽団で18年間音楽監督を務めてきた玉寄勝治先生はこう語る。
「都大会ではいい風が吹いてくれました。これまでなかなか都大会を抜けられませんでしたし、週4日の練習というのは音楽づくりの上では大変なこともありました。一方で、活動以外の時間に学生たちが重ねてきた経験は音楽に生きていたと思います。そういった私たちの道のりが、オデュッセウス王の苦難の旅路に重なり、いま、ようやく長いトンネルを抜けたなというという気持ちです。今年だけではなく、18年間、学生たちとともにコツコツやってきたことで達成されたことだと思っています」
実は、玉寄先生は都大会の演奏に完全に納得しているわけではなかったという。
「課題曲は、のっけから音程がもうひとつだなと思っていました。でも、学生たちは『ばっちりできています』というような表情をして演奏していて。代表に選ばれて嬉しい反面、驚きもあって、即売CDを買ってすぐ確かめたんですが、やっぱり音程はあまりよくない(笑)。でも、それを超える何かを感じました。これが音楽の良さであり、音楽の力なんだと思います」
玉寄先生はこれまで羽村一中や明星大学で、ハンドサインを使いながら音程感覚を養うソルフェージュを用い、基礎力を高めてきた。その長年の積み重ねの末に、基礎を超えた音楽性がこぼれだしたのが今年の演奏だった。その象徴が《ワイン・ダーク・シー》のゆったりした第2楽章のクライマックスのリタルダンドだった。
「学生たちには『リタルダンドは私がためたいだけためますから』と予告していました。練習どおりにはまったくやっていませんが、見事にはまりました。息が合うっていうのはまさにこのことだと感じました」
玉寄先生にとって、大学の部では初めての全国の舞台。意気込みを聞いてみた。
「やはり全国大会は特別な場所。そこに初めて出るという機会も、また特別。だからこそ、何が何でもいい演奏がしたい。美しさを競うのがコンクールなのだから、学生たちと美しさを追求し、それを披露したいと思います。うちの楽団は、ずば抜けた能力を持つ人たちの集まりではありませんが、みんなで音楽の素晴らしさや美を探求しています。そもそも大学とは探究する場所。全国大会は私たちの探究したものを発表する場でもあると思っています」
中学や高校、職場・一般とも違う大学吹奏楽のアイデンティティは「探究」という点にもあるのかもしれない。全国大会のステージで「新星」である明星大学がどんな美しい音楽を発表し、どんなきらめきを見せるのか、実に楽しみだ。
府中の森に響いた「自分たちの音楽」
もう1つの代表団体である東海大学吹奏楽研究会は、都大会ではトリの8番に出場した。
課題曲《祝い唄と踊り唄による幻想曲》では豊かな倍音とブレンドされたサウンドを響かせ、自由曲《「スペイン奇想曲」より》(リムスキー=コルサコフ)でも圧倒的な厚みと深み、ときには華々しさも備えた音で躍動した。特にクラリネットソロ、ユーフォニアムは見事。2年連続で全国大会金賞を継続している実績に裏打ちされた地力を感じさせる演奏で、まさに圧巻だった。
代表団体以外も素晴らしい演奏が多かった。
3年連続で都大会出場が続いている學習院大学應援團吹奏楽部は、田村文生作曲《トルキッチュ行進曲》を特殊奏法を交えながら知的かつユニークに表現。
創価大学パイオニア吹奏楽団は作曲家・伊藤康英先生の指揮のもと、《ステップ、スキップ、ノンストップ(順次進行によるカプリッチョ)》を立体的に奏で、伊藤先生自作の自由曲《怒りの日、祈りの日(ディエス・イレ、ディエス・ヴァンダナ)》は繊細さと重厚さ、緊迫感を織り交ぜながら好演。トータルで非常にクオリティの高い演奏となっていた。
3年目の出場となった青山学院大学学友会吹奏楽バトントワリング部は福島弘和作曲《ボレアス〜北風の神の神話〜》を演奏。明るい音色の美しさが印象的で、一体感があった。
東京佼成ウインドオーケストラのホルン奏者・上原宏先生が指揮する玉川大学は福島弘和《シンフォニエッタ第3番「響きの森」》を彩り豊かに披露した。特に打楽器の思いのこもった演奏が記憶に残った。
プロ吹奏楽団・ハーツウインズの指揮者でもある「大澤親分」こと大澤健一先生がタクトを執るアジア大学吹奏楽団。自由曲のロバート・ジェイガー作曲《「吹奏楽のための交響曲第1番」より》はダイナミックで表現力の高い演奏。楽章ごとの空気感の変化も見事だった。
30年ぶりに都大会出場の早稲田大学應援部吹奏楽団の自由曲は、青山学院と同じ《ボレアス〜北風の神の神話〜》。久しぶりの出場とは思えない集中力と一体感のある演奏で、音楽を奏でる喜びが伝わってきた。
コンクールゆえに結果はつくものの、各団体が「自分たちの音楽」を全うできた大会だったのではないだろうか。こうした大学ごとの個性が、また大学吹奏楽のレベルを押し上げることになるだろう。
代表となった明星大学と東海大学は、いよいよ全国の舞台に挑む。さらに研ぎ澄まされた2団体の演奏に、そして、各地から集まった全15大学の演奏に心から期待したい。