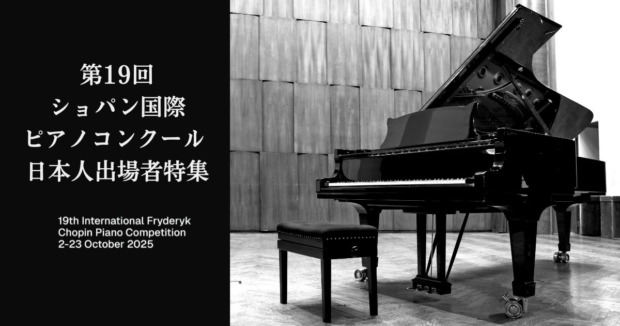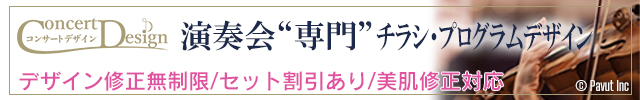5年に一度、世界中のピアニストと聴衆の視線がワルシャワへ集まる――それがショパン国際ピアノコンクールである。2025年秋、第19回大会は10月2日から23日にかけて開催される。
本稿では、公式サイトなどの情報をもとに、コンクールの仕組みや見どころ、日本勢の動向、そして「コンクール」という舞台芸術が持つ意味について、少し広い視点から見ていきたい。
コンクール概要とスケジュール
出場資格と予備予選
参加資格は1995年から2009年に生まれたピアニスト。映像審査や書類選考を経て、予備予選には171名が集った。
予備予選は2025年4月23日から5月4日まで、ワルシャワで実施され、各出場者は約30分のリサイタルを披露し、通過者が本大会(本戦)に進む。
通過者はおよそ85名。その中には「主要国際コンクールで一定の成果を収めた者」に与えられる予備予選免除枠も含まれており、日本からは13名が進出を決めた。
本大会(2025年10月2日〜23日)
本大会は10月2日の開会記念コンサートから幕を開ける。予選は3段階で進行する。
第1次予選:10月3日〜7日
第2次予選:10月9日〜12日
第3次予選:10月14日〜16日
続く本選(ファイナル)は10月18日〜20日、入賞者披露演奏会は10月21日〜23日に予定されている。
本選:10月18日〜20日
入賞者披露演奏会:10月21日〜23日
演奏はモーニング・セッション(10:00開始)とイブニング・セッション(17:00開始)に分かれ、日本時間ではそれぞれ17:00と24:00の開演となる。
特記事項―課題曲の変化―
今回の大会では課題曲に変化が見られる。本選では「幻想ポロネーズ」が全ファイナリストに課される見込みであり、協奏曲は第1番か第2番からの選択制が継続される。
課題曲の設定は、単なる選曲以上の意味を持つ。演奏の戦略や解釈の深みが試されるため、聴衆にとっても大きな注目ポイントとなる。
見どころ・注目点
「運命の30分」──予備予選という選抜の儀式
予備予選は、ひとり約30分のリサイタルで自分を示さねばならない。短い時間の中で、曲目の構成力、集中力、持久力、表現の余裕がすべて試される。その印象が審査員の記憶に残り、後のステージにまで影響を及ぼすこともある。まさに「運命の30分」と呼ぶにふさわしい時間である。
演奏順やその日の体調、ピアノとの相性といった要素も見逃せない。ここでは技術や表現だけでなく、精神力や舞台に臨む戦略眼までが審査の対象となる。
3段階予選を経て、ファイナルへ
本大会に入ると審査は一層厳格になり、以下の点が問われる。
・第1次予選では技術と構成力
・第2次予選では音楽性と個性
・第3次予選では精神性と作品解釈の完成度
そしてごく少数がファイナルへ。そこでは協奏曲と共通課題「幻想ポロネーズ」による真っ向勝負となる。
協奏曲の選択次第で舞台構成も変わり、オーケストラとの呼吸、演奏時間の密度なども勝敗の分かれ目となるだろう。
審査員陣と評価基準
審査員は多国籍にわたり、総勢17名が予定されている。審査員長にはギャリック・オールソンが名を連ねるとの情報もある。
過去大会同様、「通過可否」と点数評価を併用する方式が採られる見通しで、評価の偏りを補正する仕組みもある。演奏を聴く際、この仕組みを意識しておくと、誰が安全圏にいるのか、誰がギリギリのラインなのかを推し量ることができる。
ピアノ機種と響きの選択
ショパンコンクールでは、演奏者が選ぶピアノの機種も大きな要素となる。第19回ではC.ベヒシュタイン社のD-282が提供される予定である。
繊細なタッチや音の伸び、ペダルの反応――これらがショパン作品の表現に直結するため、ピアノ選びは演奏そのものに匹敵する重要な要素だ。ベヒシュタインの響きをどう使いこなすかは、聴きどころのひとつになる。
日本勢の動きと期待
今回、日本からは13名が本大会に挑む。内訳は、予備予選を勝ち抜いた10名と、国際コンクール実績による免除枠での出場者3名である。
免除枠には牛田智大、桑原志織、小林海都が名を連ね、いずれもすでに国際的評価を得ている実力者たちだ。とはいえ、免除であっても本大会の厳しいステージを突破するには強い精神力が必要となる。
過去には反田恭平(第2位)、小林愛実(第4位)といった入賞者が大きな話題をさらった。今大会で新しい世代がどのような躍進を見せるか、期待が高まる。
日本勢のトップバッターは牛田智大で、10月3日午後6時(日本時間)に登場。続いて山縣美季、山﨑亮汰が深夜の部に出演する。一次予選は10月7日まで5日間にわたって開催され、10月9日からは二次予選、最終的には10月18日から20日の本選で優勝者が決定する。
13名の日本人出場者情報については、ぜひ下記記事を読んでいただきたい。
ポーランド国立ショパン研究所の公式YouTubeチャンネル「Chopin Institute」で無料ライブ配信される。
未来への問いかけ
コンクールと “聴衆の変容”
かつては審査員の評価がすべてだったが、今は違う。YouTube配信やSNSの拡散により、世界中の聴衆が同時に演奏を見守り、評価する時代になった。演奏者は「審査員に向けた表現」と「世界の聴衆に届ける演奏」を同時に考えねばならない。
観客の反応や拡散は、コンクール後のキャリア形成に直結する。もはやコンクールは単なる競技ではなく、発信の場でもある。
解釈の潮流と “オリジナリティ” の模索
ショパン作品は時代ごとに解釈の流行がある。現代では、過剰な装飾や恣意的なルバートは避けられ、原典への理解や作品への誠実なアプローチが重視される。
今回の共通課題「幻想ポロネーズ」は、演奏者の思想や音楽観が強くにじみ出る作品だ。ファイナルでどのように差別化が図られるか、大きな聴きどころになる。
コンクールを超えて〜その後のキャリアとの接点〜
入賞はゴールではなく、むしろ出発点である。コンクール後にはリサイタルや録音活動が待っており、成長の軌跡が長期的に評価されていく。
優勝者リサイタルの日本公演も発表されている。コンクールの舞台で輝いた瞬間が、その後どのように花開くかを追うのも楽しみの一つだ。
最後に〜読む者への招待状〜
第19回ショパン国際ピアノコンクールは、単なる競技の場ではない。歴史と伝統を踏まえつつ、若い演奏家たちが“今”をどう表現するかが問われる舞台である。
読者には、配信やアーカイブを通じて「誰の音が心を揺さぶったか」「どの瞬間に差が出たか」を探しながら楽しんでいただきたい。演奏の背景や選曲、ピアノとの相性まで含めて味わうことで、コンクールはより豊かな体験になる。
10月、ワルシャワの国立フィルハーモニーで再び幕が上がる。ショパンの魂と若き演奏家たちとの対話を、ぜひ自分の耳と心で確かめてほしい。

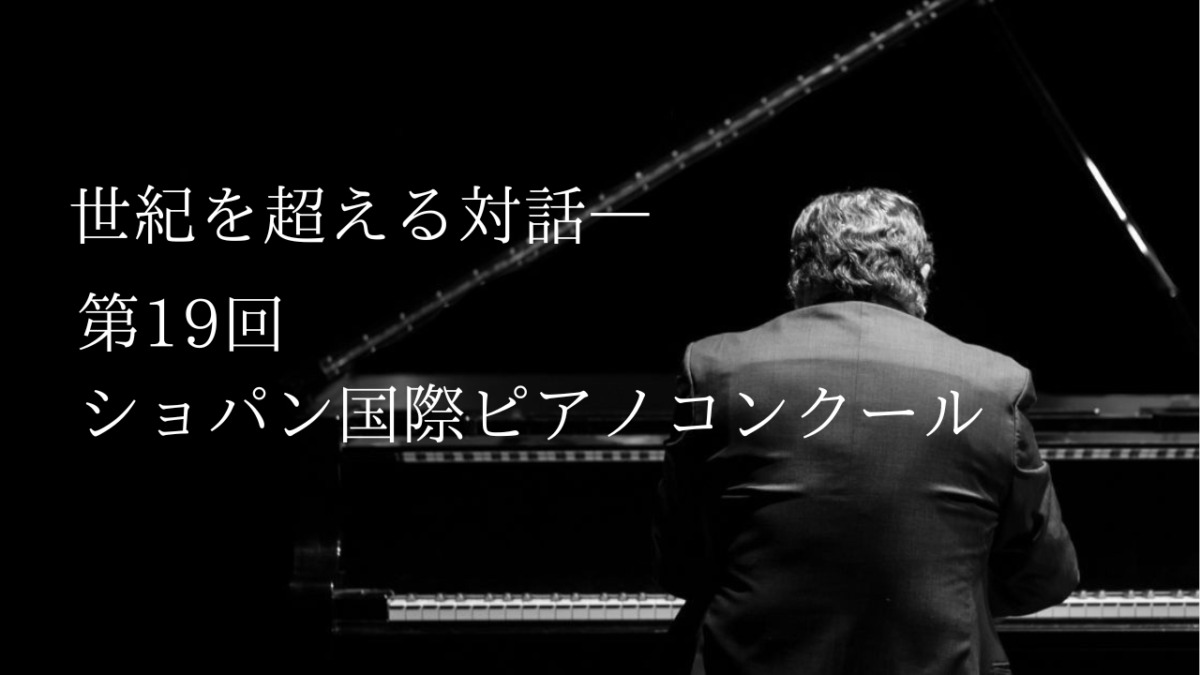


![© International Chopin Piano Competition / Photo by [Wojciech Grzedzinski]:ニュース](https://musiccontestsite.com/wp-content/uploads/2025/09/音楽コンクールガイドアイキャッチNEW-21-620x326.jpg)