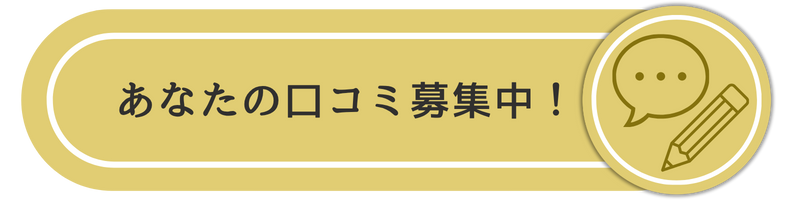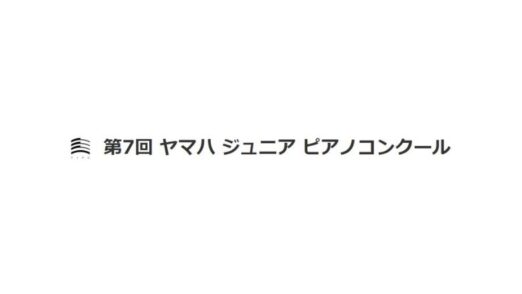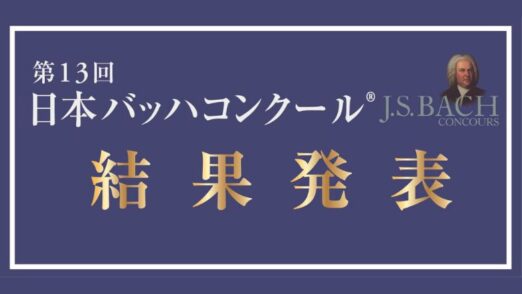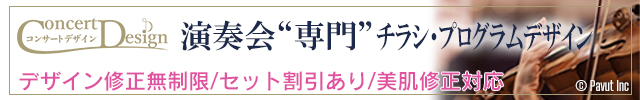- 2025年10月12日締切
大阪国際室内楽コンクールを主催している日本室内楽振興財団は、「音楽の原点」といわれる室内楽の素晴らしさを、日本そして世界に向けて発信することを目的に1992年に発足しました。
翌1993年に第1回大阪国際室内楽コンクール&フェスタを開催。以降、3年毎に回を重ねて多くの優れたアンサンブルを輩出してきました。
コンクールは世界の著名な音楽家に審査委員を委嘱し、室内楽に熱心に取り組む若きアンサンブルを広く世界中から募っています。
同時期に開催される大阪国際室内楽フェスタはクラシック音楽、民俗音楽、伝統音楽などジャンル不問の器楽アンサンブルを楽しめるイベントとなっています。
部門
第1部門:弦楽四重奏(2つのヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ)
第2部門:ピアノ三重奏(ピアノ、ヴァイオリン、チェロ)
ピアノ四重奏(ピアノ、ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ)
表彰内容
表彰
●コンクール第1部門、第2部門各々の優秀団体に次の賞が授与される。
第1位 250万円、表彰状
第2位 120万円、表彰状
第3位 80万円、表彰状
各部門の第1位受賞団体は、日本国内の約10都市で開催される演奏会ツアー(「グランプリ・コンサート」)に招聘される。
特別賞
|
ブリテン・ピアーズ・アーツ賞 |
本特別賞を受賞した団体は、ブリテン・ピアーズ・アーツが2027/2028年シーズンにイギリスで 開催するブリテン・ピアーズ・ヤングアーティスト・プログラムに参加する。 |
|
ミュージック・イン・平昌賞 |
本特別賞を受賞した団体は、2027年に開催されるミュージック・イン・平昌に参加する。 |
|
ボルドー弦楽四重奏フェスティバル賞 |
第1部門に参加している弦楽四重奏から1団体に授与される。受賞した団体は、2027年5月に開 催される「ボルドー弦楽四重奏フェスティバル」に参加して、マスタークラスの受講やコンサートへ 出演する。 |
|
ストリング・クァルテット・ビエンナーレ・アムステルダム賞 |
第1部門で第1位を受賞した弦楽四重奏は、2028年1月にアムステルダムで開催される「ストリン グ・クァルテット・ビエンナーレ・アムステルダム」に出演する。 |
|
第12回大阪国際室内楽コンクール アンバサダー賞 |
コンクールに参加している団体から1団体に授与される。受賞した団体は、VdSQ & Festival4 (www.vdsq.de)が2028年に開催する室内楽フェスティバルに、本コンクールのアンバサダーとし て出演する。 この賞はVdSQの会長により授与される。 |
|
※MK記念会特別協力 特別賞を受賞して上記の特別賞のフェスティバル、プログラムに参加する団体には、一般社団法人MK記念会からの寄 付金を財源として、交通費の一部を補助する。 ※各部門入賞団体は、2026年5月23日(土)住友生命いずみホールで開催する披露演奏会(大阪)に無料で出演しなければならない。 ※各部門の第1位受賞団体は、5月24日(日)サントリーホールで開催する披露演奏会(東京)に無料で出演しなければならない。大阪-東京間の旅費と宿泊費は、主催者が負担する。会場:サントリーホール ブルーローズ(東京都港区) |
|
審査員
モニカ・ヘンシェル(審査委員長)
ウェイガン・リ
澤和樹
オリヴァー・ヴィレ
元渕舞
アリステル・テイトゥ
サンウォン・ヤン
相沢吏江子
野平一郎
応募資格
国・地域に関係なく1990年5月18日以降に出生した演奏者によって編成される団体が応募できる。
応募方法
申込期日
2025年4月1日(火)~10月12日(日)
申込方法
または、こちらの英サイトから、オンライン申込サービス“MUVAC”(www.muvac.com)にアクセスし、必要なデータを入力、または提出する。
申込終了後、MUVACより完了メールが自動配信される。完了メールの受信を確認すること。
全ての情報、資料の提出、2.5に規定された申込料の支払いをもって、応募の完了とする。
応募団体による演奏動画
・2025年1月以降に収録したもので、録画形式はMP4であること。
・両部門共通:コンクール1次ラウンドの課題曲[1]から1曲、そして2次ラウンドの課題曲から1曲を選び収録する。
<録画に際した注意>
・1台の固定カメラで撮影し、団体のメンバー全員が楽器と共に常時明瞭に映っていること。
・1曲ごとに録画して構わないが、各曲は全楽章をワンテイクで通して演奏収録する。
・録画する部屋や撮影用カメラやマイクなど、国際音楽コンクールの応募に相応しいレベルの録画を心がけること。録画の品質によっては、予備審査の対象にならない場合があります。
・カメラに音量を自動で調整する機能が付いている場合は、設定をオフにして録画する。
・撮影した録画は編集や、音質を高めるような、いかなる加工もしてはならない。
・提出する際には、ファイル名は「団体名_演奏曲目」とすること。
1回あたりの参加料(消費税込)
コンクールに応募する団体は、MUVACで申込料として20,000円を支払う。
スケジュール
予備審査は、応募資料及び演奏動画に基づいて行われる。
審査結果は、2025年12月31日(水)までにすべての応募団体にEメールで連絡される。
第1部門
2026年5月17日(日) 第1ラウンド
2026年5月19日(火) 第2ラウンド
2026年5月21日(木) 第3ラウンド
2026年5月22日(金) ファイナルラウンド
第2部門
2026年5月18日(月) 第1ラウンド
2026年5月20日(水) 第2ラウンド
2026年5月22日(金) ファイナルラウンド
会場
すべて 住友生命いずみホール(大阪)
大阪披露演奏会:2026年5月23日(土) 住友生命いずみホール(大阪)
東京披露演奏会:2026年5月24日(日) サントリーホール ブルーローズ(東京都港区)
開催地域・会場
住友生命いずみホール(大阪)
課題曲
【第1部門】(弦楽四重奏)
|
1次ラウンド |
次の[1]と[2]の2曲を演奏する。なお、演奏順は自由とする。 [1]次の作曲家の作品から1曲を選択して演奏する。 ※予備審査と同じ曲でも可 F. J. ハイドン: 弦楽四重奏曲 作品33,、42、50、54、55、64、71、74、76、 77 L. v. ベートーヴェン: 弦楽四重奏曲 作品18(第1番~第6番のいずれか1曲)(Bärenreiter、Henle) [2]次の作曲家の作品から1曲を選択して演奏する。 A. ベルク: 弦楽四重奏曲 作品3 A. ウェーベルン: 弦楽四重奏のための5つの楽章 作品5 G. クルターグ: 弦楽四重奏曲 作品1 |
|
2次ラウンド |
次の[1]と[2]の2曲を演奏する。なお、演奏順は自由とする。演奏時間は概ね60分以内とする。(60分に満たない選曲も可。) ※予備審査と同じ曲でも可 [1]次の作曲家の作品から1曲を選択して演奏する。 F. シューベルト: 弦楽四重奏曲 第13番 D804、第14番 D810 (Bärenreiter) F. メンデルスゾーン: 弦楽四重奏曲 第3番 作品44-1、第4番 作品44-2、第5番 作品44-3 R. シューマン: 弦楽四重奏曲 第1番 作品41-1、第2番 作品41-2、第3番 作品41-3 J. ブラームス: 弦楽四重奏曲 第1番 作品51-1、第2番 作品51-2、第3番 作品67 A. ドヴォルザーク: 弦楽四重奏曲 第13番 作品106、第14番 作品105 B. スメタナ: 弦楽四重奏曲 第1番 C. ドビュッシー: 弦楽四重奏曲 作品10 G. フォーレ: 弦楽四重奏曲 作品121 M. ラヴェル: 弦楽四重奏曲 D. ショスタコーヴィチ: 弦楽四重奏曲 第9番 作品117、第10番 作品118、第11番 作品122、第12番 作品133 F. スウェイン: 弦楽四重奏曲 第1番 [2]次の作曲家の作品から1曲を選択して演奏する。 B. バルトーク: 弦楽四重奏曲 第4番 Sz. 91、第5番 Sz. 102 A. シェーンベルク: 弦楽四重奏曲 第3番 作品30、第4番 作品37 A. ベルク: 「抒情組曲」 B. ブリテン: 弦楽四重奏曲 第2番 作品36 H. デュティユー: 「夜はかくの如し」 G. リゲティ: 弦楽四重奏曲 第1番、第2番 I. クセナキス: 「テトラス」 E. カーター: 弦楽四重奏曲 第2番、第5番 T. アデス: 「アルカディアーナ」、「4つの四重奏曲」 M.トロヤーン: 弦楽四重奏曲 第3番、第4番、第5番 武満 徹: 「ア・ウェイ・ア・ローン」 西村 朗: 弦楽四重奏曲 第6番 細川 俊夫: 「沈黙の花」 湯浅 譲二: 「弦楽四重奏のためのプロジェクション II」 |
|
3次ラウンド |
次の[1]と[2]の2曲を演奏する。なお、演奏順は自由とする。演奏時間は概ね60分以内とする。 [1]酒井 健治: 委嘱新作 ※スコアと演奏用パート譜は、2026年2月末までにコンクール参加団体に送られる。 ※作品の演奏時間は15分以内となる予定。 [2]参加団体の任意の弦楽四重奏曲 ※複数の楽曲を演奏することも出来るが、楽章抜粋は認めない。 ※他のラウンドで演奏する楽曲は演奏できない。 ※弦楽四重奏作品以外からの編曲の楽曲は演奏できない。 ※参加団体は主催者からスコアの提出を求められることがある。 |
|
ファイナルラウンド |
次の作曲家の作品から1曲を選択して演奏する。 L. v. ベートーヴェン: 弦楽四重奏曲 第12番 作品127、第13番 作品130、第14番 作品131、第15番 作品132 (Bärenreiter、Henle) ※第13番 作品130の終楽章は、大フーガ 作品133へ変更しても可。 F. シューベルト: 弦楽四重奏曲 第15番 ト長調 D887 (Bärenreiter) ※参加団体が3次ラウンドでベートーヴェンの楽曲(作品59、74、95、127、130、131、132)を演奏していない場合、シューベルトは選択できない。 |
【第2部門】(ピアノ三重奏)
|
1次ラウンド |
次の[1]と[2]の2曲を演奏する。なお、演奏順は自由とする。 [1]次の作曲家の作品から1曲を選択して演奏する。 ※予備審査と同じ曲でも可 F. J. ハイドン: ピアノ三重奏曲 Hob. XV-24、25、26、27、28、29 W. A. モーツァルト: ピアノ三重奏曲 K. 496、502、542、548、564 L. v. ベートーヴェン: ピアノ三重奏曲 第1番 作品1-1、第2番 作品1-2、第3番 作品1-3 [2]次の作曲家の作品から1曲を選択して演奏する。 細川 俊夫: 「トリオ」(2013年、〈2017年改訂〉)(Schott Japan) W. リーム: 「見知らぬ土地の情景」Ⅰ又はIII(1982-1984) M. カーゲル: ピアノ三重奏曲第1番、第2番、第3番 J. ハービソン: ピアノ三重奏曲第2番 |
|
2次ラウンド |
次の[1]と[2]の2曲を演奏する。なお、演奏順は自由とする。 ※予備審査と同じ曲でも可 [1]次の作曲家の作品から1曲を選択して演奏する。 J. ブラームス: ピアノ三重奏曲 第1番 作品8(1889年改訂版)、第2番 作品87、第3番 作品101 F. メンデルスゾーン: ピアノ三重奏曲 第1番 作品49、第2番 作品66 R. シューマン: ピアノ三重奏曲 第1番 作品63、第2番 作品80、第3番 作品110 A. ドヴォルザーク: ピアノ三重奏曲 第3番 作品65、第4番 作品90 B. スメタナ: ピアノ三重奏曲 作品15 G. フォーレ: ピアノ三重奏曲 作品120 M. ラヴェル: ピアノ三重奏曲 E. ショーソン: ピアノ三重奏曲 作品3 A. アレンスキー: ピアノ三重奏曲 第1番 作品32 [2]次の作曲家の作品から1曲を選択して演奏する。 C. アイヴス: ピアノ三重奏曲(1910) D. ショスタコーヴィチ: ピアノ三重奏曲 第2番 作品67(1947) Y. ヘラー: 「白昼夢」(1994)(Boosy & Hawkes) M. ワインベルク: ピアノ三重奏曲 作品24(1945) B. マルティヌー: ピアノ三重奏曲 第2番(1950)、第3番(1951) R. クラーク: ピアノ三重奏曲(1921) |
|
ファイナルラウンド |
次の[1]と[2]の2曲を演奏する。なお、演奏順は自由とする。 [1]次の作曲家の作品から1曲を選択して演奏する。 F. シューベルト: ピアノ三重奏曲 第1番 D898、第2番 D929 ※参加団体は第2番の終楽章において、任意でカット無し版を演奏することが出来る。 [2]次の日本人作曲家の作品を演奏する。 武満 徹: 「ビトウィーン・タイズ」(1993)(Schott Japan) |
【第2部門】(ピアノ四重奏)
|
1次ラウンド |
次の[1]と[2]の2曲を演奏する。なお、演奏順は自由とする。 [1]次の作曲家の作品から1曲を選択して演奏する。 ※予備審査と同じ曲でも可 W. A. モーツァルト: ピアノ四重奏曲 第1番 K. 478、第2番 K. 493 L. v. ベートーヴェン: ピアノ四重奏曲 作品16 [2]次の作品を演奏する。 A. シュニトケ: ピアノ四重奏曲 |
|
2次ラウンド |
次の[1]と[2]の2曲を演奏する。なお、演奏順は自由とする。 ※予備審査と同じ曲でも可 [1]次の作曲家の作品から1曲を選択して演奏する。 R. シューマン: ピアノ四重奏曲 作品47 R. シュトラウス: ピアノ四重奏曲 作品13 A. ドヴォルザーク: ピアノ四重奏曲 作品87 G. フォーレ: ピアノ四重奏曲 第1番 作品15、第2番 作品45 C. サン=サーンス: ピアノ四重奏曲 作品41 E. ショーソン: ピアノ四重奏曲 作品30 W. ウォルトン: ピアノ四重奏曲 F. スウェイン: ピアノ四重奏曲 [2]次の作曲家の作品から1曲を選択して演奏する。 G. エネスコ: ピアノ四重奏曲 第1番 作品16(1909)、第2番 作品30(1944) A. コープランド: ピアノ四重奏曲(1950) C.ローテン: ピアノ四重奏曲 作品42(1992)(Editions Musica-nova) S. スタッキー: ピアノ四重奏曲(2005)(Theodore Presser) F. ドナトーニ: 「ロンダ」(1983) |
|
ファイナルラウンド |
次の[1]と[2]の2曲を演奏する。なお、演奏順は自由とする。 [1]次の作曲家の作品から1曲を選択して演奏する。 J. ブラームス: ピアノ四重奏曲 第1番 作品25、第2番 作品26、第3番 作品60 [2]次の作曲家の作品を演奏する。 細川 俊夫: 「レテの水」(2015)(Schott Japan) |
補足事項
第12回大阪国際室内楽コンクール入賞後にメンバー変更が生じた場合、「グランプリ・コンサート」や各特別賞による参加権利を失う場合がある。