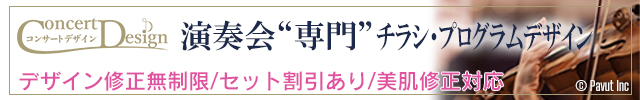夕暮れの公園で子どもたちが口ずさむ『夕焼小焼』に、そばにいた祖父母が思わず声を重ねる ──この光景こそ、童謡が世代を超えて心を結ぶ証しだ。今年で節目を迎える第40回 「寬仁親王牌・彬子女王牌 童謡こどもの歌コンクール」は、そんな日本固有の文化の魅力を未来へ届ける祭典である。
本記事では、現在、参加者募集中でもある同コンクールの歴史と魅力について、公式インタビューの内容をもとにその歩みと未来への展望を物語のようにたどっていく。
取材・文:山本知恵
ピアノ歴30年以上、他にもクラリネット、ヴァイオリンの演奏経歴を持つ音楽と美術を愛するライター。2023年にピティナ特級公式レポーターを務める。好きな曲はベートーヴェンのピアノソナタ第8番「悲愴」とヘンデルのオラトリオ「メサイア」。
<取材協力者>
早川 史郎(日本童謡協会 会長/審査委員長)
日本の現代こどもの歌・保育の歌の研究と作曲に力を注ぎ、1951年6月『現代こどもの歌1000曲シリーズ全10巻』の編曲・編纂で第7回日本童謡賞を受賞。1992年4月からNHK教育テレビ「ワンツー・どん」の音楽監督及び「しろうおじさん」として出演。2022年第20回童謡文化賞受賞。主な作品:『そらでえんそくしてみたい』『おやすみなさい』『夕やけ』『地球の音』
大石 泰(東京藝術大学名誉教授/審査ファシリテーター)
テレビ朝日在職中、主に「題名のない音楽会」「オリジナル・コンサート」などの音楽番組を担当。東京藝術大学転職後は、「コンサート・プロデュース論」の授業の傍ら、「藝大プロジェクト」「藝大とあそぼう」など、藝大奏楽堂で行われるさまざまなコンサートの企画・制作に当たる。また学外でも井上あずみ「親と子のはじめてのコンサート」など、多くのコンサートの構成・演出を手がける。
甲斐 小百合(テレビ朝日 プロデューサー/事務局長)
童謡の成り立ちと受け継がれる文化
大正期に生まれた『赤とんぼ』や昭和の『ぞうさん』、そして平成・令和の新しい子どもの歌まで、日本には数えきれない童謡が存在する。これほど多くの「こどもの歌」を持つ国は稀有であり、おそらく日本だけだろう。
童謡の源流をたどれば、昔ながらのわらべ唄や、明治期に西洋音楽を取り入れて作られた唱歌があり、そこから児童文学と結びついた童謡が大正・昭和期に開花した。
童謡は「正しく美しい日本語の教育」として大変優れた教材とも言われ、伝統的な精神を受け継ぎつつ、現代の子どもたちに愛される新しい歌も次々に生みだしてきた。童謡の文化は、まさに「伝承」と「創造」という営みの中で育まれ、時代を超えて歌い継がれてきたのである。
コンクール誕生──100年越しの願い
「このコンクールは100年以上前から始まっている」
そう語るのは審査委員長の早川氏だ。物語は1918年、大正7年に起きた“童謡運動”から始まる。
学校で唱歌が教えられている一方、詩人と作曲家は「子どもの言葉」を生かした自由な歌に挑戦し、童謡が芽吹いた。その後レコードとラジオが歌を全国へ運び、戦後は子どもの人権尊重の風が追い風に。1948年の「こどもの日」制定も関心を高めた。
こうした流れのなか「童謡をもっと広めたい」という熱意から日本童謡協会は童謡の展覧会を開き、皇室や公文教育研究会の支援を得て1986年に第1回大会へと結実する。
“童謡”の正体について早川氏はこう語る。
「童謡は実は音楽ではなかったんです。子どもの言葉や遊びを大切にする文化なんです。子どもはどんな言葉を喋るの?どんな遊びをするの?どんなうたが好きなの?そういったことをしっかり考えることがこのコンクールの基本的な考え方です。」
以来コンクールは40年、部門や審査の内容をその時代に合わせて工夫しながらも、童謡に宿る“子どもの詩”という原点を大切に守り続けている。
ただの歌のコンクールではない
このコンクールは、他のコンクールとは一線を画す。
1986年の第1回大会開催以降、1989年からは寬仁親王殿下が名誉大会委員長をお務めになり、金賞受賞者に授与される「寬仁親王牌」を自らデザインされ、グランプリ大会にご臨席くださるなど、コンクールの歩みに深く寄り添ってこられた。このことからも、「童謡こどもの歌コンクール」は日本を代表する童謡の祭典として社会に認知されてきたのである。
現在では殿下のご長女である彬子女王殿下がその意思を継ぎ、2015年の第30回大会からご臨席くださり、童謡の文化発展をあたたかく後押しなさっている。
格式高いコンクールでありながら、親しみやすさも兼ね備えているのがこのコンクール最大の特徴だ。子どもから大人まで誰もが何度でも参加できる懐の深さは他に類を見ない。
「子どもの歌っていうのは『子どもがうたう歌』と考えるんでしょうけども、実際に作っているのはみんな大人なんですよね。大人が作って大人の人が子どもに伝えない限りは子どもは歌わないってことなんです。だから子どもに伝わる自分の声で語るってことが大事なのです。おじいちゃんはおじいちゃんの語り方で、お母さんはお母さんの語り方で、子どもはそれを聞いて自分の声にかえて歌うんです。」
そう語る早川氏の言葉の端々には、子どもへの深い愛情と、童謡という言葉の文化を通じて人のつながりを何より大切にするあたたかな人柄がにじみ出る。
こうして、出場者たちは先人から受け継いだ歌の魅力を実感しながら、次の世代へと歌声のバトンをつなぎ続けている。
キッズ部門の創設と「彬子女王牌」
現在の部門は〈キッズ部門〉〈こども部門〉〈大人部門〉〈ファミリー部門〉の4つ。
今年の第40回大会に創設されたキッズ部門は、これまで「こども部門」の中で2つのグループに分かれていた審査を改め、小学3年生以下の部門を独立させた。
注目なのが、彬子女王殿下の御名を冠した「彬子女王牌」の誕生だ。キッズ部門の金賞受賞者にはこの栄誉ある牌が授与される。そして、キッズ部門を創設したことにより、全4部門に栄えある宮牌が授与されることとなった。
気になるデザインについてテレビ朝日プロデューサーの甲斐氏に尋ねてみたところ、「新たな牌につきましては、彬子女王殿下とも一緒に打ち合わせを重ねながらデザインを決めているところです」と、笑顔で答えてくれた。
皇室からの新たな牌の誕生は、伝統と革新の両輪で未来へ向かうシンボルとなるだろう。完成発表が楽しみだ。(※2025年5月上旬現在)
親子で参加することの本当の意味
子どもだけでなく大人にも門戸を開いているこのコンクールでは、親子三世代で同じ童謡を口ずさむことも珍しくない。まさに世代を超えて歌い継ぐ喜びを体現する場なのだ。
早川氏は、「大人が歌うということは、大人の心の中にある子どもに向けて歌うこと」と語り、子どもの純真さと大人の童心が響き合う舞台であることをあらためて伝えている。
また、ファミリー部門について大石氏はこう語る。
「家族たちが協力し合って、仲良く童謡を歌うその姿がすごく良いものだと思ってます。そのため、言葉を大切にする童謡を家族で歌うための部門を設けているわけです。出場者の皆様それぞれ工夫をしていて聞いていて楽しい部門でもあります。」
参加者は歌の上手下手ではなく童謡を愛する気持ちで繋がっており、会場全体がやさしいハーモニーに包まれるのが、このコンクールの醍醐味である。
歌声を評価する舞台裏の変化と進化
長い歴史を持つ「童謡こどもの歌コンクール」は、時代の流れに合わせて審査方法も少しずつ形を変えてきた。
第7回大会までは実行委員会形式にて行われていたが、現在ではテレビ朝日や日本童謡協会が主体となって運営している。審査方法も第31回大会から大きく進化を遂げている。詳しくはこちらの図を参照していただきたい。
現在の名称「童謡こどもの歌コンクール」が採用されたのは、2016年の第31回大会からである。
その経緯を大石氏はこう語る。
「前タイトルが『全国童謡歌唱コンクール』でしたが、漢字が続くのはちょっと硬いイメージもありますし、『歌唱』という文字が入ってると、どうしても歌のうまさを競うものと捉えられてしまうため。もちろんそれも重要な要素ではあるのですが、このコンクールはそれだけではないので、童謡の範囲を少し広げるということで『こどもの歌』というやわらかい表現を入れて、広く応募されるようなコンクールにしたいということでタイトルを変えました。」
さらに審査方法について「年齢や歌唱形態の異なる参加者それぞれが公正に評価されるよう部門分けと審査基準を工夫している」と加えた。その言葉どおり、誰もが主役になれる舞台が準備され、参加者が純粋に童謡と向き合える環境が用意されている。歌の練習までできる応募専用アプリもその一つだ。インストールさえすれば、スマホ一つでエントリーまで完結できる仕組みになっている。
さらなる発展に向け、プロデューサーの甲斐氏はこのように語る。
「童謡の歴史を伝承することが我々の、このコンクールの使命とも思っております。一人でも多くの方に本コンクールや童謡の魅力について知っていただくために、今後もコンクールの発展に力を注いでまいります。今年から新たに、InstagramやTikTokも開設したので、様々な形で童謡の認知度を広めることに貢献していきたいです。」
時代に合わせて柔軟に進化する姿勢こそが、コンクールの信頼と質を今日まで支えてきた力となっているに違いない。
心に残るエピソードと世代を超えた繋がり
長い歴史を持つ「童謡こどもの歌コンクール」では、毎回ステージ上で様々なドラマが生まれている。
「こども部門」で記憶に新しいのは、2020年の第35回大会に当時2歳5か月の村方乃々佳さんが出場し、『いぬのおまわりさん』を無邪気に歌い上げて史上最年少で銀賞を受賞したケースだ。会場中を笑顔にしたこの“小さな歌姫”は瞬く間に注目を集め、翌年には童謡歌手としてCDデビューまで果たし、史上最年少の童謡歌手として大きなニュースにもなっている。
「大人部門」では、2017年の第32回大会に当時90歳の浪打昭一さんが車椅子で出場し、『夕焼小焼』を静かに、しかし力強く歌い上げた。年齢を感じさせない澄んだ声と情感豊かな語り口は審査員と観客の心をつかみ、見事に金賞を受賞した。


この動画を YouTube で視聴
大石氏はやわらかな笑みを浮かべながら、当時を振り返った。
「出場者からプロのタレントさんになってる方もいらっしゃいます。司会をしている、はいだしょうこさんもそう。最近では何と言っても2歳の村方乃々佳さんが印象的でしたね。また、浪打昭一さんの歌も大変素晴らしく、心に残っています。なかには何年も連続して挑戦してくださっている方も大勢いらっしゃり、『やっとグランプリ大会に出場できました!』という言葉を聞くこともあり、大変嬉しく思っています。」
「童謡こどもの歌コンクール」では、歌の上手さだけでなく、童謡らしい表現やその人ならではの個性、そして何より「歌うことの楽しさ」が大切にされている。結果だけでは測れない、心と心が通い合うような体験。それこそが、参加者にとって一生の宝物となるに違いない。
童謡に息づく日本人のアイデンティティ
「童謡こどもの歌コンクール」は、日本の文化・日本語を見つめ直す場でもある。
早川氏は日本語の持つ力についてこう語る。
「日本の言葉は、とくに童謡においては『短い言葉の中に深い意味を持つ』という特徴があります。短く語る中に様々なことが浮かび上がり、心が動く——そういう体験をすることが重要なんです。」
わずかな言葉に深い情景と想いを込める——日本の童謡には俳句や短歌に通じる詩情の伝統が流れているのだ。参加者たちは童謡を歌うと、日本語のきれいな響きを感じとり、言葉が心にすっと入ってくる楽しさを味わえる。
「美しい言語である日本語をずっと我々は喋り続けています。その中で、もっと昔の美しい言葉も受け継いでいくことによって、私たち日本人のアイデンティティが生まれてくるわけです。」
日本語の豊かさを、童謡という形で次の世代に伝えていくことの意義について早川氏はおだやかに語った。
そして、さらにこう続ける。
「童謡の音楽的な傾向は、クラシック音楽が基本となっています。だから日本の民謡や雅楽でもないし、歌舞伎の音楽でもない。西洋の音楽に日本の言葉を非常に豊かに埋め込んで、手を繋いで作った文化だから、これは日本固有の文化であると胸を張って言えるんです。西洋の文化を入れてなおかつ日本の文化をより深く追求してる。しかも子どもに確かな焦点を当てながら。」
東西が出会い調和した音楽に、日本語という魂が宿る──童謡はそうした独自の文化的発展の結晶であり、日本ならではの大切な伝統なのだ。
未来への展望──童謡のバトンを次の世代へ
最後に、インタビューに答えてくれた3名から読者へのメッセージを紹介したい。
審査委員長の早川氏は、童謡にふれる楽しさをあたたかく語ってくれた。
「日本には数え切れないほどたくさんの童謡があります。色々な歌を自分で探していただいて、自分が1番歌いたい、そして自分の声や自分の気持ちに合っている歌を見つけ出し、楽しんで歌っていただくことを望んでおります。」
数々の音楽番組を手掛けてきた大石氏も、「難しく考えないで気軽に参加していただきたい。例えば、『各地方のテレビ局に行けるかも!』という動機でもいいのです。上手な歌を歌わなければ…ということもないので、まずは楽しむ気持ちで声を出してみてほしいです」と笑顔で呼びかける。
さらにプロデューサーの甲斐氏は、「曲を聞いた時に、『あ、この曲懐かしいな』とか、『あの時歌ったな』とか、人それぞれの思い出が詰まった曲が必ず1曲は童謡にはあると思います。ぜひ皆様にはその思いも載せてこのコンクールに参加していただけると嬉しいです。お待ちしています!」と熱いメッセージを寄せた。
ここで読者の皆さんに問いかけたい。
童謡に触れて心を動かされた経験はないだろうか。母が歌っていたあの歌──我が子が卒園式で歌ったあの歌──もし一度でもその優しいメロディに心を動かされたのなら、次はあなた自身が歌い手となってその輪に加わってみてはどうだろう。
「童謡こどもの歌コンクール」の参加費は無料。なんとグランプリ大会の観覧も無料というのだから驚きだ。こういった点にも、「童謡の文化を伝承していきたい」という強い想いが感じとれる。さらに驚くのが「一人何曲でも応募が可能」という点だ。親子で、友だちと、あるいは一人で──あなたの歌声が未来へのバトンになる。きっと次の夕暮れ、公園で誰かがあなたの歌を口ずさむ日が来るだろう。
「童謡こどもの歌コンクール」が、この先百年、二百年と歌声をつなぎ続けることを心から願ってやまない。
【第40回童謡こどもの歌コンクール開催概要】
▶募集期間
開始:2025年4月25日(金)
締切:2025年6月2日(月)
▶グランプリ大会
開催日:2025年11月9日(日)
会場:東京・EXシアター六本木
▶童謡こどもの歌コンクール公式HP
https://www.douyou-contest.com/