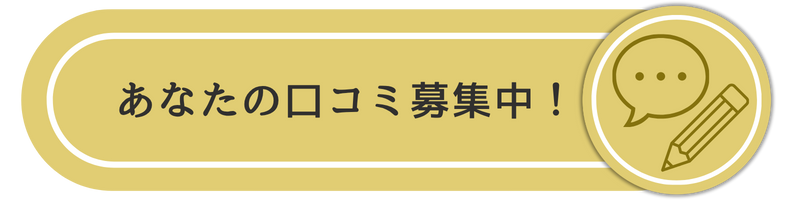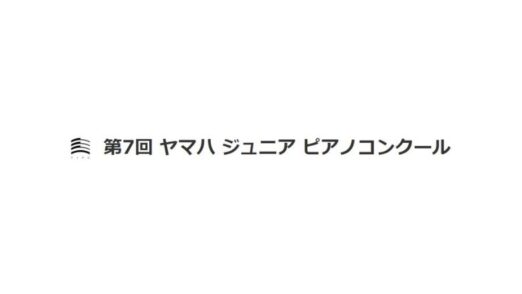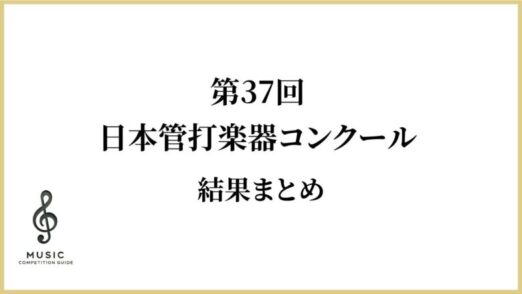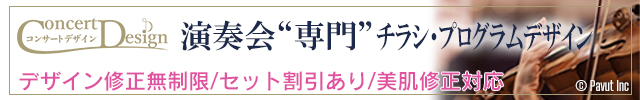- 2025年4月18日締切
東京音楽コンクールは、東京文化会館・読売新聞社・花王株式会社・東京都の四者が主催する音楽コンクールです。芸術家としての自立を目指す可能性に富んだ新人音楽家を発掘し、育成・支援を行うことを目的として実施するコンクールです。
審査部門はピアノ・金管・木管・声楽・弦楽の5つ。年によって開催部門は異なります。
本選ではオーケストラと共演する他、聴衆の投票で最も多い票を得た出場者に「聴衆賞」が贈られます。
入賞者には賞金だけでなく、手厚いサポートも提供されることが本コンクールの特徴の一つです。東京文化会館主催事業等への出演、リサイタル支援、音楽事務所やマスコミへの紹介、関係コンサート等への出演紹介や東京都交響楽団事業への出演推薦など、若手演奏家にとってはメジャーになる足がかりとして非常に魅力的といえます。
部門
●ピアノ部門
●木管部門
●声楽部門
歴代入賞者
こちらからご覧ください。
表彰内容
●部門ごとに、原則として第1位、第2位、第3位を入賞者とし、賞状及び下記の賞金を授与する。
第1位 100万円
第2位 60万円
第3位 40万円
●その他の本選出場者については、入選者とし、賞状と副賞を授与する。
●各部門の本選で聴衆による投票を行い、最も多い票を得た出場者に対し、聴衆賞と副賞を授与する。
【入賞者支援】
(1)東京文化会館主催事業等への出演
(2)リサイタル支援
(3)入賞者の紹介
(4)関係コンサート等への出演紹介
審査員
●ピアノ部門
東 誠三*/有森 博/上原彩子/岡田博美/若林 顕/シン・スジョン(元ソウル大学校音楽大学学長)/ボリス・ペトルシャンスキー(イモラ国際ピアノアカデミー教授)
●木管部門
上野由恵(Fl)/金子亜未(Ob)/近藤那々子(Ob)/フリスト・ドブリノヴ(Fl)/アレッサンドロ・ベヴェラリ(Cl)/三界秀実(Cl)/水谷上総(Fg)/吉田 將(Fg)*/ヘンリク・ヴィーゼ(Fl)(バイエルン放送交響楽団首席奏者)
●声楽部門
市原多朗(Ten)/大倉由紀枝(Sop)/大島幾雄(Br)*/久保田真澄(Bs)/高橋薫子(Sop)/竹本節子(Mez)/永井和子(Mez)/堀内康雄(Br)/彌勒忠史(Ct)/吉田浩之(Ten)/ヴィンチェンツォ・デ・ヴィーヴォ(イタリア サン・カルロ劇場元芸術監督)
●部門共通
下野竜也(指揮者)
●総合審査員長
野平一郎(東京文化会館音楽監督)
*部門審査員長
応募資格
【ピアノ部門】
~30歳 1994年6月1日以降に出生した方
国籍・居住地不問
※過去の「東京音楽コンクール」第1位入賞者は、同一部門での再応募はできない。
※第21回の第2位、第3位入賞者で、今回同一部門に応募する者は、第1次予選を免除する。ただし、申込期間中に必ず応募すること。
【木管部門】
18歳~30歳 1994年6月1日~2007年5月31日に出生した方
国籍・居住地不問
※過去の「東京音楽コンクール」第1位入賞者は、同一部門での再応募はできない。
※第21回の第2位、第3位入賞者で、今回同一部門に応募する者は、第1次予選を免除する。ただし、申込期間中に必ず応募すること。
【声楽部門】
20歳〜35歳 1989年6月1日~2005年5月31日に出生した方
国籍・居住地不問
※第22回の第2位、第3位入賞者で、今回同一部門に応募する者は、第1次予選を免除する。ただし、申込期間中に必ず応募すること。
応募方法
●申込はオンライン受付のみとする。
●4月9日12:00(正午)に公開する「エントリーフォーム」に必要事項を入力し必要データをアップロードすること。
●エントリーフォームの公開は「お知らせ」欄で通知する。
●応募期間内(2025年4月9日12:00から4月18日18:00まで)であれば修正可能。
●アップロードが必要なデータについて、郵送で提出する場合は、エントリーフォーム上で郵送希望を選択し、2025年4月18日(金)必着で事務局に送付すること。
送付する際は、封筒にオンライン申込時のログインID、氏名、部門、楽器(声種)を必ず明記すること。
|
〒110-8716 東京都台東区上野公園5-45 東京文化会館 事業係「東京音楽コンクール」事務局 |
●申込を受理した方に通知する案内に従って、納入期間内に参加費(¥30,800)をオンラインカード決済またはコンビニ決済にて納入すること。
2025年5月12日(月)12:00(正午)~19日(月)18:00厳守
(期間外の納入は受け付けない)
スケジュール
●参加申込 2025年4月9日12:00から4月18日18:00まで
●参加費納入期間 2025年5月12日(月)12:00(正午)~19日(月)18:00厳守
●第1次予選受付時間の通知 2025年5月30日(金)頃にマイページにて通知
|
ピアノ部門 |
木管部門 |
声楽部門 |
|
|
第1次予選 東京文化会館小ホール・非公開 |
6月27日(金) 6月28日(土) 6月29日(日) |
7月1日(火) 7月2日(水) 7月3日(木) |
6月24日(火) 6月25日(水) |
|
第2次予選 東京文化会館小ホール・公開 |
8月24日(日) |
8月22日(金) |
8月23日(土) |
|
本選及び表彰式 東京文化会館大ホール・公開 |
8月31日(日) 大井剛史指揮/東京交響楽団 |
8月27日(水) 角田鋼亮指揮/東京フィルハーモニー交響楽団 |
8月29日(金) 現田茂夫指揮/東京フィルハーモニー交響楽団 |
●第23回東京音楽コンクール 優勝者&最高位入賞者コンサート
2026年1月12日(月・祝) 東京文化会館大ホール
開催地域・会場
東京文化会館
課題曲
ピアノ部門
|
■を予選ではすべて記載順に、本選では選択した1曲を暗譜で演奏すること。 |
|
第1次予選 |
|
■J.S.バッハの平均律クラヴィーア曲集(下記の中から選択)とF.ショパンのエチュードOp.10又はOp.25の中からそれぞれ異なる1曲ずつを組み合わせたプログラムを2種用意すること。いずれかの組み合わせを当日各自の抽選により演奏すること。 *ショパンのエチュードはOp.10-3、Op.10-6、Op.25-7を除く。 *バッハ、ショパンの順で演奏すること。 J.S.バッハ:平均律クラヴィーア曲集より プレリュードとフーガ(繰り返しなし) 第1巻 No.1 ハ長調 No.2 ハ短調 No.3 嬰ハ長調 No.5 ニ長調 No.6 ニ短調 No.9 ホ長調 No.10 ホ短調 No.11 へ長調 No.13 嬰へ長調 No.14 嬰へ短調 No.15 ト長調 No.16 ト短調 No.17 変イ長調 No.18 嬰ト短調 No.19 イ長調 No.21 変ロ長調 No.23 ロ長調 第2巻 No.1 ハ長調 No.2 ハ短調 No.3 嬰ハ長調 No.6 ニ短調 No.7 変ホ長調 No.12 へ短調 No.15 ト長調 No.19 イ長調 No.20 イ短調 No.24 ロ短調 ■ F.リスト、C.ドビュッシー、A.スクリャービン、S.ラフマニノフ、B.バルトークのエチュードより任意の1曲(繰り返しなし) *演奏はカットする場合がある。 |
|
第2次予選 |
|
■以下のうち複数の時代を選び、30~35分(出ハケ、曲間を含まない)のプログラムを構成すること。 作品の時代区分は、各々の見識で判断すること。 •バロックの作品 •古典派の作品 •ロマン派の作品 •近現代の作品 *第1次予選で演奏する曲と重複してはならない。 *楽譜が出版されている曲に限る。楽譜の提出を求める場合がある。 *実際の演奏時間で算出すること。 |
|
本選 |
|
■以下のうち任意の1曲 W.A.モーツァルト:ピアノ協奏曲第20番 ニ短調 K466 W.A.モーツァルト:ピアノ協奏曲第21番 ハ長調 K467 W.A.モーツァルト:ピアノ協奏曲第23番 イ長調 K488 W.A.モーツァルト:ピアノ協奏曲第24番 ハ短調 K491 W.A.モーツァルト:ピアノ協奏曲第26番 ニ長調 K537「戴冠式」 W.A.モーツァルト:ピアノ協奏曲第27番 変ロ長調 K595 L.v.ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第3番 ハ短調 Op.37 L.v.ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第4番 ト長調 Op.58 L.v.ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第5番 変ホ長調 Op.73「皇帝」 F.ショパン:ピアノ協奏曲第1番 ホ短調 Op.11 F.ショパン:ピアノ協奏曲第2番 ヘ短調 Op.21 R.シューマン:ピアノ協奏曲 イ短調 Op.54 F.リスト:ピアノ協奏曲第1番 変ホ長調 S124 F.リスト:ピアノ協奏曲第2番 イ長調 S125 C.サン=サーンス:ピアノ協奏曲第2番 ト短調 Op.22 C.サン=サーンス:ピアノ協奏曲第5番 へ長調 Op.103「エジプト風」 P.I.チャイコフスキー:ピアノ協奏曲第1番 変ロ短調 Op.23 E.グリーグ:ピアノ協奏曲 イ短調 Op.16 S.ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第2番 ハ短調 Op.18 S.ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第3番 ニ短調 Op.30 S.ラフマニノフ:パガニーニの主題による狂詩曲 Op.43 M.ラヴェル:ピアノ協奏曲 ト長調 B.バルトーク:ピアノ協奏曲第2番 Sz.95 B.バルトーク:ピアノ協奏曲第3番 Sz.119 S.プロコフィエフ:ピアノ協奏曲第2番 ト短調 Op.16 S.プロコフィエフ:ピアノ協奏曲第3番 ハ長調 Op.26 |
木管部門
|
フルート ●課題曲 ■を予選では全て記載順に、本選では選択した1曲を暗譜で演奏すること。 木管部門の第1次・第2次予選は暗譜を必要としない。 *予選では途中で演奏を打ち切る場合がある |
|
第1次予選 |
|
■以下のうち任意の1曲(繰り返しなし) J.S.バッハ:無伴奏フルートのためのパルティータ イ短調 BWV1013より アルマンド、クーラント C.P.E.バッハ:フルート・ソナタ イ短調 Wq.132 H562より 第2楽章、第3楽章 |
|
第2次予選 |
|
■C.ライネッケ:フルート・ソナタ「ウンディーネ」 Op.167より 第1楽章(繰り返しなし)、第2楽章 ■O.メシアン:黒つぐみ |
|
本選 |
|
■W.A.モーツァルト:フルート協奏曲第1番 ト長調 K313 |
|
オーボエ ●課題曲 ■を予選では全て記載順に、本選では選択した1曲を暗譜で演奏すること。 木管部門の第1次・第2次予選は暗譜を必要としない。 *予選では途中で演奏を打ち切る場合がある。 |
|
第1次予選 |
|
■以下のうち任意の1曲 G.F.ヘンデル:オーボエ・ソナタ ハ短調 Op.1-8 HWV366より 第1楽章、第2楽章 C.P.E.バッハ:オーボエ・ソナタ ト短調 Wq.135 H549より 第1楽章、第2楽章(繰り返しなし) |
|
第2次予選 |
|
■以下のうち任意の一曲 D.ミヨー:オーボエ・ソナチネ Op.337 N.スカルコッタス:オーボエとピアノのためのコンチェルティーノ AK28 A.ドラティ:オーボエとピアノのための協奏的二重奏曲 H.デュティユー:オーボエ・ソナタ K.シュトックハウゼン:In Freundschaft |
|
本選 |
|
■W.A.モーツァルト:オーボエ協奏曲 ハ長調 K314 |
|
クラリネット ●課題曲 ■を演奏すること。本選は暗譜とする。 木管部門の第1次・第2次予選は暗譜を必要としない。 *予選では途中で演奏を打ち切る場合がある。 |
|
第1次予選 |
|
■以下のうち任意の1曲 I.ストラヴィンスキー:クラリネット独奏のための3つの小品〔Chester Music版〕 K.ペンデレツキ:クラリネット独奏のための前奏曲〔Schott版〕 B.コヴァーチ:シュトラウスへのオマージュ〔Edition Darok版〕 |
|
第2次予選 |
|
AとBの演奏順は自由。 ■A:以下のうち任意の一曲 J.ブラームス:クラリネット・ソナタ第1番 ヘ短調 Op.120-1より 第1楽章 J.ブラームス:クラリネット・ソナタ第2番 変ホ長調 Op.120-2より 第1楽章 ■B:以下のうち任意の一曲 P.ルヴェル:ファンタジー〔Alphonse Leduc版〕 E.ボザ:ブコリーク〔Alphonse Leduc版〕 R.ガロワ=モンブラン:コンツェルトシュトゥック〔Alphonse Leduc版〕 |
|
本選 |
|
■W.A.モーツァルト:クラリネット協奏曲 イ長調 K622(バセットクラリネットで演奏しても良い) |
|
ファゴット ●課題曲 ■を予選では全て記載順に、本選では選択した1曲を暗譜で演奏すること。 木管部門の第1次・第2次予選は暗譜を必要としない。 *予選では途中で演奏を打ち切る場合がある。 |
|
第1次予選 |
|
■以下より任意の1曲(アーティキュレーション、オーナメントは任意とする。) A.ヴィヴァルディ:チェロと通奏低音のための9つのソナタ〔Musica Budapest版〕 第6番 変ロ長調 RV46より 第1楽章、第4楽章(繰り返しなし) 第7番 ト短調 RV42より 第3楽章、第4楽章(第3楽章、第4楽章共に繰り返しなし) 第8番 イ短調 RV44より 第1楽章、第2楽章(第1楽章は前奏なし、4小節目のソロから演奏、第2楽章は繰り返しなし) |
|
第2次予選 |
|
■以下のうち任意の1曲 R.シューマン:幻想小曲集 Op.73より 第1曲 R.シューマン:幻想小曲集 Op.73より 第2曲 *チェロのパート譜を使用すること。 ■以下のうち任意の1曲 M.ビッチュ:ファゴット・コンチェルティーノ A.ベルノー:ハルシナシオン |
|
本選 |
|
■W.A.モーツァルト:ファゴット協奏曲 変ロ長調 K191/186e〔Bärenreiter版〕 |
声楽部門
|
第1次予選 |
|
歌曲とアリア各1曲を、8分以内(曲間含む)のプログラムで構成すること。※無伴奏は不可 |
|
第2次予選 |
|
歌曲とアリアを各1曲以上、約15分(曲間含む)のプログラムを構成すること。曲数は任意とする。 ※無伴奏は不可 |
|
本選 |
|
アリアまたはアリア以外で、オーケストラ伴奏による約15~20分(曲間含む。プログラム途中の出ハケは含まない。)のプログラムを構成すること。曲数は任意とする。 ※アリア以外の曲は、オリジナルがオーケストラ編成の作品に限る。 (オーケストラ用に編曲されたもの、歌譜とオーケストラ譜の調性が異なるもの、オーケストラ譜の入手が著しく困難なものは不可。ただし、作曲者本人が編曲したものは可) |
*アリアは、オペラ・アリア、オラトリオ・アリア、モーツァルトのコンサート・アリアのいずれも可。
*第1次予選、第2次予選及び本選で演奏する楽曲はすべて重複しないこと。
*アリアは原調とすること。
ただし、慣例として移調が認められる場合もあるので、原調でない場合は問い合わせること。
*歌詞は原語とする。
【原語例】
・A.ドヴォルザーク:オペラ『ルサルカ』/チェコ語
・G.ドニゼッティ:オペラ『連隊の娘』/フランス語
・P.I.チャイコフスキー:オペラ『オルレアンの少女』/ロシア語
*申込書の曲名欄に、作品名(原語及び日本語)を記入すること。
アリアについては、歌い出し部分の歌詞を記入すること。
*なお、上記の中で不明と思われる事があれば問い合わせること。
第1次予選/第2次予選
*演奏順は原則として申込書の記載順とするが、変更の希望がある場合は、予選当日、受付時に申し出ること。
*無伴奏は不可。
本選
*アリア以外の曲は、オリジナルがオーケストラ編成の作品に限る。
(オーケストラ用に編曲されたもの、歌譜とオーケストラ譜の調性が異なるもの、オーケストラ譜の入手が著しく困難なものは不可。ただし、作曲者本人が編曲したものは可)
補足事項
主催
公益財団法人東京都歴史文化財団 東京文化会館、読売新聞社、花王株式会社、東京都