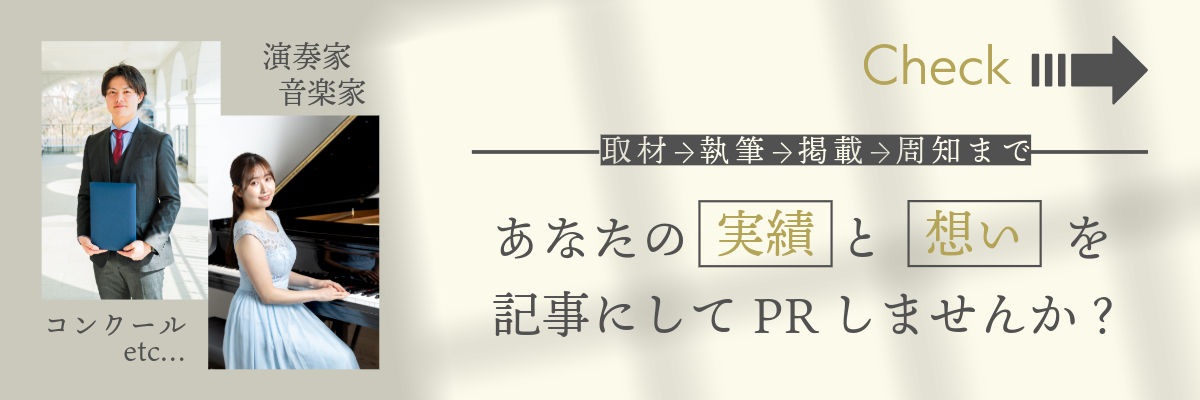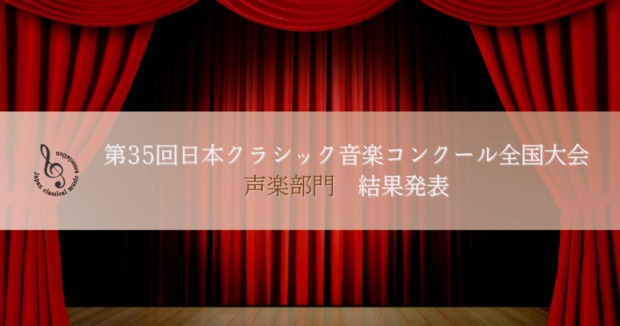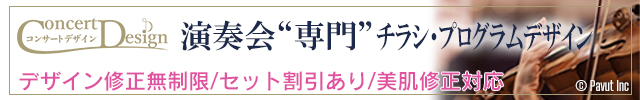ヨーロッパ音楽の伝統を受け継ぎ、孤高の美学を築いてきた松山元さん。デジタル化で音楽が「断片」として消費されがちな現代において、その妥協のない純粋な演奏観は、真の芸術のあり方を問い直します。
第35回日本クラシック音楽コンクール・大学男子の部で「最高位5位」という結果を下した決断の根底には、先人からの系譜を継ぎながらも自立して歩む「闊歩(かっぽ)」の精神がありました。
「ピアニストの前に、まず芸術家であれ」と説く言葉の裏側には、一回きりの舞台を神格化させるための覚悟が息づいています。厳格な審査に込められた、音楽の本質を伺いました。
取材・文|編集部
自分にピッタリな音楽コンクールが見つかる!国内外の音楽コンクール情報や結果まとめをわかりやすくご紹介し、次世代の音楽家や音楽ファンの皆様に寄り添います。
プロフィール
松山 元(Gen Matsuyama)
ピアニスト
所属:プロアルテムジケ音楽事務所
小林道夫、松浦豊明、外山準の各氏に指導を仰ぐ。その後、ドイツへ留学しドイツ国立ケルン音楽大学大学院修了。アロイス・コンタルスキー、タチアナ・ニコライエヴァ、室内楽をアマデウス弦楽四重奏団各氏に師事。K.H.シュトックハウゼンの演奏を始めとし、現代音楽の旗手として350曲以上の初演に携わり、中島健蔵音楽賞を受賞。自らはコンクールに頼らず(コンクールを受けたことはない)独自の道を切り拓いた経験から、門下生には「広い世界で活躍すること」を説き、藤田真央氏ら数多くの才能を輩出している。
趣味・特技
料理(歴史的レシピの再現や、素材を活かした即興料理)
読書、美術館巡り、散策と思索
【現職・役職】
クラングフォルム・ベルリン 代表
アンサンブル・ミルソニカ(2025)代表
文化庁芸術家在外研修員の会(在研会)理事
日本演奏連盟 会員
日本ロシア音楽家協会 会員
元 ベルリン芸術大学 客員教授
元 東京音楽大学 客員准教授(〜2017)
【主な経歴・受賞歴】
2000年度 文化庁派遣芸術家在外研修員
フンボルト大学(哲学科第Ⅳ・音楽美学)客員研究員
2010年 第28回中島健蔵音楽賞 受賞
国内外コンクール審査・演奏活動歴
招聘実績: 世界の著名国際音楽祭での招待演奏、国際ピアノコンクールの審査員、および国際ピアノ講習会講師として度々招聘されている。
審査員: セニガリア国際、Citta di OSTRA国際、国際ラフマニノフ、ピティナほか多数。
教育活動: ヴァルトクライブルク、ヴァッサーブルク等の国際ピアノ講習会講師、ならびに東京藝術大学、東京大学、ソウル大学等での講演活動
現在の指導活動について
日本クラシック音楽コンクール 第1位優勝者輩出: 藤田真央(グランプリ)、稲葉千隼、大谷内映、長谷生雅(計4名・延べ5件の第1位)
その他: 国際ガウデアムス演奏家コンクール、ロザリオ・マルシアーノ国際ピアノコンクール、日本音楽コンクール、全日本学生コンクール、宝塚ベガ音楽コンクール、彩の国・埼玉ピアノコンクール、大阪国際音楽コンクール等々、国内外の数多くのピアノコンクールにおいて第1位優勝者を輩出。
第35回日本クラシック音楽コンクールを終えて
──日本クラシック音楽コンクールでの審査を担当されたご感想と、全体としての印象をお聞かせください。
松山
まず全体を俯瞰しますと、「総じてレベルが高くなった」というのが第一印象です。しかししその一方で、上位入賞者は少なくなったようにも感じます。
この背景には、一つに「時代の流れ」があるでしょう。かつて音楽に携わる人々は、家庭環境も含め、ごく一部の層に限定されていました。それが時代を経て、クラシック音楽が日本の社会に広く浸透したことで、全体の底上げにつながったのだと思います。
ただ、「飛び抜けた才能」に出会う機会は少なくなってきているように思えます。これほど情報や環境が整った時代ですから、「もっと上の次元へ到達する人がいてもいいのではないか」と感じるのです。時代の劇的な変化の割には、飛躍的、あるいは飛翔的な意味での発展が見受けられないのが現状ではないでしょうか。
事実、私が審査を担当した「大学男子の部」では、第5位が最高位という結果になりました。これには様々な要因が考えられますが、一つには演奏に対する価値観の変化が影響しているように思えます。
──演奏に対する価値観。一体どのように変化したのでしょうか。
松山
私はヨーロッパの伝統的なものを、自分という人間を介して後進へ伝えていくことを自らの使命と考えています。大きな演奏の歴史という連なりのなかに、私は存在するわけですから。本来、ヨーロッパの音楽というのは時間の流れの内にあって「横につながったもの」、あるいは線と線の絡み合う「層」なのです。
ところが、現代はすべてがデジタルですから、基本的には「点」なんです。瞬間瞬間の連続であり、いわば写真を早く回した映画のようなもの。ですから、前述しました「いわゆるアナログ」的な音楽観と今のデジタル的な音楽観との間には、乖離(かいり)的とも言える大きな価値観の相違を感じています。
例えば、CD録音では録音場所のいかんを問わず、点と点、つまり良い部分だけをつなぎ合わせて一つの音楽をつくり上げます。それが果たして良いのか悪いのか。
歌や弦楽器の方は物理的に音がつながっているため、こうした「断片化」の意識を回避し、伝統的な価値観を持ち続けやすいようにも思えます。一方、ピアノは楽器の特性上、音を線として捉え続けることが難しいのかもしれません。
──日本クラシック音楽コンクールの特徴や強みはどのような点にあるとお考えですか。
松山
一つ目は、「絶対評価」に基づいた客観性です。上位入賞者の順位は、単なる参加者同士の相対的な比較ではなく、点数化された厳正な評価によって決まります。審査後の合議(話し合い)などで結果が調整されることも一切ありません。示された点数こそが結論であり、そこに「客観的な公平性」が保たれている点は非常に大きな強みです。
二つ目は、入賞記念演奏会への出演機会があること。
三つ目は、さらに上位に入賞すると、オーケストラと共演できることです。ピアニストはどうしても自分の世界に閉じこもりがちですが、オーケストラとの共演は、その殻を破る極めて貴重な体験となります。
もともと音楽の本質は「アンサンブル」。ですから、早い段階からオーケストラだけでなく、室内楽や歌手との共演などを通じて音楽の深淵に触れ、理解を深めていかなければなりません。「ピアノだけで完結する」と考えてはダメなんです。
若いピアニストの皆さんには、なるべく早くアンサンブルの経験を積むことをおすすめします。
──審査の際にはどのような点を特に重視されましたか。
松山
バランスです。演奏芸術における「技術」と「音楽性」は切っても切り離せない関係にありますから。さらに「表現力」とは、この両者が密接に結びつくことで必然的に備わってくるもの。とりわけ「個性」に関しては、それらの関係性の「結果」として最後にもたらされるものだと考えています。
演奏家の「個性」を捉えるのは、非常に難しいことです。実際、単なる「自分勝手な癖」を個性だと勘違いしてしまうケースが非常に多いんですよ。
土台となる「技術」は絶対に必要です。そして「音楽性」――つまり、作曲家がいた時代の様式への深い理解と、奏者自身が持つ音楽的な資質。これもまた不可欠です。 真の個性とは、これらが高い次元でバランスを保った時に初めて、自然と滲み出てくるものです。
決して「個性的であろう」と狙って作るものではありませんし、ましてや夜郎自大(やろうじだい)的——つまり自分の力量を知らず、独りよがりに振る舞うような「癖の強い演奏」であってはならないのです。
──自分の癖を「個性」とはき違えないように、ということですね。
松山
「個性的な演奏」という言葉は、実はとても危険なものです。なぜなら、その多くは自分よがりな「癖」に過ぎないからです。
まずは、作曲家のメッセージと、その独自のスタイルをありのままに受け入れること。そのプロセスを経てなお、にじみ出てしまう違いこそが本質なのです。作品に誠実に向き合った結果として、素直に、自然な姿で現れたものだけが、真の「個性」となり得ます。
逆に、作品に真摯に向かい合うことなく、楽譜や作曲家を自分をひけらかすための「道具」として利用したり、目立つために演じたりすることは、我々表現者にとって絶対にやってはいけない禁忌です。
どんな世界でも同じですが、「自分がこう感じるのだから、好きにやればいい」とわがままに振る舞うことを「跋扈(ばっこ)する」と言います。 一方で、伝統や真理を正しく受け継ぎ、自分の自我と相対化し、その結果として備わった個性を持って堂々と生きていく、あるいは演奏していくことを「闊歩(かっぽ)する」と言います。
「跋扈」と「闊歩」は似て非なるもの。ここには厳然たる一線を引かなければなりません。これは私が教育の場で、常に伝え続けていることです。
──「演奏が上手い」だけでは届かない、聞き手や審査員の心に残る演奏とはどういうものでしょうか。
松山
これは先ほどの話にもつながりますが、やはり作品に真摯に向き合い、自我の確立を持ち「闊歩(かっぽ)」している演奏です。楽譜をどれほど深く読み込んでいるかということを含め、迷いなく堂々とした演奏は、我々審査員に対しても大きな説得力を持ちますから。
審査員は演奏される作品のほとんどを熟知しています。どこに何が書かれ、どの音が何分音符で、どのような指示があるのか。それらを把握したうえで評価を下します。加えて、その場の「ホールの響き」を瞬時に耳で捉え、コントロールできているか。つまり、ホール全体を支配する能力があるかどうかを見ているのです。
そうした土台の上で、ふとした瞬間に見せる「即興的な選択」。これが、いい意味で我々を驚かせることがあります。そうした輝きを抜本的・総括的に評価したときに「文句なしに素晴らしい。第1位にふさわしい」という結論に至るのです。
──コンクールにおいて文句なしに「1位」と評価せざるを得ない方には、どのような特徴がありますか。
松山
第1位に選ばれる方というのは、概して次のような要素を兼ね備えています。
- その年代において卓越した技術があること
- 天性の資質としての豊かな音楽性があること
- 同時に、作品に対してどこまでも真摯に向き合っていること
これらすべてを高い次元で調和させ、本番という「やり直しのきかない一回きりの舞台」でホールを支配し、聴き手の精神を掴むことができるか。その総合力が試されているのです。
イタリア・ルネッサンス期の書物『宮廷人(カスティリオーネ)』のなかに、演奏について触れられた一節があります。「デコーロ(技術)」と「スプレッツァトゥーラ(即興性)」この二つのバランスが極めて重要だと書かれています。
これは現代でも全く同じです。自分の修練によって身に付ける技術と、そして本番での即興的な音楽的選択。その両立は欠かせません。ところが、中世の人々はそれだけでは十分ではないと考えていました。
では、もう一つ必要なものは何か。彼らが挙げたのが、天から降りてくる「グラーツィア」(いつ訪れるかわからない特別なもの/恩寵)です。これが立ち現れると、その時間と場所が神格化されます。演奏家と聴衆が一体となり深い感動に包まれる――。そう捉えられていました。
現代に置き換えるなら、限られた時間と場所で交わされる演奏家と聴衆の皆さんのやり取りです。決して意図されることのない「グラーツィア」の降臨、その瞬間、舞台がギリシア語で言うテメノス「神の領域」「神殿」と化すのです。そこまで到達して初めて真に素晴らしい演奏と言えるのだと、中世の人々は考えていたのですね。
そう思うと、現代よりも昔の方が芸術に対する価値観は豊かだったのかもしれません。そうした「かつての豊かな価値観」に立ち返ることも、今の我々には必要なのかもしれません。
──本番でそのような特別な瞬間を迎えるためには、どんな準備や練習が必要なのでしょうか。
松山
準備とは、「計画的・意識的」であると同時に、ときに「恣意的(思うがまま)」であるべきです。まずは計画的に自らを切磋琢磨し、積み上げていく。その先にこそ、先ほどお話しした「スプレッツァトゥーラ(即興性)」が、意図せずとも結果として心の中に現れてくるのです。
人間の意思は脆弱であり、とかく自らに甘い存在です。だからこそ、練習するときには常に自らに厳しく、自らを疑う姿勢が求められます。
例えば、日々の練習でつい速いテンポばかりで弾いてしまい、「こんなものだろう」と流してしまっていませんか?しかし毎日1ミリの誤差があると、10日後には1センチ、100日後には10センチの誤差に広がるんです。そうなってから慌てて楽譜に立ち戻るようでは、またイチからやり直しです。
俗に「親愛なる神は細部に宿る」といいますが(原文:Der liebe Gott steckt im Detail:A.ヴァールブルク)、「もうできるはずだ」「このくらいのテンポでいいや」という甘い誘惑に負けず、自らを疑う気持ちを持って、細部まで徹底的に意識し抜くことが大切です。
ただし、本番では逆に、自らに全幅の信頼を持って演奏に臨まなければなりません。これは「スイッチを切り替える」というような表面的な意味ではありませんよ。自分の演奏に対して「責任」を持つということです。本番はあくまでも練習の延長線上にあります。
演奏するということは、しゃべることと同じ。大人が自分の発言に責任を持つのと同じように、自分の奏でる音の一つひとつに責任を持てるようになることが大切です。
──日々厳しく自分を顧みて練習を重ねることで、自然とそれが土台となり、責任ある演奏が可能になるということでしょうか。
松山
そうです。練習曲集で『グラドゥス・アド・パルナッスム(M.クレメンティ)』というものがあります。「パルナッスム」というのはギリシャの神々の住む山のこと。このタイトルには「パルナッスムへ上る道すがら」という意味があります。
この「パルナッスム山」の頂が、本番だと思ってください。日々の練習はその険しい山道を一歩ずつ登っていく過程であり、最後にようやく頂上へと辿り着く。
ここまでやり抜いて初めて「自らの存在を賭けたパフォーマンス」が可能になります。自分が積み上げてきたものを信じ、すべてを賭けることができるのです。
──より良い演奏のためには、どのように自らの感性や内面を磨くべきですか。
松山
これは私が長年言い続けていることですが、「音楽とは人間理解」にほかなりません。
作曲家を理解するということは、作品を通して作曲家の人間とその人間性・思想を理解することです。例えば、べートーヴェンを弾くなら、今向き合っている作品だけでなく、ほかのあらゆる作品にも目を向け、彼の人生そのものを理解しようと努める。そのプロセスがあって初めて、一曲の理解が深まるのです。
これは、演奏者自身にも同じことが言えます。コンクール審査では、演奏が始まったほんの一瞬の間に、奏者の意識や心の状態が手に取るように伝わってきます。それに続いて、その人の「人となり」が明らかになっていく。ヘルマン・ヴァイルが言うとおり、あまつさえ「真・善・美は同じものの3つの側面にすぎない」のです。つまり、最後に問われるのは演奏者の人間性なんです。
だからこそ、練習の段階から自らの甘えや脆弱な精神と戦い、自分を厳しく律しなければなりません。人間のあらゆる行為は、常に「己との闘争」を孕んでいるものです。
幼い子供は本番であまり緊張しませんが、大人になるにつれてアガりやすくなりますよね。それは、舞台で問われているのが演奏だけではなく、「自分という人間そのもの」であると気づくからなのです。
──入賞は一つの通過点です。結果がどうあれ、生涯を通してピアノと幸せに歩むために、これだけは失わないでほしい「音楽への純粋な情熱」とは、どのようなものだとお考えですか。
松山
まず、「音楽への純粋な情熱」とは「音楽への純粋な愛」にほかなりません。そのうえで、演奏家を目指す方々に対して提言したい。
単なる職人としての演奏家を目指すのではなく、まず芸術家であり、次に音楽家であり、その媒体としての楽器奏者(ピアニスト等)であっていただきたいのです。
世の中には、素晴らしい仕事をする「職人」がいます。パン屋さんや大工さんなど、プロフェッショナルなマイスターの方々です。しかし、彼らが「芸術家」かといえば、私はそうではないと考えます。
なぜなら音楽、美術、文学、哲学といった「芸術」や「思想」には、「人間とは何か」「人間の存在とは何か」「人間の佇まいはどうあるべきか」といった共通の問いがあるからです。
ですから、まずは一人の芸術家として世界に向き合ってください。そのうえで、文学や美術ではなく「音楽」という道を選び、その媒体として「ピアノ」を弾く。この順序が大切なのです。
ピアノだけやっていて、安易に音楽家や芸術家を名乗ることはできないのではないかと私は思いますね。
──日本クラシック音楽コンクールへの参加を検討している方や、音楽を志すすべての方へのメッセージをお願いします。
松山
日本クラシック音楽コンクールの審査は、極めて公平かつ厳正です。
繰り返しになりますが、このコンクールの順位は単に相対的に割り出された結果ではありません。その結果として、私が担当したカテゴリー(大学男子の部)では、今回、最高位が第5位に留まりました。
参加者の皆さんには、結果に一喜一憂することなく、絶えず挑戦し続けていただきたいと思います。厳しい評価を乗り越え、上位入賞者に名を連ねることができたなら、それは皆さんにとって大きな誇りとなり、さらなる高みを目指すための強力な原動力となるはずです。
●2026年2月23日「Klavier-Matinée(松山門下生演奏会)」レイボックホール/小ホール(さいたま市)
●2026年3月16日「ショスタコーヴィッチに寄せて」かつしかシンフォニーヒルズ/アイリスホール(東京都)
●2026年5月8日「アンサンブル・ミルソニカ第1回公演」すみだトリフォニー/小ホール(東京都)
インタビューを終えて──編集後記
インタビューの途中、ふと先生の背後に目を向けると、壁一面を埋め尽くす膨大な書籍に圧倒されました。音楽にとどまらず、美術、文学、哲学——その知の蓄積こそが、松山先生の人間性と音楽性を支える土台なのだと感じられます。本棚の佇まいからは、音楽に向き合い続け、人生を捧げてきた時間が静かににじみ出ていました。
「まじめに答えようとすると、つい説明が長くなってしまいました」取材後にいただいたこの言葉からも、先生の誠実なお人柄がうかがえます。言葉を尽くすのは、音楽や相手を軽んじたくないという想いの表れ。その真摯な姿勢が、厳格な言葉の奥にある温かさとして伝わってきました。
日々の研鑽で自らを律し、本番では自らの存在を賭けて舞台に立つ。
先生が示してくださったこの道筋は、コンクールを越え、芸術へ向かうための「魂の在り方」そのものです。ピアノと共に歩むすべての人にとって、迷ったときに立ち返れる揺るぎない道しるべとなることでしょう。