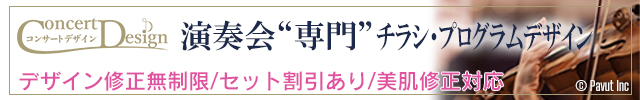全日本ジュニアクラシック音楽コンクールは、2001年に第1回を開催し、本年2025年に第50回という節目を迎える。24年の歩みを重ねた今も、若い演奏家の挑戦と成長を支える舞台として、全国規模の予選体制や自由曲制度、全員への講評などの仕組みを磨き続けてきた。
本特集は、審査員・入賞者への取材に基づき、審査の「評価軸」や近年の演奏トレンド、挑戦者のリアルな成長ストーリーを描いている。次の本番に直結する実践的なヒントを、現場の声とともに凝縮してお届けする。
取材・文:音楽コンクールガイド編集部
国内外の音楽コンクール情報を紹介する専門サイトを運営。「見やすい、探しやすい、わかりやすい」をコンセプトに、コンクールに関わる全ての方に、有益な情報をお届けすることを志している。
<取材協力者>
審査員:太田 幸子(おおた さちこ)
一般社団法人東京国際芸術協会 会長、東邦音楽大学 特任教授。全日本ジュニアクラシック音楽コンクール審査歴15年以上。
入賞者:中村 僚太(なかむら りょうた)
3歳よりヴァイオリンを始める。A.グリュミオー国際ヴァイオリン・コンクール第1位、全日本ジュニアクラシック音楽コンクール第1位、日本演奏家コンクール第1位・準グランプリなど受賞多数。野口千代光、渡辺玲子に師事。東京藝大附属高校を経て東京藝術大学に進学。
同コンクールでの第1位入賞歴: 第49回・第46回(ヴァイオリン)/第38回・第32回・第30回・第27回(弦楽器)
評価の軸と舞台裏 ── 審査員 太田幸子先生の視点
長年「全日本ジュニアクラシック音楽コンクール」の審査に携わる太田幸子先生は、評価の物差しが一つではないことを静かに示してくれる。技巧、音楽性、構成力という基本軸に加え、作曲家が作品の内側に宿した“音色”をどれだけ引き出せているか──その一点が演奏の真価をそっと押し上げる。譜面の正確さを土台に、音色で意図を語り、音楽の核を立ち上げることが大切なのだという。
また、「近年のステージには変化がある」と太田先生は語る。キッズから大学生まで技巧的な選曲が増え、指のコントロールは全体に底上げされた印象だ。一方で、映像プラットフォームの普及により『まず音楽を理解してから練習する』流れが広がり、冒頭からテンポ感と歌心で聴き手を引き込む演奏が目立つ。だからこそ、最初の数小節が勝負どころである。呼吸の置き方、間の取り方、響きの立ち上がりに、その人の音楽観が自然にあらわれる。
とはいえ、舞台は生身である。完璧に整えたはずの暗譜がふと途切れ、音が止まる瞬間もあったという。舞台は厳しい。しかし、厳しさの先には必ず学びがあり、挑戦した者だけが手にできる確かな“成長”があるのだ。
挑戦と成長の物語 ── 中村僚太さんの軌跡
参加者の視点からこのコンクールを見渡すと、挑戦の積み重ねがそのまま成長の軌跡になっていることに気がつく。中村僚太さん(Vn)は、全日本ジュニアクラシック音楽コンクールで計6回の第1位に輝いてきた入賞常連である。初出場は小学校低学年。母が見つけてくれたこの舞台で、毎回「今年はどこまで行けるか」を自分に問いながら臨んだという。ライバルの演奏からは良い刺激を受け、結果は「できている」という手応えに、厳しい講評は次の成長の土台になる。参加者全員に講評が届く点も、このコンクールならではの魅力である。
練習の柱は“長さ”ではなく“質”だという。「ダラダラ続けない。やるべき課題を見極め、限られた時間でやり切る」。学業やほかの楽しみと両立するための工夫が、モチベーションを保つ支えになったと中村さんは話してくれた。その積み重ねが心の余裕につながり、いまでは「音楽をいろんな人に届けたい。どうしたら聴き手に良い音楽を届けられるか」を考えて舞台に立っているという。
とはいえ、ずっと順風満帆だったわけではないようだ。小中学生のころには、意欲が上がらず「やめたい」と家族に打ち明けた時期もあったとのこと。それでも母の励ましと、舞台でつかんだ手応えが背中を押し続けたという。「あのときやめなくて本当に良かった」。ヴァイオリンを続けてきたからこそ出会えた仲間や師、数々の経験が、いまの自分を形づくっていると中村さんは語る。
このコンクールが“挑戦しやすい場であることも、成長を後押ししている。年2回の開催に加え、全国各地で予選が行われるため参加しやすい。さらに自由曲で挑める点も大きいという。
選曲は「いま取り組んでいる課題」や前回からの再挑戦を選ぶことが多く、実際に一度賞を逃した曲で次の回に再挑戦して受賞した経験もある。何度でも挑める環境が、努力の方向を照らし、上達の線を着実に太くしていくのである。
副賞と支援制度
全日本ジュニアクラシック音楽コンクールには、参加者のキャリアを次の段階へ押し上げる導線がいくつも用意されている。
入賞者には海外マスタークラスへのアクセスが開かれており、学費免除の推薦枠が設けられているのが心強い。対象は、ウィーン国立音楽大学、ドイツ国立シュトゥットガルト音楽大学、スイス国立チューリッヒ芸術大学の教授によるクラスのほか、ヨーロッパ国際マスタークラスなど、多彩な選択肢である。学内外の第一線に触れられる機会は、視野を広げ、次のステップを具体化する足場となるはずだ。
また、全国大会の入賞・入選者には、東京・サントリーホール ブルーローズでの表彰式・入賞者披露演奏会に出演する機会が与えられる。さらに、東京国際芸術協会管弦楽団との協奏曲共演の場が用意されており、特に高校生・大学生にとっては、実演家としての自覚と経験値を一気に高める貴重な機会となる。大舞台での一回の成功体験が、その後の挑戦を後押しすることは少なくない。
加えて、本コンクールは奏者だけでなく指導者にも光を当てている。所定の基準を満たした指導者に授与される「優秀指導者賞」は、日々の教育現場を支える努力に確かな評価軸を与えるものである。指導者の士気が高まれば、学びの現場全体の質も自然と底上げされる。演奏者と指導者の双方を支える設計が、コンクールの価値を静かに、しかし着実に押し広げていると言える。
コンクールの舞台から世界の舞台へ
コンクール入賞をきっかけに音大の演奏家コースでの躍進、大学院進学の決定、バレエ団でのトップピアニストや指揮者としての活躍など、次の扉を開いた例が数多く報告されている。第50回を迎える全日本ジュニアクラシック音楽コンクールについて、太田先生はこう語る。
「現在はエントリー数も増え、コンクールのレベルも大変高くなりました。先生方からも『公平・公正で温かいコンクール』との評価を頂戴しています。今後益々、ここから日本を代表する音楽家・教育者を輩出していきたいです。」
挑戦は結果だけでなく、進学や活動の選択肢を広げる“経験値”として着実に積み上がっていく。
一方、入賞常連として走り続けた中村さんは、留学を視野に、ソロ・室内楽・指導のいずれにも開かれた将来像を描く。「まだ一つに決めない」。その柔軟さは、多様な演奏現場で“音を届ける”という原点を見失わないための選択でもあるように感じた。
舞台はあなたの挑戦を待っている
本記事を読んでくれたあなたへ、今回インタビューに答えてくれたお二方からのメッセージをお届けしたい。
太田先生
「初めての出場でいきなり輝かしい賞を目指すのではなく、そこに至るまでのプロセスが大切です。回を重ねることで、必ず上達は見られます。ご家庭でも、どうか温かく見守っていただければ幸いです。」
中村さん
「コンクールとはいえ、音楽を楽しむことが一番。つまらない状態でやると音楽もつまらなくなってしまうので、モチベーションを維持しながら、無理せずやってみましょう。」
このコンクールが示すのは、「初回から頂点」よりも挑戦のプロセスこそが上達を連れてくるという事実だ。
審査員は、努力の跡と音楽の理解を確かに見ている。完璧よりも前進を。積み重ねた一音一音が成長へと導き、やがて未来への大きな響きとなるだろう。
最後は、第50回 全日本ジュニアクラシック音楽コンクール代表理事・片山氏の言葉で、未来への余韻を残して本特集を結ぶ。
第50回全日本ジュニアクラシック音楽コンクール 代表理事御挨拶
全日本ジュニアクラシック音楽コンクールが第50回の節目を迎えることができましたこと心より御礼申し上げます。
とりわけ全日本ジュニアクラシック音楽コンクールにこれまで御参加いただきましたみなさま並びに、参加者を支えていただいたご家族ご友人のみなさま、出演者を御指導いただいた先生方に感謝申し上げます。
第1回開催から今日まで、多くのみなさまに御参加いただきましたが、変わらず継続してきた3つの項目がございます。それは予選、本選会場の選択が可能で全国各地様々なホールで演奏できること、審査員による客観的視点から指標を講評という形で受け取ることができること、全自由曲制により日々のレッスンで学習した曲をコンクール演奏曲として選曲できることです。
これまでのレッスンで学んでいただいた成果をコンクールという舞台で演奏し、さまざまなホールで音の響きを体感いただくことができます。こうして得られた貴重な知見を日々のレッスンに活かしていただきたいと願っております。
これからもみなさまにとって全日本ジュニアクラシック音楽コンクールがひとつの指標になるよう、次の50年先に向けて努力してまいります。引き続き本コンクールをどうぞよろしくお願い申し上げます。
一般社団法人東京国際芸術協会
代表理事 片山孝調

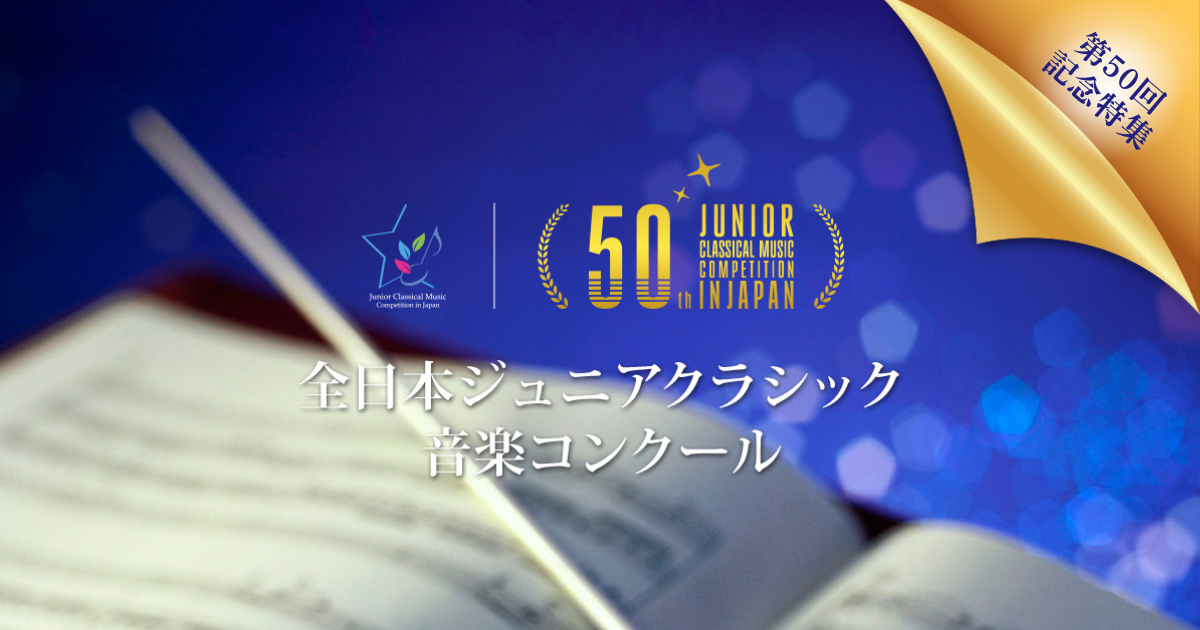






-522x294.jpg)
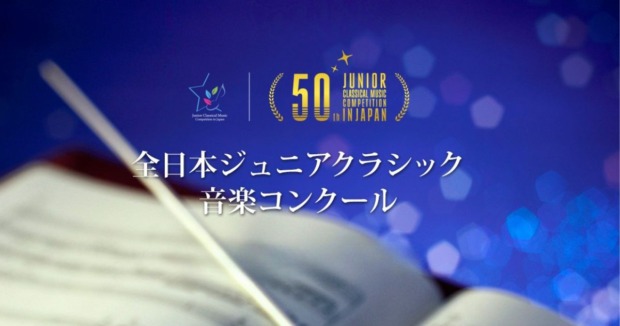
-結果-620x326.jpg)