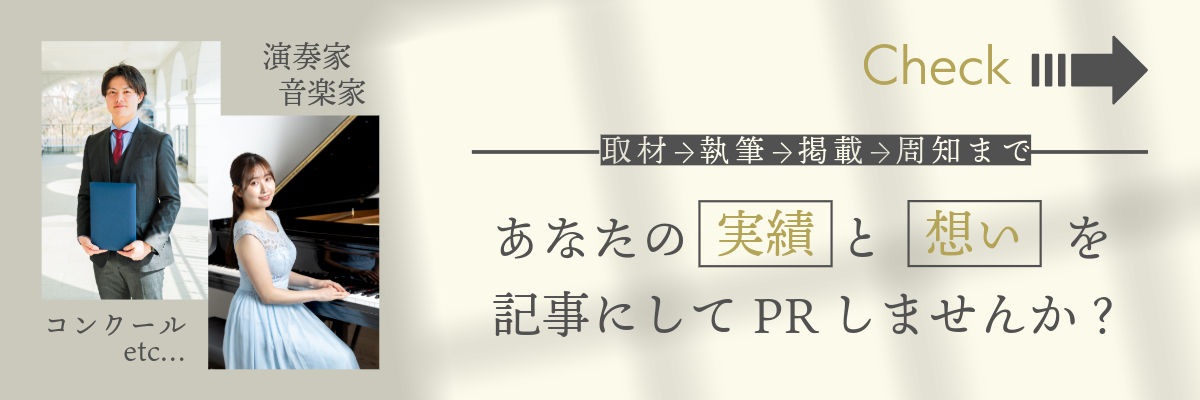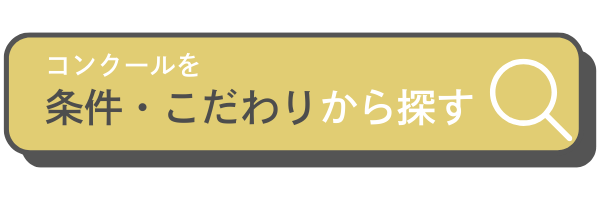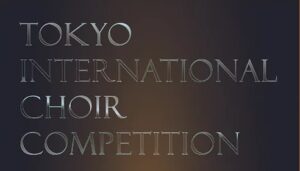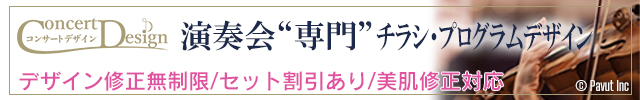清泉女学院で理科教諭・教頭を務め、現在は音楽部特別顧問として合唱教育に携わっている佐藤美紀子さん。横浜国立大学で植物生態学を学び、幼い頃から合唱に親しみ、20歳からは故・関屋晋氏に指揮を師事。国内外の舞台での歩みは「倍音が満ちるハーモニーで心を動かす」という思いへと育ち、Nコン金賞・内閣総理大臣賞、欧州主要国際コンクールのグランプリへとつながります。
そして今回、東京国際合唱コンクールでは総合グランプリを受賞。佐藤さんには“清泉サウンド”の今とこれからを、部長・練習責任者のお二人には、日々の練習設計やチームづくり、「聴く人に幸せの光を届ける」という合唱の使命について伺いました。
取材・文|編集部
自分にピッタリな音楽コンクールが見つかる!国内外の音楽コンクール情報や結果まとめをわかりやすくご紹介し、次世代の音楽家や音楽ファンの皆様に寄り添います。
プロフィール
佐藤美紀子(Mikiko Sato)
清泉女学院音楽部特別顧問
横浜国立大学教育学部で植物生態学を専攻。卒業後、清泉女学院中学高等学校に理科教諭として着任し、長年にわたり生物教育と自然保護教育に尽力した。その後、教頭を経て、現在は音楽部特別顧問を務める。
幼少の頃からピアノを習い、合唱団のメンバーとして音楽に親しむ。20歳頃より、故・関屋晋氏に指揮法を師事。晋友会合唱団のメンバーとして、世界の著名なオーケストラや指揮者のステージに立ち、海外公演にも参加して技術を磨いてきた。
趣味・特技
トレッキング(アマゾン、キリマンジャロ、ヒマラヤその他多数)、スキー
写真、茶道、華道(師範免許)
指導団体と指導歴
1998年より清泉女学院中学高等学校 音楽部
2009年より清泉女学院卒業生による合唱団 “La Pura Fuente”
2023年より保護者合唱団 “La Fuente Serena”
年間の主な活動として、上記団体での各種コンクール出場や公演活動を実施。
国内での指導実績
全日本合唱コンクール全国大会において、中学・高校・一般の各部門で31回金賞受賞、うち9回を文部科学大臣賞受賞に導く。
NHK全国学校音楽コンクール全国大会では、2019年と2024年に金賞を受賞し、内閣総理大臣賞の受賞に貢献。
声楽アンサンブルコンテスト全国大会連続金賞受賞。
国外での受賞実績
2010年 第49回セギッツイ国際合唱コンクール:2部門優勝、グランプリ選総合第2位
2013年 European Choir Games Graz:3部門優勝、グランプリ選総合第1位
2015年 バードイシュル国際合唱コンクール:3部門優勝、グランプリ選総合第1位、優秀指揮者賞
2018年 ラトヴィア開催 “Riga Sings”:グランプリ選総合第1位
今年度の主な受賞・成果
3月 声楽アンサンブルコンテスト全国大会:金賞
4月 ブダペスト国際合唱コンクール:3部門金賞、ユース部門第1位
7月 東京国際合唱コンクール:2部門第1位、グランプリ選 総合第1位
10月 全日本合唱コンクール全国大会 金賞 富山県教育委員会教育委員会長賞
音楽活動
指揮者として、鈴木輝昭作曲のCD「地球歳事記による作品集」、「譚詩章」、「合唱の地平VII」の録音に参加
受賞・役職・社会貢献活動
神奈川県教育功労者表彰、鎌倉市文化功労者表彰、神奈川県部活顧問賞などを受賞。
現在、神奈川県合唱連盟 副理事長、日本指揮者協会 会員を務める。
ユースへの合唱活動の普及のための催事、およびヨーロッパの現代宗教音楽の普及に積極的に取り組む。
第7回東京国際合唱コンクールを終えて
ーー今回のコンクールに挑戦された狙い・位置づけ(教育的目標や部の成長目標)を教えてください。
佐藤
私たちは今回、東京国際合唱コンクールへ初めての参加となります。COVID-19パンデミックの影響で3年に1度行っていた海外遠征を中断していましたが、6年ぶりに4月のブダペスト国際合唱コンクールに出場し、約20曲という多彩なプログラムに挑みました。その成果をさらに深めるべく、今年はNHK全国学校音楽コンクールの出場を見送り、清泉サウンドを美しく響かせることができる音響効果の高いホールで行われる本コンクールに出場することにしました。
そもそも国際合唱コンクールは、ルネサンスからロマン派、そして現代音楽まで幅広いレパートリーに加え、衣装や楽器、珍しい民族音楽など創意工夫に満ちたパフォーマンスが魅力です。演奏者も観客も、多様な音楽を肩の力を抜いて心から楽しむことができ、フレンドシップコンサートやオープニングの集いでは各国の合唱団との交流を深める機会にも恵まれます。欧州特有の乾燥した空気のもと、教会の響きが螺旋状に立ち上る空間に身を置き、合唱の原点を体感できることも貴重な機会だと考えています。
ーープログラムと選曲方針について教えてください。
佐藤
国際合唱コンクールの規定により、ルネサンス期から現代音楽までの幅広い様式から選択すること、世界の皆様が共通して理解しやすいラテン語の宗教曲、あるいは外国語の曲(今回はスペイン語とラテン語)を選ぶこと、日本文化を紹介できる日本民謡の編曲作品を取り入れること、視覚的にも楽しめるコレオグラフィー付きの演奏を行うこと、さらに12声部にわたる難度の高い曲を含めること――以上の視点で選曲しています。
練習の過程で数多くの言語に触れることで、その国の文化や宗教への理解が進み、自国の文化への関心も深まり、生徒にグローバルな視野の広がりをもたらします。過去の大会では、ドイツ語、フランス語、ラテン語、英語、マジャール語など、6か国語を練習したこともあります。
ーー準備期間の取り組みについて教えてください。
佐藤
過去6回の海外遠征、そして国内の数々のコンクールへの参加に際し、保護者の皆様からは温かな応援とご支援をいただいております。また、学校生徒会、保護者の会、卒業生の皆様からも多大なご援助とご協力を賜っております。27年前にコンクール活動を始めた頃、そして18年前に初めて海外遠征を実施した時と比べますと、学校のサポートや周囲の皆様のご協力の在り方は大きく変化してきました。
どの大会・ステージ・コンクールにつきましても、私たちの取り組みは一貫しています。生徒の活動期間は限られているため個人の最終目標があると思いますが、指揮者であり顧問である私にとっては、「清泉サウンド」を育てる長い道のりの通過点に過ぎません。
日々の基礎づくりとして、①筋トレ、②脱力(こんにゃく体操)、③脳トレ、④耳トレ、⑤発声の基礎練習を、さまざまなパターンで繰り返し行います。朝の短時間練習でも組み合わせを変えながら取り組んでいます。音取りはパート練習で進め、パートリーダーが中心となって運営し、指揮者不在の際は、練習責任者が中心となって全体をまとめることもあります。コロナ禍以降の変化としては、オンラインでのパート練習(現在は減少)や、課題提出に基づく個人レッスンの方法が加わりました。本番が近づけば、練習のたびに録音を行い、調整を重ねます。
ーー本番当日の様子はいかがでしたか?
佐藤
この大会だからといって、特別なことはありません。先にも申し上げましたが、少人数でも倍音が出やすいホールであったことは、大変助けになりました。酷暑のなか、夏季講座終了後の夕方に鎌倉から会場まで約1時間半を移動し、到着後すぐにリハーサルと本番という、通常より厳しい条件でしたので、宿泊している団体に比べてコンディションづくりは大変だったと思います。2日目は室内楽曲部門に出演後、グランプリ選出に出場された皆様との交流会もあり、帰宅は深夜近くになりました。そして3日目のグランプリ選出本番へ――生徒たちの気力が3日間持続したことは立派でした。
夜の交流会についてですが、中国の団体が国旗と呼称をめぐる問題を抱え、グランプリ選出の辞退を申し出る事態がありました。折り紙を折るなど積極的に国際交流を行っていた最中、中国のジュニア団体2団体が突然会場を退場し、ロビーで涙をこぼす姿も見受けられました。生徒たちは、そこに国際情勢の緊張を感じ取ったようです。主催者と各国・各団体の懸命な説得と交渉の結果、翌日のグランプリ選出では参加国の国旗が全て下ろされ、国名のアナウンスも変更されました。こうして、予定していたすべての合唱団が集い、無事に表彰式を迎えることができました。
ーー同コンクールを目指す学校・後輩たちへメッセージをお願いします。
佐藤
国際合唱コンクール全てに共通して言えることですが、日頃から演奏レパートリーを広げること、そして表現力を磨くことが大切だと思います。
ーー今後の目標などお聞かせください。
佐藤
倍音による「天使の声」と呼ばれる響きにヨーロッパの教会で出会った日から、ハーモニーの響きだけで心を動かせる演奏を目指してきました。パート内のピッチがそろった純度の高い音を追求し、「清泉サウンド」を築くための基礎練習を17年前に据えました。それ以降、倍音の響きはホールを満たし、表現力の深まりとともに多様な音楽への挑戦を可能にしています。
生徒に提示している目標は、次の三点です。
1.未来に向かう凛とした姿勢
2.隣の人の息遣いが聞こえるような透明な声
3.聴いていただく方々に「幸せの光」を届ける温かな表現
将来、生徒が困難にぶつかった時の心の指針として思い出せるような楽曲を、仲間と心を合わせて歌うこと、そしてかけがえのない友人をつくることが、生徒たちにとっての最大の目標だと考えています。表現者として大切なのは、自己満足で歌うのではなく、聴衆に「幸せの光」を届けることです。
また本校はカトリック校ですので、ヨーロッパの現代宗教曲を日本に普及させること、そして本校の宗教曲をヨーロッパに広めることもミッションと考えています。私たちは決して大きな力を持つわけではありませんが、世界中で悲しみや苦しみを抱える方々の重荷を共有し、その状況と理由を理解し、世界平和の実現に向けて祈り、歌う姿勢を忘れずに過ごしていきたいと思います。
近年は、どの大会におきましても審査員から「ピッチがそろった鮮やかなハーモニーと技術力が素晴らしい。Mysterious!! Marvelous!!(神秘的‼素晴らしい‼)」と評価していただけるようになりました。これは、この17年にわたる基礎トレーニングの成果だと感じています。また、聴衆の皆様から「情景が浮かび感激した」というお声を頂戴し、合唱を通じて学校のミッションである「喜びと光」を実現できたことに、深く感謝しております。
清泉女学院高等学校音楽部 部長×練習責任者インタビュー
①総合グランプリのご受賞おめでとうございます!受賞の喜びと、特に心に残った瞬間を教えてください。
平山(部長)
総合グランプリをいただけたことは、素直にとても嬉しいです。全員が大変喜んでいました。もともと「グランプリの舞台で歌いたい」という思いを胸に、部員一同、学校合唱部部門と室内合唱部門の2部門に出場しました。1日目の学校合唱部部門の結果によりグランプリ出場が決まったときは、少しでも多く私たちの歌を聴いていただける機会をいただけたことに、大きな喜びを感じました。そして、グランプリ団体の発表で「清泉女学院高等学校」と呼ばれた瞬間は、跳ね上がるように驚きました。
特に心に残ったのは、もちろんグランプリ発表の瞬間ですが、演奏中に見えたお客さまの笑顔、そしてホールの残響です。東京国際合唱コンクールでは、曲間の拍手が手を挙げて“ひらひら”と振るスタイルだったのですが、多くの“ひらひら”が見えて、とても印象的でした。加えて、非常に響きの良いホールでしたので、全て歌い切ったあとの残響が美しく、深く心に残っています。
聴いてくださった皆様にとっても、心に残る演奏になっていれば幸いです。
②部長として心がけたことを教えてください。
平山(部長)
私が部長として心がけたのは、「全員で作り上げる合唱」です。合唱の最大の魅力は、やはり「たくさんの声が重なることで生まれる音色の美しさ」だと思っています。一人ひとりの声が合わさることで生まれる美しい響き、チームで目標を達成する喜び、そして共に音楽を作る過程で深まる絆。だからこそ、部員全員が気持ちよく部活動に取り組めるよう、部の雰囲気づくりや本番前の声掛けを意識しました。練習の際も、態度やモチベーションを高めてもらうために、こまめに声をかけるようにしました。
部を引っ張る立場である高2とは多くの話し合いを重ね、方針を決めたことで団結力が高まり、その姿勢が高1にも伝わりました。結果として、21人という少人数だからこその強い絆が生まれたと思います。部員同士が互いに励まし合い、課題を共有しながら解決するチームワークが育まれ、仲間と共に音楽を創り上げる喜びを、より深く実感できたと感じています。
これからも「合唱が楽しい!」と思える雰囲気づくりを心がけていきます。
③当日のステージで「伝えたかったこと」/お客さま・審査員に届いて欲しかったことを教えてください。
吉村(練習責任者)
各部門で歌う4曲は、曲調が全く異なっていました。最初の一音で曲のイメージが決まりますので、各曲の冒頭で意識を切り替えられるようにしました。通常の日本のコンクールとは異なり、海外からの団体や審査員の先生が多いことも、国際コンクールならではの特徴です。私たちが今年4月にハンガリーで行われた国際コンクールに出場した際も、海外の団体が歌う曲の歌詞の意味は分からなくても、複雑な和音や音楽の激しさを通して、その曲の雰囲気を十分に感じ取ることができました。
海外の方に日本語の歌詞の意味を直接理解していただくのは難しいですが、ハンガリーの舞台での経験を踏まえ、言葉の抑揚や揺らぎによって感情を伝えることを意識しました。例えば「Meciendo」では、母が子に注ぐ愛から世界平和へとつながる壮大な世界観を、多声による和音やグリッサンドが生み出す揺らぎから感じ取っていただけるよう工夫しました。
④一番苦労した点と、それを乗り越えた“合言葉”や工夫があれば教えてください。
吉村(練習責任者)
21名という少人数のため、一人ひとりの声の重要性を改めて実感しました。迫力を出すことが難しい一方で、個々の声が目立ってしまうことも課題でした。パート練習では互いの声をよく聴き合い、音程やピッチが揃っているかを確認しました。「合わせ練」では、各パート1名ずつで構成したグループで、和音の“縦のライン”が綺麗にはまっているかを精査しました。さらに全体練習では、パートバランスや和音の精度など、合唱全体のバランスを聴くことを意識しました。
例えば、学校合唱部部門の課題曲「spring」の終盤に登場するロングトーンでは、春の暖かさを感じさせる柔らかな和音へ、綺麗に変化させられるよう工夫しました。「グランプリの舞台で歌いたい」という思いを胸に、部員一同、力を尽くしました。
⑤応援してくれた方へメッセージをお願いします。
平山(部長)
日頃から熱いご指導をくださる佐藤先生をはじめ、顧問の先生方、そして「大会頑張れ!」と応援してくれるクラスメイトのみんな、陰で支えてくださった保護者の皆さん、先輩方に心より感謝申し上げます。先生方の心のこもったご指導、歴代の先輩方から受け継いだ「清泉サウンド」とそこに込められた熱い思い、そして学校全体からの応援が大きな力となり、私たちは本番の舞台で全力を尽くすことができました。
皆様のおかげで一つ一つのステージを乗り越え、私たちの歌を届けられたことを誇りに思います。心が痛む紛争のニュースが絶えないこの世の中が、少しでも平和に近づくことを願い、聴いてくださる方々に「幸せの光」を届けられる歌を、これからも歌い続けていきたいと思います。
⑥これから挑戦したいことはどんなものがありますか?
吉村(練習責任者)
私たち高校2年生は、引退まであと一年を切りましたが、今後さらに透明感のある壮大なハーモニーで、聴いてくださる方の心に響く音楽を目指していきます。今年4月、国際コンクールでハンガリーを訪れた際には、現地の教会でも歌わせていただき、吹き抜けの天井に和音の残響が吸い込まれるような感覚が忘れられません。来年1月には、鎌倉・雪の下教会で歌わせていただく予定です。
天井を感じるような硬い音、浅い母音、不安定な和音など、課題は少なくありません。教会で“天使のような美しい声”を響かせるため、部員一同、さらに豊かな声を追求していきたいと思います。私自身、先輩方の背中を見て「自分もあんな先輩になりたい」という憧れを抱きながら、ここまで歌ってきました。部員それぞれが持つ個性豊かな声を揃えることは難しい反面、絆を深め合い、誰かを幸せにできるという素晴らしさがあります。先輩から学んだ伝統ある「清泉サウンド」を、後輩へと確かに引き継いでいきたいです。
2026年
1月12日(月)JLMM主催 チャリティーコンサート(鎌倉市・雪の下教会)
2月21日(土)第40回 音楽部ミュージカル公演(清泉女学院 講堂)
5月14日(木)~16日(土)昌原フェスティバル 招待演奏(Seisen Youth Choir として参加)
6月12日(金)~14日(日)World Choral Championship 2026(ポーランド・クラクフ)
インタビューを終えて──編集後記
今回のお話から、「清泉サウンド」は技術のうまさだけでなく、日々の積み重ねと先生方の想いの中で育まれている響きだと実感しました。21名という編成でも和音の純度や倍音を丁寧に磨き、一人ひとりが互いに耳を寄せ合って音楽を束ねている——その姿がとても印象的でした。
ハンガリーでの教会の残響や各国との交流といった海外経験を、舞台へ自然に還元している点も素敵です。「うまく歌う」を越え、言葉の壁を超えて気持ちを届けようとする姿勢に、国際舞台で得た視点を感じました。
ひとつひとつの本番が次へとつながる大切な機会なのだと思います。グランプリはその歩みの結果であり、未来へのバトンですね。これからの“清泉サウンド”がどんな輝きを見せてくれるのか、とても楽しみです。
お時間をいただき、ありがとうございました。皆様のさらなるご活躍を心から応援しています。
第7回東京国際合唱コンクールの概要については下記をご覧ください。
第7回東京国際合唱コンクールの結果については下記をご覧ください。