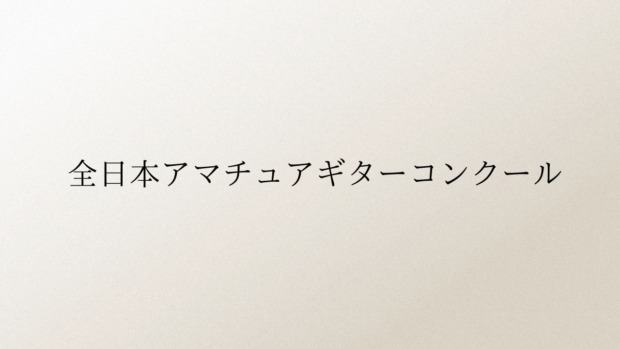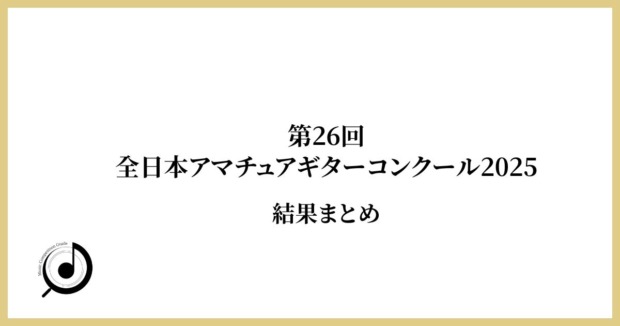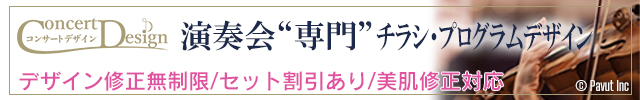フェリス女学院大学、桐朋学園芸術短期大学、村治昇ギター早期才能教育教室で教え、(公社)日本ギター連盟の理事も務めるクラシック・ギタリスト、坪川真理子さん。5歳でピアノ、12歳でギターに出会い、東京外国語大学卒業後はスペイン政府奨学生として渡西。マドリッド中級音楽院「テレサ・ベルガンサ」を首席で修了し、「ホアキン・ロドリーゴ賞」を受賞。マドリッド王立上級音楽院ギター科を日本人女性として初めて修了(優秀賞)。現在は東京を拠点に演奏・教育・スペイン語翻訳に携わり、全日本アマチュアギターコンクールの審査は18年にわたります。今回は「伝わる演奏」、練習の工夫、そしてコンクールが与える前向きな力についてお話を伺いました。
取材・文|編集部
自分にピッタリな音楽コンクールが見つかる!国内外の音楽コンクール情報や結果まとめをわかりやすくご紹介し、次世代の音楽家や音楽ファンの皆様に寄り添います。
プロフィール
坪川 真理子(Mariko Tsubokawa)
Instagram facebook YouTube
東京都出身・在住
フェリス女学院大学、桐朋学園芸術短期大学、村治昇ギター早期才能教育教室講師
(公社)日本ギター連盟理事
東京を拠点に演奏・教授活動 / スペイン語翻訳業務にも従事
5歳で自らの意思によりピアノを始め、12歳で母の影響からクラシックギターにも出会い、ピアノと並行して研鑽を重ねる。東京外国語大学を卒業後、スペイン政府の奨学生として渡西。マドリッド中級音楽院「テレサ・ベルガンサ」を首席で修了し、さらにマドリッド王立上級音楽院ギター科を日本人女性として初めて卒業。
故・加藤英之、今野有二、J.アリサ、C.ロス、G.エスタレージャス各氏に師事。
趣味・特技
読書と手芸を好む。近ごろは多忙のため手芸はお休み中。読書は主に電車で、つい歩き読みしてしまうほど物語に没頭するタイプ。兄は小説家の結城充考。
受賞歴・演奏活動歴(抜粋)
サンティアゴ・デ・コンポステラ国際スペイン音楽講習会「ホアキン・ロドリーゴ賞」
マドリッド王立上級音楽院「優秀賞(卒業時)」
主なリリース
ソロCD『スペイン幻想』『ラテン幻想』(Bishop Records)— 多方面で高評価
アルポリール・ギタートリオ(新井伴典・金庸太と結成)『HarpoRhythm(アルポリズム)』(現代ギター社)
スペイン留学同期ギタリスト5名による「スペインギターフェスタ」『わたしたちのスペイン』(SGF)
ソロ新譜『佐藤弘和編曲作品集 ~鳥の詩(うた)~』(Woodnote studio)雑誌『レコード藝術』特選盤に選出
ーー全日本アマチュアギターコンクールで審査を担当されたご感想と、全体としての印象をお聞かせください。
坪川
全日本アマチュアギターコンクールの審査を担当して18年ほどになります。他にもいくつかのコンクールで審査に携わっておりますが、最も長く関わっているのが当コンクールです。今回は大阪のコンクールと日程が重なった影響で関西からの出場者は少なめでしたが、予選には北海道から沖縄まで全国各地よりご参加いただきました。
本選では、審査員7名のうち4名が佐藤さんに1位を付け、圧倒的な優勝となりました。2位とは7点差、さらにその1点差で3位が続きました。出場者の内訳は20代1名、40代1名、50代4名、60代2名、70代2名。初出場の20代・佐藤さんが頂点に立ちました。過去の優勝者はもう少し上の世代が多い傾向にあります。今回も熱い演奏が相次ぎ、採点に悩む場面もありましたが、終わってみれば佐藤さんの圧勝。音の美しさに加え、ダイナミクスの組み立てや音楽の流れが秀逸でした。
ーー全日本アマチュアギターコンクールの特徴や強みは、どのような点にあるとお考えですか。
坪川
国内に数あるコンクールの中でも人気が高く、参加者が多いのが特徴です。響きが素晴らしいホールで演奏できることや、録音予選では不合格だった方々に、ステージ予選では50人全員に各審査員からの直筆コメントをお渡ししていることも、ご好評をいただいているようです。
審査員としては、特にステージ予選で数分の間にコメントを書くのは大変ですが、皆さまに喜んでいただけることを励みに、できるだけ良い点と今後の参考になるアドバイスの両方を書くよう心がけています。
また、課題曲の版を指定しているため、読譜ミスには厳格に対応します(対象は音符・リズムの誤りで、運指やスラーは自由)。そのため、本選に何度も出場している方でも、録音予選で不合格となることは少なくありません。
当コンクールは「多くの人にチャンスを与えたい」という信念のもと、「他のコンクールで3位以内に入賞した人は参加資格なし」、また「学生不可」としており、初めて入賞できる喜びを多くの方に味わっていただけていると思います。シニア層の参加が多いのも特徴ですが、シニア限定ではなく学生でなければ若者も挑戦できるという点は強みかもしれません。
ーー審査の際に特に重視された点は何でしょうか。
坪川
個人的には、どのコンクールでも技術点と芸術点を各50点、計100点満点で付けています。当コンクールの本選は順位で付けるため、100点満点から換算して提出します。
技術点はテクニック、リズムの安定感、音質、音量、レガート、メロディと伴奏のバランス、消音など、芸術点はフレージング、歌い回し、和声感、時代の様式感、個性などを含みます。細かなミスよりも大きな音楽の流れを見るようにしています。他のコンクールに比べると曲の難易度はそれほど重視しませんが、完成度が同程度なら難曲のほうが評価は高くなります。
音質は芸術点に含める方もいると思いますが、良い音を出すことは一つのテクニックだと考えているので、私は技術点として評価しています。
また、技術的にしっかり弾けていても「音楽的に好きではない」という理由で極端に低い点を付ける審査員を、他のコンクールで見かけることがあります。私は、音楽のコンクールもフィギュアスケートのように技術点と芸術点を分けて審査すべきだと考えています。人間が審査する以上、最終的に好みが影響することはあるかもしれませんが、たとえ好みでないタイプでも技術的な部分はしっかり評価されるべきだと思います。
ーー「演奏が上手い」だけでは届かない、聴き手や審査員の心に残る演奏とはどのようなものでしょうか。
坪川
やはり音楽的要素が大きいですね。ダイナミクスも大事です。どんなに速弾きでノーミスの演奏をしても、音がずっと小さいとか、逆にフォルテ一辺倒では心を動かされません。クレッシェンドやデクレッシェンドは、自分ではやっているつもりでも、かなり大げさにやらないと伝わらないものです。
特にクラシックギターは音量が小さい楽器なので、いくらよく鳴る楽器を使っても最大音量には限りがあります。弱い方向にダイナミクスを広げることはとても大事ですし、当コンクールを開催している三鷹市芸術文化センター「風のホール」は音響が素晴らしいので、ピアニッシモを効果的に使えます。ただ、弱い音にも響きが必要で、しっかりしたタッチでないとよく聴こえずに終わってしまうこともあります。
また、ギターは指で直接弦を弾いて音を出すため、音質の良し悪しに大きな差が出る楽器です。ビブラートも大切ですね。同じ演奏でも、細い音よりもビブラートのかかった美音のほうが、10倍感動させられると思います。
ーー本番で実力を発揮するために、演奏家が日々意識すべきことや、取り組んでほしい練習方法はありますか。
坪川
コンクール曲については、とにかく苦手な箇所をゆっくり部分練習することです。やみくもに繰り返すのではなく、まず運指を見直し、届きにくい音型に備えて指の準備をしておくなど、弾けない原因を考える必要があります。
本番で一番惜しいのは度忘れです。確実な暗譜がとても大切だと思います。普段から、間違えても弾き直さない習慣、度忘れしても止まらずに進む習慣をつけること。次の段落へ飛んでも良いので、先へ進める練習を勧めています。通し練習の際はとにかく弾き通し、後から間違えた部分や忘れた部分を見直します。目標テンポの半分で弾いてみると、暗譜の確認にとても有効です。
メンタル面については、自信を持てるよう難所を克服しておくこと、そして人前で弾き慣れることに尽きます。ご家族相手でもかまいません。きちんとお辞儀から始め、一度限りの本番形式で演奏することを勧めています。
ーー応募時に音源データの提出が必要な場合、そのクオリティは審査に影響しますか。影響する場合、望ましい音源の条件をお聞かせください。
坪川
できるだけ録音状態の良し悪しを差し引いて審査するよう努めていますが、聴き取りにくいほど録音状態が悪い、あるいは金属的な音になっている場合は、どうしても影響します。
ただ、近年はスマートフォンでもかなり良い音で録れますし、昨年からデータ提出となって以降、録音状態の悪いものは減りました。それ以前はカセットテープも数本あり、何度も頭から上書きされたためか、まるで歴史的録音のような音質のものもありました。また、再生不能なMDやCDが毎年ありましたが、データ提出になってからはそうした失格がなくなり、とても嬉しく思います。
録音クオリティは高いに越したことはありませんが、過度なリバーブやノイズキャンセリングを施した録音は好ましくありません。加工は行わないほうが無難だと思います。浴室で録ったような音のものが見受けられることもありますし、スタジオを借りて録音される方もいますが、大きな雑音さえなければ、通常の部屋で十分だと考えます。
ーー 全日本アマチュアギターコンクールへの参加を検討している方や、音楽を志すすべての方へメッセージをお願いします。
坪川
「コンクールに挑戦するのは、もっと上達してから」と参加を先延ばしにしている人にこそお勧めしたいコンクールです。コンクールは、まず応募することで練習が進み、上達につながるのが一番のメリットだと思います。録音して自分の演奏を客観的に聴くのも勉強になります。たとえ録音予選で落ちてもアドバイスがもらえますし、「ステージ予選に出て知り合いが増え、ギターライフがさらに楽しくなった!」という声も多いです。
「音楽」という漢字が示すとおり、何より楽しむことが第一だと思います。コンクールに参加し、さらに上位入賞を目指すようになると、楽しい練習だけでは済まなくなってくるでしょうが、それも含めてとにかく楽しんでいただきたいと思っています。仲間と弾き合い会をされている方も多いです。人前で弾くことは苦しいことではなく、楽しいことになれば、きっとハマってしまうこと間違いなしです!
全日本アマチュアギターコンクールでは、ステージ予選での直筆コメントや、他のコンクールで3位以内入賞経験者・学生をあえて対象外にして「はじめての喜び」に光を当てる方針にも、厳しさとやさしさの両方を感じました。
坪川先生のお話からは、配点に明快な軸をお持ちでありながら、評価の中心に据えられているのは細かな減点ではなく「音楽の呼吸」と「歌い回し」。一音一音を大切に聴いておられることが伝わってきます。また、部分練習や運指の見直し、暗譜を半分のテンポで確かめる工夫、そして本番形式の練習——いずれも今日から取り入れられる実践的なヒントだと感じます。
「まず応募することで練習が動き出す」という言葉どおり、挑戦は日常を少しずつ変えていく。一歩踏み出す人に、舞台は必ず応える。その確信を、今年の本選の「美しい音の流れ」とともに、坪川先生のお言葉がやさしく示してくださいました。背中を押す数々のヒントと温かなエールに、心より御礼申し上げます。
第27回全日本アマチュアギターコンクール 2026年8月22日(土)三鷹市芸術文化センター 風のホール
予選課題(録音予選):ヘンツェ《ノクターン》※繰り返し省略
ステージ予選(公開審査):ソル《魔笛の主題による変奏曲 Op.9》より〈テーマ〉
使用楽譜:『発表会用ギター名曲集』(現代ギター社版)※運指・スラーは自由
また、このたび 「第1回アマコン・オンライン」 の開催が決定。
演奏動画の送付にて、当コンクール審査員5名からコメントをお返しします。アマコンのリピーターの方、初心者の方、家庭の事情や遠方で首都圏のコンクール参加が難しい方も、ワンレッスン感覚 でぜひお気軽にご参加ください。(詳細は当協会HPをご覧ください。)
第26回全日本アマチュアギターコンクールの概要については下記をご覧ください。
第26回全日本アマチュアギターコンクールの結果については下記をご覧ください。


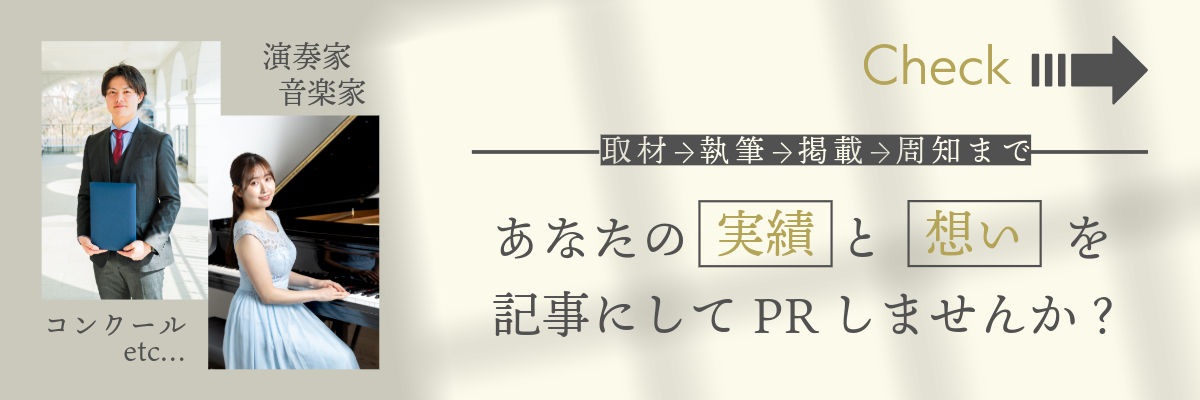



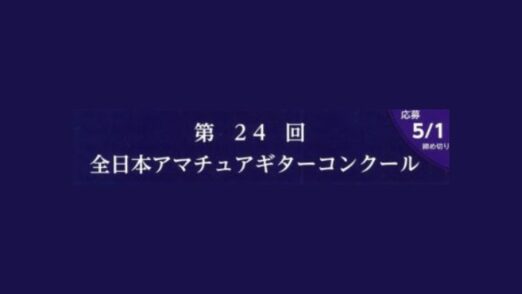
-522x294.jpg)
-522x294.jpg)