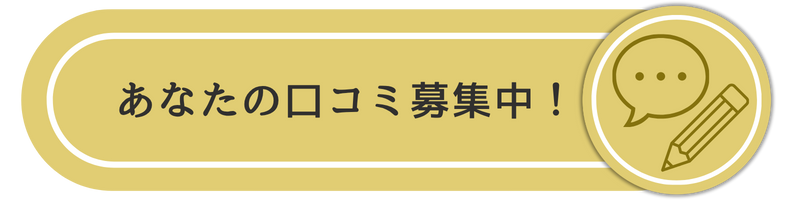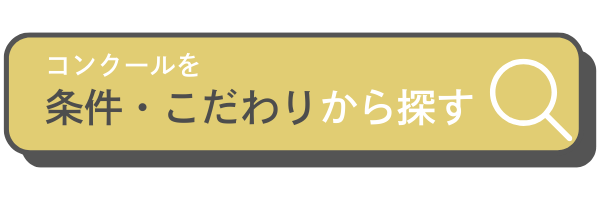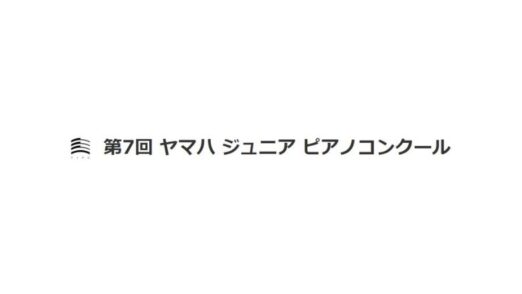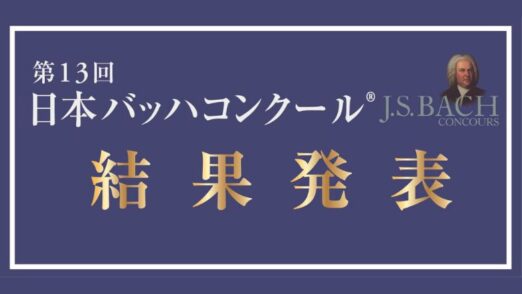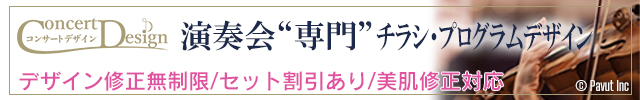参加者30名が公式発表される
米テキサス州フォートワースで今年5月21日から開催される「第17回ヴァン・クライバーン国際ピアノコンクール」の本戦出場者30名が、現地時間4月9日に公式発表されました。
応募総数340名から映像審査を経て77名が3月の予備選考(スクリーニング・オーディション)に進み、そこでの演奏(各25分リサイタル)を経て選ばれた精鋭30名です。
出場者の年齢は18歳から30歳(平均25歳)と若く、出身は17の国と地域にわたり非常に国際色豊かな顔ぶれとなりました。最多出身国は中国の7名で、次いで米国とロシアが各4名などとなっています。
日本からは重森光太郎(25)と山﨑亮汰(26)の2名が選出されており、日本勢の健闘が光ります。
発表された出場者一覧(名前と国籍)
今回発表された本戦出場30名のピアニストは以下の通りです。
- Piotr Alexewicz(ポーランド)
- Jonas Aumiller(ドイツ)
- Alice Burla(カナダ)
- Yangrui Cai 蔡陽睿(中国)
- Elia Cecino(イタリア)
- Yanjun Chen 陈艳君(中国)
- Jiarui Cheng 程嘉睿(中国)
- Federico Gad Crema(イタリア)
- Shangru Du 杜尚儒(中国)
- Roman Fediurko Роман Федюрко(ウクライナ)
- Magdalene Ho(マレーシア)
- Carter Johnson(カナダ/アメリカ)
- Xiaofu Ju 鞠小夫(中国)
- Mikhail Kambarov Михаил Камбаров(ロシア)
- David Khrikuli(ジョージア)
- Pedro López Salas(スペイン)
- Philipp Lynov Филипп Лынов(ロシア)
- Jonathan Mamora(アメリカ)
- Callum McLachlan(イギリス)
- Evren Ozel(アメリカ)
- Chaeyoung Park 박채영(韓国)
- Korkmaz Can Sağlam(トルコ)
- Aristo Sham 沈靖韜(香港/中国)
- 重森光太郎 (Kotaro Shigemori)(日本)
- Vitaly Starikov Виталий Стариков(イスラエル/ロシア)
- Anastasia Vorotnaya(ロシア)
- Angel Stanislav Wang(アメリカ)
- Xuanxiang Wu 武暄翔(中国)
- 山﨑亮汰 (Ryota Yamazaki)(日本)
- Sung Ho Yoo 유성호(韓国)
以上30名(50音順ではなく姓アルファベット順)。
カナダ/アメリカやイスラエル/ロシアなど二重表記は二重国籍または多国籍の経歴を示しています。
このリストからも、欧米とアジアを中心に世界各地から才能が集まっていることがわかります。
日本人出場者の横顔と実績
今回、日本から本戦に進むことになった重森光太郎さんと山﨑亮汰さんのプロフィールにも注目が集まります。
重森光太郎(25)は東京・桐朋学園大学で学んだ後、現在フランスに渡って研鑽を積んでいる俊英です。6歳で母親にピアノを習い始め才能を伸ばし、2022年のロン=ティボー国際コンクールで第4位に入賞、第6回石川国際ピアノコンクールでも第3位と聴衆賞を受賞するなど国際コンクールでの実績を重ねています。
国内コンクールでも数多くの賞歴があり、「世界で活躍できるピアニスト」の一人として認められる存在です。
2023年からはパリのエコールノルマル音楽院に留学し、著名教師レナ・シェシェフスカヤ氏に師事するなどグローバルな視野で研鑽を積んでおり、東京フィルハーモニー交響楽団との共演やフランス・パリでの演奏経験も持ちます。重森さんは「音楽を通じて聴衆の心を癒やしたい」という信念を掲げる実力派です。
一方、山﨑亮汰(26)は福島県出身。7歳からピアノを始めると国内外のジュニアコンクールで頭角を現し、17歳で米クリーブランド管弦楽団と共演する快挙を遂げています(同年、米国のクーパー国際コンクールで優勝)。桐朋学園大学で二宮裕子氏に師事したのち、現在は渡米してロサンゼルスのコルバーン音楽院でファビオ・ビディーニ氏のもと研鑽中です。
国際大会でも輝かしい成果を収めており、2023年のブゾーニ国際ピアノコンクールで第3位を獲得したほか、ボルツァーノ・ハイドン管弦楽団(伊)、読売日本交響楽団、日本フィルハーモニー交響楽団、東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団など国内外の主要オーケストラと共演してきました。
さらに15歳の時には日本音楽コンクールで最年少グランプリに輝き、日本フィルとプロコフィエフのピアノ協奏曲第3番を演奏した実績も持ちます。
「クラシック音楽を未来へ継承するには新しい試みで新たな聴衆を開拓することが大切」という信念を持ち、ショッピングモールや駅での無料演奏会(Japan Music Summitへの参加)にも積極的に取り組むなど、演奏活動の幅も広げています。
多彩な顔ぶれ:国際的広がりと教育背景
30名の出場者はアジア・北米・ヨーロッパの各地域からバランスよく選ばれており、中国や韓国、日本といった東アジア勢、欧州からはポーランドやイタリア、ロシア、英国、スペイン、ジョージア(グルジア)など、北米からも米国やカナダといった具合に、世界17の国・地域に及ぶ多国籍な構成です。
その内訳を見ると、中国出身者が7名と群を抜いて多く、次いで米国とロシアが各4名、韓国2名、そして日本が2名で続きます。年齢分布は18歳から30歳までと幅広いですが、平均年齢は25歳と20代中盤の若手が中心です。最年少は18歳のウー・シュエンシャンさん(武暄翔、中国)で、最年長は30歳の出場者が数名(米国やロシア出身者など)となっています。
音楽教育の背景に目を向けると、各国の一流音楽院や名教師のもとで研鑽を積んだ人材が集まっていることも特徴です。例えば日本の重森さんは東京の桐朋学園で学んだ後フランス留学、山﨑さんも桐朋から米国コルバーン音楽院に留学しています。同様に、中国出身者の中には欧米の音楽大学で学ぶ者、ロシアや欧米出身の参加者でも他国で研鑽を積む者が多く、若手ピアニストたちが国境を越えて腕を磨いている現状が反映されたラインナップと言えるでしょう。
また、既に他の国際コンクールで実績を残している参加者も少なくありません。上述の日本勢以外にも、たとえば韓国のパク・チェヨンさん(Chaeyoung Park)は過去にリーズ国際コンクールで入賞経験があり、カナダ出身のアリス・バーラさん(Alice Burla)は若くして注目された経歴を持つなど、それぞれ輝かしいキャリアの一端を引提げての挑戦となります(※各出場者の詳細プロフィールは大会公式サイトで公開されています)。
このように、世界中から選び抜かれた精鋭たちが集う本大会は、その顔ぶれだけでもピアノ界の次世代を担うスター候補の国際ショーケースとなっています。
主催者の視点:選考過程と期待のコメント
今回の30名選出にあたっては、まず世界各地から集まった340名の応募者の映像審査を経て、著名ピアニストを含む審査パネルが150名を推薦し、さらにフィリップ・ビアンコーニ氏(フランス)、アレクサンダー・コブリン氏(米国)、児玉桃氏(日本)ら5名のスクリーニング審査員が77名をフォートワースでの予備選考に招待、最終的に5日間の公開オーディションで30名を選抜するという綿密なプロセスが踏まれました。
主催するクライバーン財団のジャック・マーキスCEOは選考を終え、「応募者の演奏技術や情熱の高さに深く感銘を受けた。クライバーンという場が、彼らの音楽的ビジョンを表現する国際的な舞台を提供できることを光栄に思う」とコメントしています。
実際、同コンクールは「クラシック音楽界で最も権威あるコンテストの一つ」と評される存在であり、1962年の創設以来、若手ピアニストのキャリアを世界規模で飛躍させてきました。前回大会(2022年)の優勝者ユンチャン・イムさん(韓国)は史上最年少での快挙となり、その後世界的な活躍を見せています。
また、日本の辻井伸行さんも2009年大会での優勝(同率)を機に国際的キャリアを築いた一人であり、今回選ばれたピアニストたちにも同様の飛躍が期待されています。
日本国内への意味と展望
この出場者発表は日本のピアノ界にも少なからぬ波及効果を持つと見られます。
まず、日本人が2名も世界最高峰の一つである本コンクール本戦に名を連ねたことは、国内の若いピアニストや学生にとって大きな励みとなるでしょう。実際、クライバーン本戦は参加枠30名と狭き門であり(例えばショパン国際ピアノコンクールは約80名が本戦参加)、その舞台に立つだけでも名誉と言われます。
そうした厳しい選考を勝ち抜いた日本人2名の存在は、国内の音楽教育機関にとっても自信と誇りとなり、指導者たちが世界に通用する人材を育成している証とも言えます。重森さんと山﨑さんはいずれも国内で研鑽を積んだ後に海外留学し研鑽を深めた経歴であり、日本の音楽教育と国際経験の両輪の重要性を示す好例とも言えるでしょう。
また、この発表は日本のクラシック音楽ファンや関係者にとっても大きな関心事であり、専門メディアが速報で伝えるなど注目度も高くなっています。本大会は5月下旬から開幕し、その模様はすべて公式YouTubeチャンネル等で生配信されます。日本から出場する2人の活躍次第では、辻井伸行さん以来の快挙への期待も高まります。特に山﨑さん・重森さんの両名は、この発表後すぐにショパン国際コンクールの予備予選(4月下旬開催)にも出場予定であることが明らかになっており、同世代の世界的コンクールに連続して挑む姿は国内の後進に大きな刺激を与えるでしょう。
日本の音楽教育界にとっても、こうした才能の国際舞台での活躍はカリキュラム充実や海外との交流推進などの動機づけとなり得ます。総じて、今回の出場者発表は、日本のピアニストが世界へ羽ばたく好機であると同時に、日本の音楽界全体にさらなる研鑽と国際志向を促すニュースと言えそうです。
Sources:
The Cliburn Foundation 公式発表・プレスリリース
クライバーン国際コンクール 公式サイト 出場者プロフィール